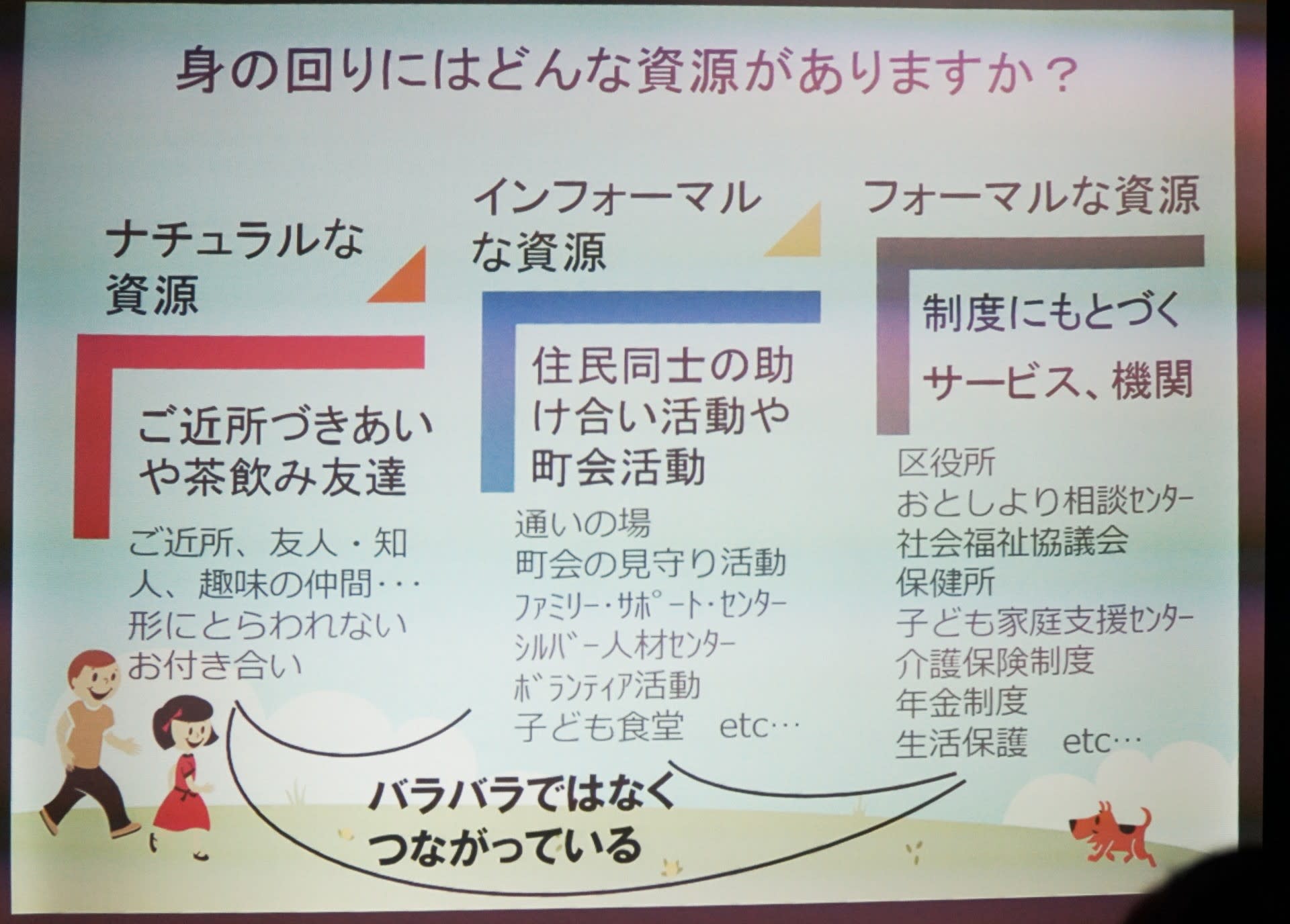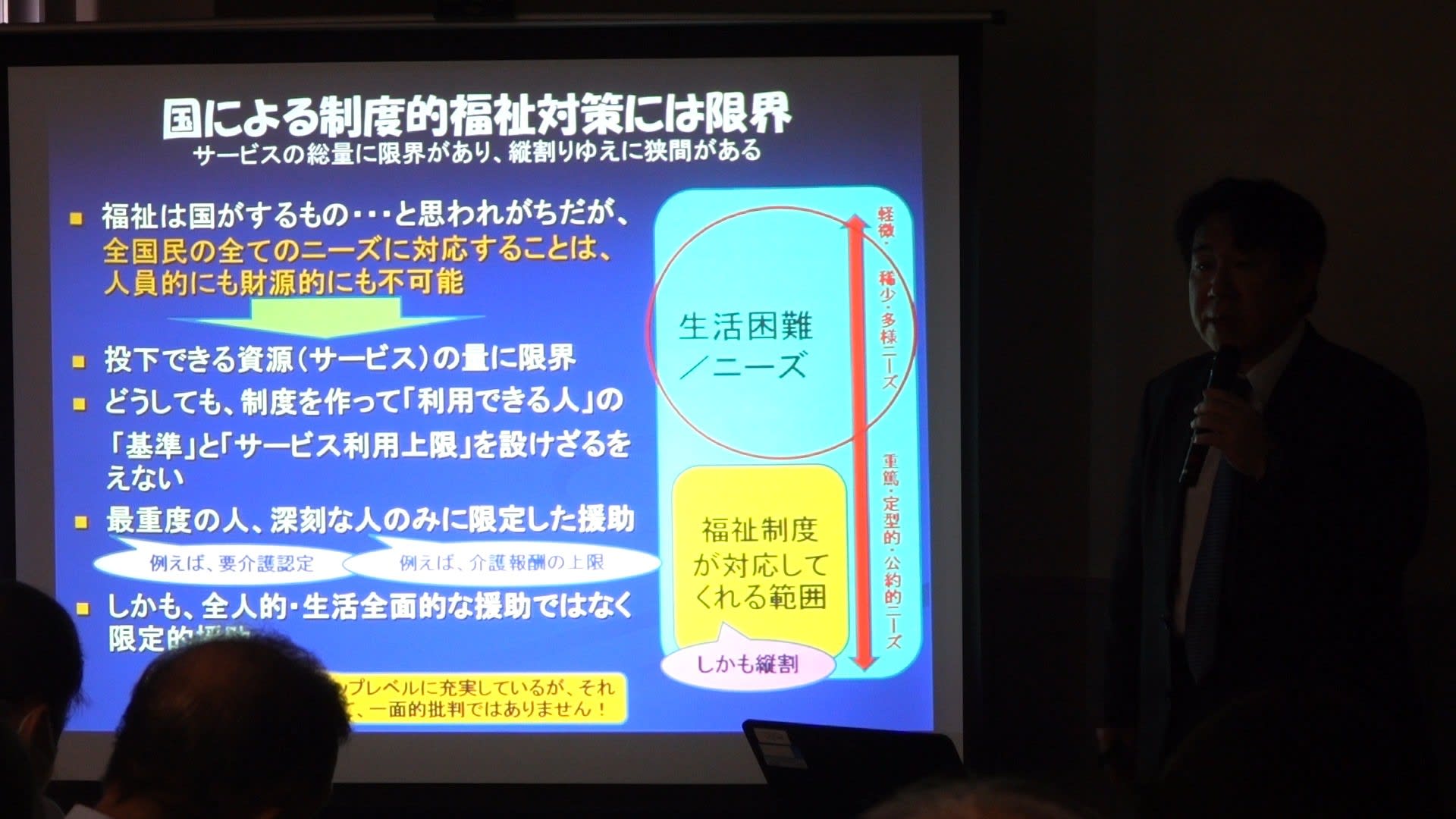東京大学 先端科学技術研究センター 准教授 熊谷 晋一郎


本日紹介する当事者研究とは、2001年に北海道で誕生した新しい取り組みです。ここでいう当事者とは、障害や病気、貧困や差別、子育てや介助、そのほかにも刑務所出所後の暮らしの困難など、何らかの苦労を抱えた本人のことです。こうした苦労のメカニズムの分析や対処法の考案は、専門家に任せきりにすることが多いものですが、専門家の知識や経験にも限界があるので、当事者の視点から見ると方向性がずれたり、かゆいところに手が届かなかったりといった場合もあります。当事者研究は、苦労を抱えた本人が研究者になって、似た苦労を持つ仲間と協力しつつ、メカニズムや対処法について研究する取り組みです。
自閉スペクトラム症の診断を持つ研究者である綾屋紗月氏によれば、当事者研究は、先行する2つの当事者活動から多大な影響を受けています。
1つ目は、障害者自立生活運動などを含む「障害者運動」です。そしてもう1つは、12ステップと呼ばれるプログラムに沿ってアルコールや薬物の依存症からの回復に取り組む、1930年代にアメリカで誕生した「依存症自助グループ」です。
かつて障害は、例えば自力では階段をのぼれない身体の中に宿るものであるという考えが主流でした。
これを、障害の「医学モデル」と言います。しかし、医学モデルの下で行われるリハビリ訓練や手術などで、無理に障害者を健常者に近づけようとすることには限界があり、本人の身体や尊厳を傷つける場合も少なくありませんでした。その後、医学モデルを批判した障害者運動は、エレベーターのない建物や、手話を言語として認めない人的環境の中にこそ障害が存在するという「障害の社会モデル」という理念を打ち出しました。そして、等身大の心や体のままでも平等な機会が保障される社会の実現こそが必要だと主張しました。


医学モデルで捉えた障害をインペアメント、社会モデルで捉えた障害をディスアビリティと言って区別することもあります。社会モデルの考え方は今日も、多様性、共生社会、インクルージョンなどといった概念として受け継がれています。
もう一つの依存症自助グループは、周囲の人々を信頼して、弱さや限界を抱えた等身大の自分を正直に開示し、身近な他者と分かち合うことが困難な状態、言い換えると、人に依存できない状態こそが依存症であるという発見をしました。その背後にはしばしば、戦争や暴力からの被害や、社会からの排除など、人間や社会への不信感が強くならざるを得ないような出来事が影響しています。自助グループは、専門家でさえさじを投げた依存症について、当事者同士で、正直に、自分たちの経験を語り合う自助グループ活動の効果を示すことに成功しました。


障害者運動と依存症自助グループは、専門家が見落としてきた価値観や知識、実践方法を、当事者が中心となって発見し、世の中に広めていった代表的な当事者活動です。そして、弱さや限界を抱えた等身大の自分を、まずは自分が受け入れ、次に社会に受け入れてもらうよう働きかけていくという点で、多様性を認める共生社会の実現の方向を向いていました。そして、北海道の浦河町にある、精神障害のある人々の活動拠点である「浦河べてるの家」で、この2つの当事者活動を精神障害の現場に応用しようとする中で、当事者研究という方法が誕生したのです。
当事者研究は、障害者運動と依存症自助グループの、それぞれの長所を受け継いでいます。例えば障害者運動は、未来の社会を変革しようとする傾向が強く、過去の振り返りや自己変革の要素が相対的に弱い傾向がありました。一方依存症自助グループは、当事者の語りをグループの外部には持ち出さず、社会変革を目指さない運営方針を取っていました。当事者研究は、明示的には社会変革を謳っていませんが、自助グループから受け継いだ等身大の正直な語りを、グループの外部に公開することで、自ずと社会の価値や知識が変革されていくという特徴があります。
当初、精神障害の領域で始まった当事者研究は、その後、発達障害、慢性疼痛、聴覚障害者、認知症、吃音者、ホームレス状態の人々、トップアスリート、企業、こども、特別支援教育の現場など、障害や病気の有無を超えて、広く様々な苦労を抱えた当事者へと急速に広まっています。こうした現場の共通点は、既存の専門家の言葉や、既存の当事者グループの言葉では十分に自分の苦労を表現できない人々が集まっているという点です。1930年代の依存症者や1960年代の身体障害者は、自分を語る十分な言葉を持っておらず、それを生み出す必要がありました。今や、彼らは多くの自分を語る言葉を持っているかもしれませんが、その傍らで、未だそうした言葉を持っていない当事者が置き去りにされています。当事者研究は、言葉のなかった経験に、言葉を生み出す実践です。したがって、その時代その時代で置き去りにされている人々の間で、最も活発に展開していくでしょう。
最近では興味深いことに、マジョリティの当事者研究も始まっています。2000年以降の急速な社会構造の変化によって、マジョリティの中に「新たな苦労を抱えた人」が多く発生しています。苦労を抱えているにもかかわらず、自分の側にそれを説明できる特徴を持たない彼らは、最も言語が足りていない当事者かもしれません。そして、どうして自分たちはがんばっても親世代のような生活をできないのか、その理由を探しあぐねるうちに、すでに苦労が可視化されたマイノリティのことを既得権益相と誤認し、彼らへの敵意を持ってしまうこともあるでしょう。マジョリティの当事者研究は、マジョリティが自らの被害者性を弱者への加害へと転嫁せず、新しい困難を説明する言葉を編み上げ、苦労の帰属先を慎重に見定め、インクルーシブな社会へと水路づけようとする試みと言えるでしょう。
在野で始まった当事者研究は、徐々に、大学とも連携を始めています。


東京大学先端科学技術研究センターでは2015年に、当事者研究分野という新しい講座が設立されました。2018年に東京大学では、様々な研究分野に障害のある当事者の視点を取り入れるべく、当事者研究者雇用制度を試行的にスタートしています。さらに2019年から、「すべての人によるすべての人のためのインクルーシブなアカデミア」を実現するために、人的・物的支援を充実させるためのインクルーシブ・デザイン・ラボプロジェクトをスタートします。
アカデミアへの当事者参画は、国際的にも重視されつつあります。例えば、市民や当事者が、研究費の配分、仮説の提示、実験、分析、結果の解釈と公開など、研究のすべての段階をリードし、専門家とともに科学技術を推進する取り組みが、2018年に雑誌Natureで特集されたり、精神医学領域の権威ある雑誌であるLancet Psychiatryが査読者の中に精神障害のある当事者を加える方針を打ち出したりといった例が挙げられます。科学技術の進歩だけでなく、それへの信頼を高める上でも、重要な取り組みです。
当事者研究は、少数派と専門家、苦労の種類が異なる少数派同士、多数派と少数派など、私たちを分断する様々な壁を乗り越える力を持っています。
すべての人が、弱さを抱えた等身大の自分を正直に見つめ、分かち合うことからしか、共生社会は実現しないでしょう。