久しぶりに読み応えのある経済書に出会ったね。浅沼信爾・小浜裕久両先生の「途上国の旅・開発政策のナラティブ」だ。経済学は、本来、経国済民の学であり、国と民をいかに富ませるかが問われる。そのリアルさを知ることができる好著だと思う。途上国に関心のある人に限らず、経済を学ぶ人に広く読まれて欲しいものだ。
………
著者の総括的な主張は、至って普通のことだ。序章や終章で示されるとおり、経済発展には、決定的な時期というものがあり、それを活かす指導者層のコミットメントとテクノクラートの見識が欠かせず、事前には有効な戦略や政策は知り得ないから、状況に応じて選ばねばならないというものである。そして、そうした普通のことの実践が、どれほど困難で、知恵が要るかが描かれている。
経済学をひと通り学ぶと、市場メカニズムという「神の見えざる手」が自然に発展をもたらしてくれる気になるが、それを有効に機能させるには、様々な政治的、社会的条件を整えなければならない。それらは決して容易でない上に、整えたからといって、必ずしも上手く行くものでもない。しかも、そうなる理由を経済学は教えてくれない。あくまでも、その時々で会得しなければならないのである。
「ナラティブ」では、輸出志向型政策で成功を収めたマレーシア、シンガポール、韓国とともに、輸入代替型政策で失敗したガーナ、アルゼンチンも紹介されている。指導者もテクノクラートもだらしなかったガーナを見ると、若い読者は、先進国の日本には縁遠い問題のように思われるかもしれないが、それは驕りというものだ。アルゼンチンという戦前の先進国から転落した例もある。
歴史を顧みて、明治国家が指導者の選抜と官僚制の整備にいかに心血を注いだかを思い起こしてほしい。それらは、在って当たり前のものではなく、不断の努力によって得られるものである。加えて、戦前の指導者が国際情勢に幻想を持ち、軍という官僚制が暴走し、滅亡の縁まで至ったことも忘れてはなるまい。指導者と官僚制に、いかに現実的なビジョンを持たせ、コンセンサスを得させるかは、終わりなき課題だ。
………
「ナラティブ」で興味深いのは、「途上国」だった戦後日本の経験にも1章を割いていることだ。そこでは、「日本は輸出主導的ではなかったが、輸出に向け効率向上に熱心だった」ことがポイントとして挙げられている。これは定説ではあるが、本コラムの読者には、経済全体に占める割合が小さくとも、追加的な輸出需要が投資促進にいかに決定的かは、つとに説明してきたところである。
戦後日本の凄さは、その重要性を、理論でなしに、現実感覚でつかみ取ったところにある。当時は、経済学者による国内開発の主張も有力であって、指導者が間違った選択をする可能性もあった。1940年代後半には、社会党政権が炭鉱の国家管理を目指す一幕もあり、自由主義的な経済体制の選択すら必然とは言えない。
日本が戦後混乱期の補助金依存から市場経済への復帰を果たしたのは、1949~50年における、強力なデフレ政策の「ドッジライン」によるが、この成功には偶然の要素がある。もし、朝鮮特需がなければ、あまりの痛みのために挫折していたかもしれない。緊縮だけで、外需がなければ、今のギリシャのような政治的、経済的な苦境に喘ぐことになっていただろう。
その後、日本は高度成長へと向かう決定的な時期を迎える。このチャンスを捕まえた、指導者の池田勇人やテクノクラートの下村治の役割は特筆に価する。いまや常識である輸出をテコにした高度成長も、当時は未知のものであった。批判を受けつつも、可能性を見出し、思い切った積極策に打って出て、それで獲得した成果である。税収が読めるほどの池田の財政運営の力量、成長力を数字で裏付けた下村の見識なくしては成し得なかった。
………
残念ながら、今の日本の指導者層の持つビジョンは、欧米からの借りもののように思われる。日本の現実を見据え、自ら創り出した、池田や下村のそれとは違う。需要の乏しさに苦闘する庶民の姿は見えず、金融万能・緊縮財政の理論の正しさを疑うこともしない。さらに、今のテクノクラートは、由らしむるために、税の自然増収を分からなくし、財政がどれほど需要を抜くかも知らせず、現実から目を逸らさせている。
「ナラティブ」は、ようやく回復の道を歩み始めたガーナについて、「試みが失敗して初めて、厳しい現実に直面して初めて、思想を支配してきた理論の呪縛から解放され、現実的な戦略と政策が取れるようになった」としている。国を誤るのも、民を富ますのも、どれだけ現実に即した政策を取れるかだが、往々にして、悲惨な目に会わなければ目が覚めないものだ。これは国家や時代を問わない真実として例を重ねて行くに違いない。
(今日の日経)
損保ジャパンが英社買収。日・ASEAN共同宣言。来年度の政府成長率1.3%。国債発行180兆円前後。SC開業60件超に回復。
………
著者の総括的な主張は、至って普通のことだ。序章や終章で示されるとおり、経済発展には、決定的な時期というものがあり、それを活かす指導者層のコミットメントとテクノクラートの見識が欠かせず、事前には有効な戦略や政策は知り得ないから、状況に応じて選ばねばならないというものである。そして、そうした普通のことの実践が、どれほど困難で、知恵が要るかが描かれている。
経済学をひと通り学ぶと、市場メカニズムという「神の見えざる手」が自然に発展をもたらしてくれる気になるが、それを有効に機能させるには、様々な政治的、社会的条件を整えなければならない。それらは決して容易でない上に、整えたからといって、必ずしも上手く行くものでもない。しかも、そうなる理由を経済学は教えてくれない。あくまでも、その時々で会得しなければならないのである。
「ナラティブ」では、輸出志向型政策で成功を収めたマレーシア、シンガポール、韓国とともに、輸入代替型政策で失敗したガーナ、アルゼンチンも紹介されている。指導者もテクノクラートもだらしなかったガーナを見ると、若い読者は、先進国の日本には縁遠い問題のように思われるかもしれないが、それは驕りというものだ。アルゼンチンという戦前の先進国から転落した例もある。
歴史を顧みて、明治国家が指導者の選抜と官僚制の整備にいかに心血を注いだかを思い起こしてほしい。それらは、在って当たり前のものではなく、不断の努力によって得られるものである。加えて、戦前の指導者が国際情勢に幻想を持ち、軍という官僚制が暴走し、滅亡の縁まで至ったことも忘れてはなるまい。指導者と官僚制に、いかに現実的なビジョンを持たせ、コンセンサスを得させるかは、終わりなき課題だ。
………
「ナラティブ」で興味深いのは、「途上国」だった戦後日本の経験にも1章を割いていることだ。そこでは、「日本は輸出主導的ではなかったが、輸出に向け効率向上に熱心だった」ことがポイントとして挙げられている。これは定説ではあるが、本コラムの読者には、経済全体に占める割合が小さくとも、追加的な輸出需要が投資促進にいかに決定的かは、つとに説明してきたところである。
戦後日本の凄さは、その重要性を、理論でなしに、現実感覚でつかみ取ったところにある。当時は、経済学者による国内開発の主張も有力であって、指導者が間違った選択をする可能性もあった。1940年代後半には、社会党政権が炭鉱の国家管理を目指す一幕もあり、自由主義的な経済体制の選択すら必然とは言えない。
日本が戦後混乱期の補助金依存から市場経済への復帰を果たしたのは、1949~50年における、強力なデフレ政策の「ドッジライン」によるが、この成功には偶然の要素がある。もし、朝鮮特需がなければ、あまりの痛みのために挫折していたかもしれない。緊縮だけで、外需がなければ、今のギリシャのような政治的、経済的な苦境に喘ぐことになっていただろう。
その後、日本は高度成長へと向かう決定的な時期を迎える。このチャンスを捕まえた、指導者の池田勇人やテクノクラートの下村治の役割は特筆に価する。いまや常識である輸出をテコにした高度成長も、当時は未知のものであった。批判を受けつつも、可能性を見出し、思い切った積極策に打って出て、それで獲得した成果である。税収が読めるほどの池田の財政運営の力量、成長力を数字で裏付けた下村の見識なくしては成し得なかった。
………
残念ながら、今の日本の指導者層の持つビジョンは、欧米からの借りもののように思われる。日本の現実を見据え、自ら創り出した、池田や下村のそれとは違う。需要の乏しさに苦闘する庶民の姿は見えず、金融万能・緊縮財政の理論の正しさを疑うこともしない。さらに、今のテクノクラートは、由らしむるために、税の自然増収を分からなくし、財政がどれほど需要を抜くかも知らせず、現実から目を逸らさせている。
「ナラティブ」は、ようやく回復の道を歩み始めたガーナについて、「試みが失敗して初めて、厳しい現実に直面して初めて、思想を支配してきた理論の呪縛から解放され、現実的な戦略と政策が取れるようになった」としている。国を誤るのも、民を富ますのも、どれだけ現実に即した政策を取れるかだが、往々にして、悲惨な目に会わなければ目が覚めないものだ。これは国家や時代を問わない真実として例を重ねて行くに違いない。
(今日の日経)
損保ジャパンが英社買収。日・ASEAN共同宣言。来年度の政府成長率1.3%。国債発行180兆円前後。SC開業60件超に回復。












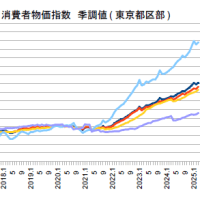













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます