2冊目はこちら。
ブックオフ商法については、わたしなどがイチャモンをつけなくても様々な方面から批判は寄せられている。たとえば万引き問題。
新刊書店から万引きを行い、ブックオフにそのまま売り払う犯罪は後を絶たない。それどころか出版社の人間が在庫を持ち込んだり、新刊書店員がブックオフから古書を買い、スリップ(本の中にはさみこんである売り上げ伝票)を入れて取次に返品したりする裏技まで報告されている。ブックオフの出現が、流通のモラルを低下させているというわけだ。ちなみに、ブックオフ自身は「やまびこ方式」と呼ばれる万引き対策をとっている。ひとりが「いらっしゃいませ」と言ったらフロアの全スタッフが「いらっしゃいませぇ!」と応え、フロア全員が“監視している”ことを印象づけようとしているのだ。うるさいだけのかけ声じゃなかったんだなー。
しかしわたしがブックオフに批判的なのはこんな理由ではない。本の価値を鮮度だけで判断していいのか、文化的存在として……なーんて「良書だけ擁護」派だからでもない。最大の問題は、ブックオフのあふれるほどの利潤が、書き手に全然還元されていないところにある。出版界の現状に色々な問題があることは理解できる。本屋に注文してもなかなか顧客に本が届かない理由はいくら考えても納得できないし、書店が値付けを行う必要のない(つけられない)再版制度が疲弊していることも確かだ。でも、著作権者が利益を得られない業界に明日はないはず。優秀な書き手を育てるのは、それだけではないにしろ経済的保障ではないか。その観点がブックオフからは完全に抜け落ちている。
ブックオフは単品管理をしていない(!)から作家への還元は事実上無理だの、中古車を売るときにメーカーに利潤は入らないでしょう?だのと理屈をこねているけれど、だとしたら新古書店という存在には文句なく根本的な欠点がある、ここから話を始めなければ意味がない。
ブックオフは必要だと思う。旧弊な業界に一撃を加えたことは確かだし。でも不可欠な存在としてこれからも在ろうと思えば、著作権料というハードルは無視できないはずだ。そうでもなければ、単なる『必要悪』という鬼っ子のままだろう。え?もう売り上げの半分以上はDVDやゲームソフトになっているからうるさいことは言うな?そっちの著作権料の方が緊急課題だっ!
※その後、創業者の所得隠しなどでブックオフのうさん臭さは次第に露わになっている。しかし、中古ピアノの転売でもうけたアイデア社長一族の影響を排除することは、新古書店の社会的存在意義を高めるうえで絶対に必要だ。
画像は、怒濤の不倫小説「夜の果てまで」泣ける。盛田隆二はホントにいいです。
 若い頃、友人の家を訪ねたときだった。きこえてくる家族の談笑にわたしは本当におどろき、チャイムを押すのをためらった。
若い頃、友人の家を訪ねたときだった。きこえてくる家族の談笑にわたしは本当におどろき、チャイムを押すのをためらった。 このファミレス、女性には圧倒的におすすめ。でもわたしのような中年男が再び訪れるのはやっぱりきついかも。味は最高なんだけど、なにしろ料理人のレシピの解説とかがうるさそうだし(笑)。
このファミレス、女性には圧倒的におすすめ。でもわたしのような中年男が再び訪れるのはやっぱりきついかも。味は最高なんだけど、なにしろ料理人のレシピの解説とかがうるさそうだし(笑)。









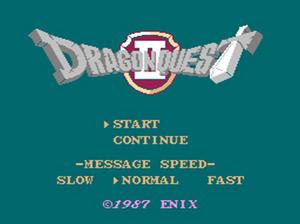 中年の教員ドラクエファンたちの泣き言の数々。
中年の教員ドラクエファンたちの泣き言の数々。
 「あー面白かった」
「あー面白かった」 さて、色々といちゃもんをつけさせてもらったけど、どうして日本で「
さて、色々といちゃもんをつけさせてもらったけど、どうして日本で「 (
( 決してレベルが低い作品ではないと思いますが、宮崎作品としては可もなく不可もなく、という気が。あの
決してレベルが低い作品ではないと思いますが、宮崎作品としては可もなく不可もなく、という気が。あの 中の上?
中の上? 評価分かれまくりハウル。どうせロングランされるんだから劇場が空き始めてからチェックしようと思ったけれど、こうなったら早いとこ観ておかねば……
評価分かれまくりハウル。どうせロングランされるんだから劇場が空き始めてからチェックしようと思ったけれど、こうなったら早いとこ観ておかねば…… 声優はみんな大正解。特に火の悪魔の我修院達也と、ハウルの弟子を演じた神木隆之介(「
声優はみんな大正解。特に火の悪魔の我修院達也と、ハウルの弟子を演じた神木隆之介(「 この映画に数々の批判、というか罵倒が寄せられていることはきいていた。これまでの
この映画に数々の批判、というか罵倒が寄せられていることはきいていた。これまでの 既に時事ネタとして消費し尽くされた感のある「電車男」。しかしこの物語には、味わうべき点がもっともっとあったと思う。
既に時事ネタとして消費し尽くされた感のある「電車男」。しかしこの物語には、味わうべき点がもっともっとあったと思う。 んもう韓流、韓流、韓流である。
んもう韓流、韓流、韓流である。

 。それにしてもみごとな装幀。
。それにしてもみごとな装幀。 本が売れない。一見「バカの壁」「
本が売れない。一見「バカの壁」「



