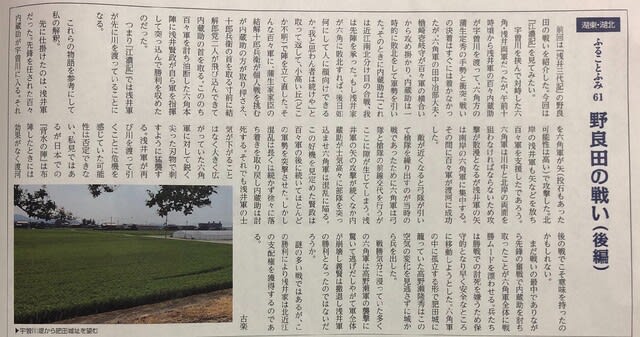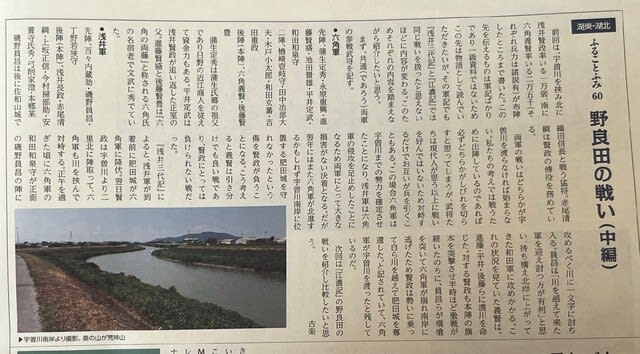前回は『浅井三代記』の野良田の戦いを紹介した。今回は『江濃記』を見てみたい。
宇曽川を挟んで対峙した六角・浅井両軍だったが、午前10時頃から浅井軍の百々内蔵助が宇曽川を渡って、六角方の蒲生定秀の手勢と衝突。戦いの決着はすぐには着かなかったが、六角軍の田中冶部大夫・楢崎壱岐守が百々軍の横合いから攻め掛かり、内蔵助は一時的に敗北をして軍勢を引いた。そのときに内蔵助は「これは近江南北分け目の合戦、我は先陣を承った。もし浅井家が六角に敗北すれば、後日如何にして人に顔向けできるか。我と思わん者は続けや」と取って返して、小高い丘(どこか不明)で陣を立て直した。そんな百々軍に、蒲生家家臣の結解十郎兵衛が個人戦を挑むが内蔵助の方が取り押さえ、十郎兵衛の首を取る寸前に結解郎党二人が飛び込んできて内蔵助の首を取る。こののち百々軍を討ち油断した六角本陣に浅井賢政が自ら軍を指揮して突っ込んで勝利を収めたのだった。
つまり『江濃記』では浅井軍が先に川を渡っていることになる。
これらの物語を参考にして私の解釈。
先に仕掛けたのは、浅井軍だった。先鋒を任された百々内蔵助が宇曽川に入る。それを六角軍が矢(投石もあった可能性は高い)で攻撃した。北岸の浅井軍も矢などを放ち百々軍を支援したであろう。六角軍は川中と北岸の両面を狙わなければならないため攻撃が散漫となるが浅井軍の矢は南岸の六角軍に集中する。その間に百々軍が渡河に成功した。
敵が近くなると弓隊が引いて槍隊を繰り出すのが当時の戦であったために六角軍は弓隊と槍隊の前線交代を行うがここに隙が生じてしまう。浅井軍の矢の攻撃が続くなか内蔵助が士気高々に部隊を突っ込ませ六角軍は混乱に陥る。この好機を見定めた賢政は百々軍の後に続いてほとんどの軍勢を突撃させた。しかし混乱は長くは続かず徐々に落ち着きを取り戻し内蔵助は討死する。それでも浅井軍の士気が下がることはなく大きく広がっていた六角軍に対して鋭く尖った刃物で刺すように猛襲する。浅井軍が再び川を渡って引くことに危機を感じていた可能性は否定できない、私見ではあるが日本での『背水の陣』は布陣したときには効果がなく渡河後の戦でこそ意味を持ったのかもしれない。
まだ戦いの最中でありながら先鋒の奮戦で内蔵助を討ち取ったことが六角軍全体に戦勝ムードを漂わせる。兵たちは勝戦での討死を嫌うため保守的となり早く安全なところに移動しようとした。六角軍の中に孤立する形で肥田城に籠っていた高野瀬隆秀はこの空気の変化を見逃さずに城から兵を出した。
戦勝気分に浸っていた多くの六角軍は高野瀬軍の襲撃に驚いて逃げだしやがて軍全体が崩壊し義賢は撤退し浅井軍の勝利となったのではないだろうか。
謎の多い戦ではあるが、この勝利により浅井家は北近江の支配権を獲得するのである。
宇曽川堤から肥田城址を望む

宇曽川を挟んで対峙した六角・浅井両軍だったが、午前10時頃から浅井軍の百々内蔵助が宇曽川を渡って、六角方の蒲生定秀の手勢と衝突。戦いの決着はすぐには着かなかったが、六角軍の田中冶部大夫・楢崎壱岐守が百々軍の横合いから攻め掛かり、内蔵助は一時的に敗北をして軍勢を引いた。そのときに内蔵助は「これは近江南北分け目の合戦、我は先陣を承った。もし浅井家が六角に敗北すれば、後日如何にして人に顔向けできるか。我と思わん者は続けや」と取って返して、小高い丘(どこか不明)で陣を立て直した。そんな百々軍に、蒲生家家臣の結解十郎兵衛が個人戦を挑むが内蔵助の方が取り押さえ、十郎兵衛の首を取る寸前に結解郎党二人が飛び込んできて内蔵助の首を取る。こののち百々軍を討ち油断した六角本陣に浅井賢政が自ら軍を指揮して突っ込んで勝利を収めたのだった。
つまり『江濃記』では浅井軍が先に川を渡っていることになる。
これらの物語を参考にして私の解釈。
先に仕掛けたのは、浅井軍だった。先鋒を任された百々内蔵助が宇曽川に入る。それを六角軍が矢(投石もあった可能性は高い)で攻撃した。北岸の浅井軍も矢などを放ち百々軍を支援したであろう。六角軍は川中と北岸の両面を狙わなければならないため攻撃が散漫となるが浅井軍の矢は南岸の六角軍に集中する。その間に百々軍が渡河に成功した。
敵が近くなると弓隊が引いて槍隊を繰り出すのが当時の戦であったために六角軍は弓隊と槍隊の前線交代を行うがここに隙が生じてしまう。浅井軍の矢の攻撃が続くなか内蔵助が士気高々に部隊を突っ込ませ六角軍は混乱に陥る。この好機を見定めた賢政は百々軍の後に続いてほとんどの軍勢を突撃させた。しかし混乱は長くは続かず徐々に落ち着きを取り戻し内蔵助は討死する。それでも浅井軍の士気が下がることはなく大きく広がっていた六角軍に対して鋭く尖った刃物で刺すように猛襲する。浅井軍が再び川を渡って引くことに危機を感じていた可能性は否定できない、私見ではあるが日本での『背水の陣』は布陣したときには効果がなく渡河後の戦でこそ意味を持ったのかもしれない。
まだ戦いの最中でありながら先鋒の奮戦で内蔵助を討ち取ったことが六角軍全体に戦勝ムードを漂わせる。兵たちは勝戦での討死を嫌うため保守的となり早く安全なところに移動しようとした。六角軍の中に孤立する形で肥田城に籠っていた高野瀬隆秀はこの空気の変化を見逃さずに城から兵を出した。
戦勝気分に浸っていた多くの六角軍は高野瀬軍の襲撃に驚いて逃げだしやがて軍全体が崩壊し義賢は撤退し浅井軍の勝利となったのではないだろうか。
謎の多い戦ではあるが、この勝利により浅井家は北近江の支配権を獲得するのである。
宇曽川堤から肥田城址を望む