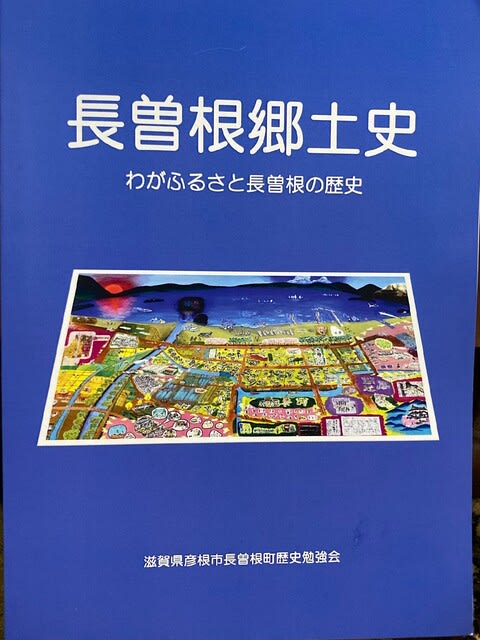鎌倉幕府二代執権北条義時ほど家族によって人生が変わった権力者も珍しい。一番大きな変化は姉・政子が源頼朝に嫁いだことであるが、その他にも父・時政の政治判断による他氏との戦い、継母・牧の方の野心を逆手に取って北条氏の家督を奪うことにもなる。何よりも注意しなければならない出来事の一つが兄・宗時が石橋山の戦いののちに討死したことである。
宗時が鎌倉幕府開幕まで生存していたならば義時の名前が歴史に刻まれる可能性は少なく、場合によっては平家との戦いで前線に立つ武将の一人として歴史の役目を終えていたかもしれない。
そんな宗時の死は突然訪れる。平家打倒を掲げた源頼朝が治承四年(一一八〇)八月十七日に挙兵、その夜の内に山木兼隆を討ち勝利を飾るが同月二十四日には石橋山で大敗し頼朝軍は散り散りになってしまう。宗時は北条領に戻る途中、早川という地で外祖父伊東祐親の軍勢に囲まれ討たれたのだ。
長々と北条宗時の死について記したが、この話は近江の歴史とは何の関係も無い。注目すべきは宗時と共に早川で亡くなった人物がいることである。『吾妻鏡』には宗時の死に続いて「茂光者。依歩行不進退自殺云々」と記され、茂光という人物が、歩行が難しくなったために自殺したと伝えている。また早川の近くに北条時政が建立する宗時の墓隣には茂光の墓も並んでいる。
そんな茂光とは何者なのか? 歴史的には「工藤茂光」と記されることが多い人物で、伊東祐親の叔父になる。北条近くの狩野を領していたことから「狩野茂光」とも記され子孫は狩野姓を名乗っている。頼朝は茂光の協力が確定したことから挙兵を断行したとの説もあり、工藤氏は伊東氏に並ぶ伊豆の有力者と考えられる、実際に北条と江間(北条義時の若い頃の知行地)の間には狩野川が流れていて、狩野を領する工藤氏が河川運搬を支配していたとするならば相当な利益を生んでいたはずである。
その茂光の子・狩野宗茂より「狩野介」を称して子孫は伊豆で在庁官人(現地官僚)だったが、戦国時代に北条早雲と戦って敗れ、後北条氏に仕えることとなる。茂光の子孫とされている狩野泰光(一庵)の子が狩野主膳と言われていて主膳は豊臣秀吉の小田原征伐で八王子城に籠って討死する、この時二歳だった主膳の息子(のちの右京)は母と共に八王子城を出て母方の伯母に保護され養育される。主膳の妻の父親は新野左馬助(井伊直虎の母方の伯父)であり、右京を保護した伯母の夫は木俣守勝。
守勝には実子が誕生しなかったため、やがて右京が木俣家を継ぎ木俣守安と名乗り、井伊直孝に認められ木俣家を彦根藩筆頭家老の家格へと押し上げて行くこととなるのだ。
余談ではあるが、安土桃山時代から江戸時代を代表する狩野探幽ら狩野派の絵師も茂光の子孫である。
北条宗時(右)と工藤光茂(左)の墓(静岡県田方郡函南町)

宗時が鎌倉幕府開幕まで生存していたならば義時の名前が歴史に刻まれる可能性は少なく、場合によっては平家との戦いで前線に立つ武将の一人として歴史の役目を終えていたかもしれない。
そんな宗時の死は突然訪れる。平家打倒を掲げた源頼朝が治承四年(一一八〇)八月十七日に挙兵、その夜の内に山木兼隆を討ち勝利を飾るが同月二十四日には石橋山で大敗し頼朝軍は散り散りになってしまう。宗時は北条領に戻る途中、早川という地で外祖父伊東祐親の軍勢に囲まれ討たれたのだ。
長々と北条宗時の死について記したが、この話は近江の歴史とは何の関係も無い。注目すべきは宗時と共に早川で亡くなった人物がいることである。『吾妻鏡』には宗時の死に続いて「茂光者。依歩行不進退自殺云々」と記され、茂光という人物が、歩行が難しくなったために自殺したと伝えている。また早川の近くに北条時政が建立する宗時の墓隣には茂光の墓も並んでいる。
そんな茂光とは何者なのか? 歴史的には「工藤茂光」と記されることが多い人物で、伊東祐親の叔父になる。北条近くの狩野を領していたことから「狩野茂光」とも記され子孫は狩野姓を名乗っている。頼朝は茂光の協力が確定したことから挙兵を断行したとの説もあり、工藤氏は伊東氏に並ぶ伊豆の有力者と考えられる、実際に北条と江間(北条義時の若い頃の知行地)の間には狩野川が流れていて、狩野を領する工藤氏が河川運搬を支配していたとするならば相当な利益を生んでいたはずである。
その茂光の子・狩野宗茂より「狩野介」を称して子孫は伊豆で在庁官人(現地官僚)だったが、戦国時代に北条早雲と戦って敗れ、後北条氏に仕えることとなる。茂光の子孫とされている狩野泰光(一庵)の子が狩野主膳と言われていて主膳は豊臣秀吉の小田原征伐で八王子城に籠って討死する、この時二歳だった主膳の息子(のちの右京)は母と共に八王子城を出て母方の伯母に保護され養育される。主膳の妻の父親は新野左馬助(井伊直虎の母方の伯父)であり、右京を保護した伯母の夫は木俣守勝。
守勝には実子が誕生しなかったため、やがて右京が木俣家を継ぎ木俣守安と名乗り、井伊直孝に認められ木俣家を彦根藩筆頭家老の家格へと押し上げて行くこととなるのだ。
余談ではあるが、安土桃山時代から江戸時代を代表する狩野探幽ら狩野派の絵師も茂光の子孫である。
北条宗時(右)と工藤光茂(左)の墓(静岡県田方郡函南町)