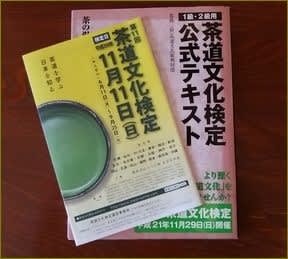昨日はベテラン男性を亭主に、正午の茶事でした。
終わって、「皆さんご苦労様「」と、
亭主側の方達に濃茶を一服点てて差し上げました。
しばらくの間、膝が痛くて正座を避けていましたので、
お茶を点てるのも、久しぶりです。
少し回復したので、「略式でね」と。
思いついて、心構えもなく点てましたので、
満足のいくお茶を点てて差し上げられませんでした。
やはり濃茶は、気持ちの準備から始めないとだめと反省させられました。
後姿を撮られているとは思いませんでした。
後姿にも、年齢は現れるものなのでしょう。
これが私なのねと、しみじみ見ています。
今回のメンバーは、客側に、亭主さんのお友達をお招きして、
その他社中の方2人と私の4名。
亭主側に男性2人と、女性2人の4名です。

ご亭主はベテランですので、
「この年ですから、テーマは道楽とでもしましょう」と。
でも、あまりいい気にならないようにと、
ご自分で用意された床のお軸は「吾唯足知」でした。

濃茶のお茶碗には、清水六兵衛さんの三島写しをお出ししました。
私の好きなお茶碗なのですが、
お招きしたお友達の方にも、喜んでいただけてうれしく思いました。

そして薄茶は、亭主がそのお客様から頂いたという飴釉のお茶碗で。
これもサプライズで楽しんでいただけたと思います。
社中の稽古茶事ですが、このように亭主のご知り合いにご参加いただくのも、
とても新鮮で、また別の緊張感も持てて良いと思いますね。
盃事に選んだお酒は、

今評判で、なかなか手に入りにくいといわれたそうですが、
ネットで見つけられたとか。ワインのような口当たりで、色もこの通り。
終わってから、ちょっとバカラのグラスで頂いてみました。
お懐石も、さすがは料理人さんと、そのもとで修業中の社中の方の心尽くし。
上品で、心のこもったお料理でした。毎回この料理だけは、写真にとるのを忘れます。
頂くことに集中してしまいますので。でもそれでよいのだと思いますね。
お菓子は朝早くから頑張って、作り上げてくれた「きんとん」です。
こだわりのグラデーションだそうです。

イメージしたのは「やましゃくやく」ということです。
ここの所材料の餡をがそろっているので、きんとん三昧でした。、
このきんとんは何とかできるようになったようですので、
別のお菓子も教えて差し上げられるように、
私も修行をしておかなくてはと、挑戦を始めました。
客として、座っている時間が長く、膝を心配しましたが、
お尻の下に枕を入れて、何とかしのぎました。
二日間は、正座無しで、膝を休めます。
皆さんそして私の膝さん、お疲れ様でした。