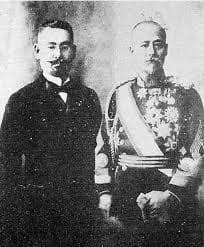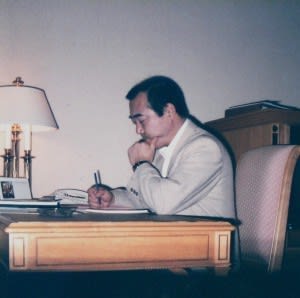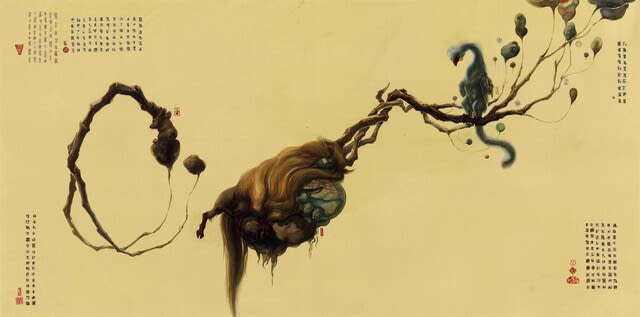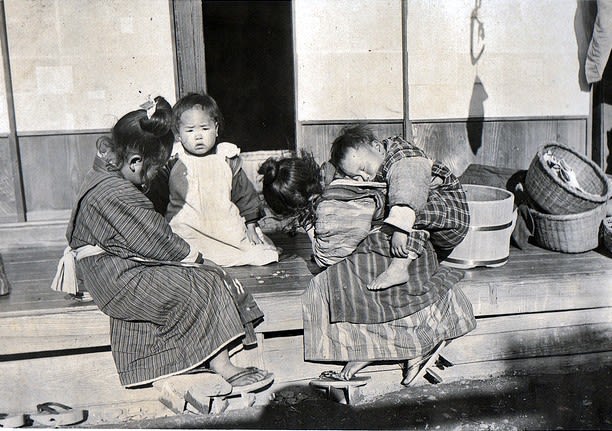「機略」機会に応じた考え。(略には奇略もあれば策略もある)
「逆賭」将来を予測して、いま手を打つこと。
これでベトナムの敗戦は帳消しだ。
政府や軍だけでなく大衆の意識にも認めたくない記憶があった。
ベトナムは冷徹な秀才、マクナマラ国防長官、今度も類似したラムズフェルド氏だ。
共通点は、兵站、戦端、継戦は数値計算でできるが、防戦、撤退、或いは占領軍政となると世界は解らなくなるようだ。アフガン、イラクは今でも混沌としている。

筆者 幹部講話 統御、機略、浸透学、謀略 死生観
指揮司令の機略とは、臨機(機会に臨む)に、いかに各ユニットのコンビネーションを計り、組織を司る人間の職掌を超えた連帯意識と調和を考えることであり、かつ目的を共有した使命感がなくては行動のタイミングを失うことになる。
また多くの識者も大意はそのようなことを仰せになる。なぜならそこには人間が絡む問題が発生し、多くの時間と労力が割かれる憂慮があることに他ならない。
元米国の国防長官ラムズフェルド氏の回想録を読んでいる。
自身の出生から思春期の事情もあるが、考え方はことのほかドライである。筆者の友人である米国人に聞くと「右派」と切って捨てられたが、何処か納得するような気分にさえなるが、似て非なる心情吐露もそこに感ずる内容もある。
それを日本人なりの忖度推考としても、彼の順を追った経歴説明がどこか空虚に映るのは、幼児期に無垢で素直な童心に添うことのない大人の対応からの離脱と、それが他への厳しすぎるくらいの客観的間合いにしみついた習慣的思考の組み立てが見て取れるからだろう。
解りやすくいえば寝技型の柔道と突き放し型のボクシングとでもいおうか、思考、性格にも現れている。音楽でいえば人付き合いの巧くない奏者がセッションによって不規則ハーモニーといえるような楽曲と、楽譜通りに演奏するパートが指揮者のもとに楽曲するバンドのようなものだ。
聴く方も解ったような気する熱気とソロ曲奏、雑音一つ許さないオーケストラは、双方、演奏する者も聴く方も同じようなものが集うのである。
そこの了解事項は、ともに結果に納得性があるが、あらたな機会の創造と目的の自己納得という正当性のロジックを、他のくちばしの届かないところ、それはバーチャルであれ、球体であれば底部しか見えない位置に浮かせる必要性がある。
それは彼の行動説明の方程式のようなもので、全ての組み立てに応用され、その分析理解と論理的考証、そして他への説明は明解ではあるが「明晰」とは異なり、あるいは右派というよりか、中国の混乱期に交渉を委任された説家のような自在応答の巧みさであろう。
それは余程計画だったものでも開戦、終戦、掌握,平定、撤退と普通なら数年かかる軍事オペレーションから現地の臨時軍政、施政委譲など、選択変化が多い状況に合った政策が事前に策定できるものか疑わしいし、その変化をネガティブな論争を想定し、かつ耐えるような継続的大義なりが必要になる。
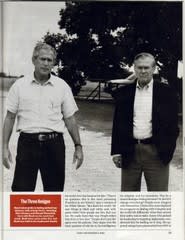
「大統領の戦争」とは・・・
何よりも大統領の発意を政策として練り上げることは、そもそも大統領の戦争というエピソードを記しつつ、逡巡する高官の意見を調整するという従順な臣下と、一方の権力への緻密な客観的観察に長けた臣下という姿を自己調整しなければならない。
いろいろなエピソードが綴られるが、それを超えて向かわなくてはならない使命があった。いやそう見える。なぜなら、機会に望んだときに現れる有能な人間の多面的な考察にある両にらみの気質ではあるが、ラムズフェルドの能力と大統領と良き相談相手のチェイニーの登場は、その段階から意図されていたともおもえるような絶妙なセッションパートであったようにも見えるのは、職掌や権域を超えて符丁が合ったからでもあろう。
つまり、失敗しても氏の責任として問わない事前了解のようなものだ。
それは、勝つのは解っている。どう勝つか、どのように整理するか、ということが目的に合った戦争だったように、そこからみえるのだ。
とくに強大な軍事力が背景にあるからこそ可能な説得論理でもあり、近ごろの日本の若者にもあるような分類、考証し、自身に組み込まれている思考の手順、結論の導き方に合わせ、その範囲とは異なる方策に討論を挑む、ある意味の小心で排他的な自己確認の様子が回想経過にもみえる。
それは納得せざるを得ないような高邁な理屈を並べ、珍奇な学説さえ編み出せるような環境作りのために、別の意志で戦争ロジックを作り、それらしく発表することだ。批判、反論が出やすいロジックだ。
本意は前に記した、くちばしの入ることのない所か、球体の底辺しか見えない箇所に吊るせばいい。なぜなら食い扶持としての足場がないところ以外には立たないことを知っているからだ。
突き詰められたときの国家への帰属意識や、より複雑な要因を以て構成されている合衆国へ無条件の貢献という、より難解な取り組みてはなく、繁栄を毀損すると考えるもの、市場の増殖を抑えるもの、あるいはメンツを汚すものへの復讐など、米国民の潜在する一方の良心との葛藤の様な行動にみえるのだ。
それを整合するための他との事前了解と自己(米国そのもの)の納得は、より難しい論理の整合性を求められるのは当然なことだ。
民主主義の体裁、議会の了解、予算の確保、まさに簡略拙速が求められる後方戦略でもある。
また、その後方における広報戦略のイロハは、広報をゲリラユニットとフォーマルユニットに分け、大統領コメント、あるいはメッセージとして各機会の用となすのだ。彼はその機能を駆使して機略を整え周知している。
ただ、戦後軍政については、それほど時を割かなかったようだ。だが、それが政権の足を引っ張ることまで彼の性格上組み込まれなかったようだ。それは既定勝者の増長ともいえるが、米国民が納得する戦争の意味からすると、より混乱の種となることは必至だからだ。
それはベトナム、ソマリアの泥沼にトラウマが潜んでいることを彼自身十分知っていたことと、機を逃さないとする熱気の高まりがそれを置き去りにしてしまった。
米国は戦争の長期耐力が衰えたとの印象を世界に与えた。長期戦に耐えられない・・・、それは装備にも如実に表れた。
初戦さえ防げば・・・。あのフセインは開戦前に「空爆でやられても、地上戦では勝つ」と言い放った。それはゲリラでもなんでも長引けば米国世論が後ろから槍を向ける、つまり大統領選をはじめとする選挙の攻撃を受けるということだ。それを読まれた上での戦争だ。
国防長官も難儀だが、一番は前線兵士の想定意志だ。まかり間違って「こんなに戦闘が長引くとは・・」「こんなに増員補充が必要だったとは・・」
この部分ではラムズフェルド氏は有能だった。そして完遂した。

かれはビジネスマンとしても優秀だった。それも全米でも優秀な企業として世界にも販路を広げている製薬会社だ。あの高熱死亡の流行り病で騒がれた当時、我が国の国策で購入したタミフルも彼の会社の主要品だ。多くの副作用が問題視され薬害とも噂されたものだ。
組織の組み立て、人員配置、能力の可否判断、販路の開拓、よく整理され、それぞれの部署が機能的に連動し、氏の人脈も加味された総合的な企業として成功している。それは社員の冷徹な観察が人事にも表れ、そのガバナンスは総合戦略の具体的な手法と相まって優れた業績を上げている。もちろんラムズフェルド氏の経歴も大いに効果を上げたようだが、株価、利益率など経営上の数値基準も整ったグローバル企業として成功している。
我が国も民官の交流と称して天下りが横行しているが、米国のそれは前任の関係充て職だけでなく、多くは実質的経営を就任の前提となっている。財務長官がゴールドマンサックスの社長、国防長官が製薬会社の社長など多くの政府高官が民間企業との関係を持つが、再就任する場合は議会の厳格な公聴会をクリア―しなければならない。
余談だが、我が国でも天下りなどと揶揄されないよう官吏の事前審査公聴会を開いたらと思うのも、あるいは人事考査の峻別厳格さなど、米国の手法を憧れと感ずる日本人が多いのも事実だ。
それはアメリカらしい姿として、かつ公私のドライな峻別の姿として人の追及を容易にさせている。我が国のように政界のみならず産業界まで狡猾に支配する官吏の姿からすれば、分かりやすい人材の登用基準である。
彼は国防長官となりアフガン、イラクを指揮したが、すべてのきっかけはブッシュ大統領の一言から始まったと記述している。また冷徹と合理の塊といわれた彼にとって唯一気がかりな子息の薬物依存と浮浪の生活を旧友のチェイ二―や大統領が個人的にも心配してくれたことに涙を流す場面に、大統領が肩を抱える状況は戦争意志の構成に多くの職掌を指揮する他の部下とは違う三人の共通意図がみえる。それは誓いに似た強固な意志を常に確認するエピソードとしても綴られている。

真の正義と勝者の判別は・・・・
「時が熱狂と偏見が過ぎ去った暁には、女神は秤の均衡を保ち、賞罰の置くところを変えるだろう」
インドの司法家 ラダ・ビノード・パル博士
それが9/11を切っ掛けとしたものなのか、あるいは彼らの考える除外すべき異端の敵なのか、それとも純に自由と民主を広げる殉教的に近い考えなのか、はたまた自由な市場をグローバルに広げる意図なのか、その分類された理由ではなく、単に力を持ったものが陥る思考の行き付く極単純な現示的行為であり、宗教的教示の強圧なのか。それは単なるアカデミックな分析では理解の淵にも届かない複雑な問題のようにもみえる。
日本にも「説明責任」がはびこった。行為について解るように説明しなければならないという強圧に近い促しだ。その上、聴いた印象でものごとの可否を民主的に採決して数値の多少で納得する。
たしかに中枢会議では一言も疑義をはさまなかった将官が、マスコミに語りそれがさも反対意見のように書かれ、しかも将官が訂正しない不思議さをラムズフェルド氏は、非難はしないが、不思議さを感じている。
いや、戦術の合理的説明には挿入する言葉もないのだろう。しかも大統領の戦争なのだ。
将官の憂慮は、たとえGPSをつかい誘導爆弾を投下しても、あるいはトルコを除く関係国の領空飛行許可、諸外国の賛同、そして米軍の召集がスムーズに進み部隊運用が計画されても、戦後の駐留にともなう異なる多民族、異宗教、異習慣を深慮しなければ、より多くの要員を派兵しなくてはならず、抜き差しならない状態になると考えていた。
日本の戦後を例にとったものがいたが、そこには毀損されなかった「長」がいた。そのことはマッカーサーも熟知していた。ベトナムはマクナマラが指揮をとったが、数年かかってキッシンジャーの交渉で結末をみた。中国、フランス、日本、そしてアメリカなど歴史上侵攻してきた国にとっての国防の矜持は力を背景にした文明国でも歯が立たないことをホ―チーミンは示し、逃げ帰った米国との交渉に一歩も引きさがらなかった。
その後のアメリカ社会はどうなっただろう。アジアの賢明なる指導者はその勝者の弛緩と糜爛したアメリカ社会の民情を決して鑑とはしない。
もし、ヒット&ウエイの戦術合理的手法によって拙速に戦闘終結しても人々の血は怨念として刻まれる。いくら「オー・マイ・ゴット!」と叫び、神は許すと考えていても戦争は人の血を消耗品として「率」を数値計算する。それは将官(騎士道にある武人)として合理的言辞に馴染むものではなかった。
それは自国の法を世界に普遍化しようとする意図と、異民族にも普遍な情の乖離に逡巡するゼネラルとして当然な精神だったとおもう。
彼はそれを理解しても同情心を抱いてはいけない、あるいは雨のように投下する爆弾の下で逃げ惑う人々の声を聴いてはいけない、それは立場を変えれば吾が身も家族もそのようになる、と納得した。もちろん勝って当然な戦争でも、である。
たとえ一人でも部下を死地に赴かせる愛国指揮官としてその説明責任は問われる。自分さえ解らぬものが説明はできない。いやラムズフェルド氏だけではない、みな真意でなく状況を知りたいだけなのだ。その説明の具は数値の比較有効性と飾り立てた大義が、一番納得し易いことを知っている。
ラムズフェルド氏はそれを部分の問題として考慮の範囲においていた。だが、まずは戦争に勝たなくてはならない。しかし誰が考えても負けるはずはない戦いだ。
それを如何に合理的に説明つくところで決着をつけなくてはならない、その工夫が大統領の意志に沿うことだった。イラクの戦後より選挙の動向が一つの要因にもなったようにもうかがえる。
それは、国務長官のパウエル、ライスへの人物観、友人チェイニーとの永年の回顧、ロックフェラ―副大統領への評価など、何をもとに人物をみているのかが遠慮がちな記述でも解るし、それが氏の人との関係の、゛間合い゛として有効なものを選択する基準のようなものだった。
また、なぜそのような評価をするのかは、戦争の大義と勝つための戦術、紛争地の異民族との応答という多面的な要素を整理説明する手順と結果に導かれた現実感の共有化を促す姿、つまり池の小石の波紋ではなく、染料を流し込んで色付けする作業のようにみえるのである。
波紋は障害があれば流れを変えるが、色は薄まりながらも平均化する。だだ、ブルーに染めても染める前の透明化をまつことなく、時々の繕った大義で順次黄色や赤色を流しこんだら民族なり環境の他とは異なることの有効性や、生存するために異質の慣習を持つ民族の種さえ毀損してしまうことになる危惧もある。

勝者の自由・・・?
異様な種や厳しい陋習、稀なる結論の導き方など、白人、西洋、キリスト教、文明国と評され、現在では論理的とも思われている米国の強制威力を持つ軍事責任者の異なるものの理解は、謳いあげる自由と民主と市場拡大が、随い順化され、平準化を有効として、かつ圧倒的な力によって見せられた民族は、言われるがままに、衣を染めつけられるだろう。
地球上には多岐にわたる陋習慣が存在する。それは近代国家の選別カテゴリーとして独裁、社会主義、民主主義と選り分けられるが、宗教分類ではイスラム、キリストという一神教の軋轢が国家戦争ともなっている。
それは未だ多くの要因を含み、ときに戦争によって新たな闘争を誘引している。武器消費においては市場拡大だが、その戦争経費の出どころは金融と資源、つまり懐と地下から取り出したもの、つまり宗教では禁じられた金貸しの金利と為替、資源の意味のない浪費という、なんら宗教戒律とはかけ離れた戦費調達によって、何らかの宗教的使命感や現示的幸福感のための異なる欲望を満たしている。
゛邪魔ものは殺せ゛とは映画のセリフだと、またそんな恐ろしいことを考えることなく生を営んでいる処世の人々にとって、欲望を理屈に符合させ、整理して説明しても真の納得はない。いや以前はそうだった。
だだ、都会の衆遇の多声や,衆を恃む扇動家を周知宣伝する商業マスコミの騒論は、群れとなった衆を思索と観照から遠ざけ、より高邁な説明論法によって方向を集約している。これも一つのユニットの力でもあり、有効な判断観察の恣意的な姿である。
ラムズフェルド氏に戻るが、現実の諸問題に対応するのは政治家の勤めだが、相手の峻別を一方の価値に包む謀は、自陣営ですら煩いの種として排除し、彼の視点では多くが優柔不断に思えるような強固な意志は、愛国者というよりか、効率的思考のテクノクラートと映る。
ゆえに戦いは勝利しても混乱期の軍政(占領統治)には現地の歴史に浸透した固陋な掟や習慣、そして底流にある面子や金銭などの欲望について理解が深いとは思えない。いや,前記したが深くては戦争などできないのだ。数パーセントの副作用を見込む薬業の世界と同じことのようだ。
あのアフガンで推戴された指導者も権力が安定すれば、主体的に戦闘を協働した米国を始めとした西側といわれた国々の影響力から離れ、逆に歴史的にも対抗する大国の援助に多くの利権を与えるようになっている。それはラムズフェルト氏を含めエリートと称される人々の理解範疇にはない、つまりアカデミックから土着的協調への変化と、現地の転化という将来観とは別なる情緒に対する考察が欠如している故だろう。
学科の数値能力と応用能力と異なることは、我が国の「不」エリートではなく、「似非」エリートのintention(意図)とAction(行動)の乖離と効果なき連動は、既得概念に染まった官吏の慣性劣化で実証済みだが、米国発知的労働者像も数値に対する愚直さとしてみれば、情緒や将来観などは不必要な部類であり、それゆえに繰り返して記す、゛戦後の現地折り合い゛の稚拙さは当然なことと思われる。
意図を行動に結びつけるとき、目の前に大きな溝なり障害が逡巡のもととなるが、それは自身の欲の一種である習得知力の範囲内での行動のこだわりや、切り口の異なる異能者に対する排他的態度など、数値エリートの宿命的欠陥でもあろう。
よく数学者が挑む素数の証明も、物理学者(量子学)とのふとした縁で知った原子の性質との類似性によって、数学の世界では証明できなかったことが、別文野との接触て新たな切り口が発想となり、可能性が進歩した例がある。
処世て言うなら「世間知らずの専門バカ」の様なもので、個々の特徴を調和(譲り合って)させて、連帯する効果の接続要素は、人間社会ては「縁」ということすら解らないようだ。その動きの法則を素数の配置で証明しようとしているのだろうが、大自然の原子ら始まる運動体の複雑な動きは、数学者ならずとも無学な知恵者は直感している。なかには「そうゆうものだ」と心身調和した実利的生活を世代を超えて継続している。
滅びの順は、心身や調和と個々の結びつきがなくなれば分裂し崩壊する。
それは、ソフトパワーによってある程度の効果はあがり、人心や金融は混乱の極におかれるようになったが、今度は戦争というハードパワーによって、より亢進性をたかめる両面策の目的は、単なる動いていればエネルギーは発するといった単純なものではないらしい。
処世の哲人たちは、そのセキュリティまて知っている。それは自身の「ホド」と「キリ」た。説明すれば「欲のコントロール」と「吾身の限界を知る」ことだ。
高級な学び舎に行くと心が放たれ、知恵が飛散する。
だから「勝つために」「効率よく破壊するため」「人間をひとくぐりにまとめるため」などに妙なシステムや組織論を論じ、そして世界観を夢想するのだ。
しかも、的が外れるから混乱するのだ

天地は同様なものを映す 名栗湖
英国は対外諜報機関M16の特務員によるクェートとイラクの直線分断によって利権を確保したが、それはあの混乱期のことだ。こんどは北のクルド人地区をイラク新政府と分断して採掘権契約を結ぶ様な意図は、数百年にわたる彼ら西洋商人との複合国家のたくらみとして現地人は『またか・・』と政策には面従腹背している。
アジアの賢人からしても戦争大義と勝者の態度は決して心の勝者とはいえない姿であり、勝者の資格さえない権力の使い方である。
ラムズフェルド氏が単なる軍事オタクならそれもあろうが、「しょせんはそんなもの・」と思われる米国の大義も意気地がない。やせ我慢ゆえ獲物を目の前でかすめ取られることはヤンキーの意地と精神では我慢ならないだろうが、自分で獲物を抱えて腐らせる愚かものは別として、唱えた大義のために、かつ怨霊の恨みでなく、米国の若い兵士の意志として獲物を分け与えたら兵は死ななくて済むようになる。これは経綸であり大戦略であることを、まず知ることだ。
皆、腰ぬけと嘲られながら戸惑うのはその将来への逆賭なのだ。つまり将来に起こることを想定して現在取るべき布石を打つことへの、もう一段高い調整と努力の検証の必要性だ。
だだ、「兵は拙速を旨とする」定石からすれば、機会を逃すことにもなる。その間に隠匿されたり逃避されたり、外交問題が混沌としてキャスティングボードが握れないかもしれないが、負けたら大変というともあるが、勝ったらどうなるか、人心は弛緩しないか、奢らないか、いくら民主と自由を掲げても敗戦国の国民からから怨嗟を受けないか、まずは戦闘者の矜持として戦災地の民生と勝者の自尊と弛みを慎重に考えることへの促しである。
それを以て勝者の資格であり大国の名誉だということを考えることが必要なことだろう。
戦後、米国の勝利は高級軍人の口利き、納入便宜など、正義を謳って勝利した大国にあるまじき弛緩が起こっている。くわえその弛みは戦闘の大義であった大量破壊兵器はなかったという情報がイギリスから洩れた。増長した為政者に対しては自国の自制として漏れたものだが、はかりごとが弛む風潮はウィキリ―クスの出現によってより広がった。
そして戦勝国のアメリカは信用を失くし、「力」を敬する諸外国から侮られるようになってきた。
それさえも指をくわえていなければならない東北アジアの同盟国として忸怩たるおもいがある。あの阿諛迎合的にみえた被占領国民であった日本人の姿は普遍ではない。米国の力が弱まっても先の戦争を「アジア侵略!」「謝罪と賠償」などとは吠えない。カリフォルニアの日系人強制隔離があっても、忘れかけたころ米国大統領が過ちを認めれば、それでこそ米国大統領だと賛辞を呈し、しつこく賠償金を訴えない。
だからこそ米国の変質が気にかかるのだ。戦後処理、つまりその態度に敗者は戦争の意志をみる。憎らしければ虐殺、虐政を救いたければ徹底的扶助、だだ風の吹きまわしで起こる戦争は意志がゆるみメンツのみで泥沼になる。
米国は色々な経験をした。だだ、大国の「欲」にもみえる、経済市場の確保と支配の意図が見えすぎると、折角の戦略も兵士の血も台無しになってしまう。
その米国の世界戦略にほころびが出てきた。我が国同様とは思えないが縦割り機関である国務省と国防総省、つまり戦闘と外交、戦後処理の意志の乖離だ。それも表に出ない暗闘だ。
それは多岐にわたる陋習と導かれた為政は整理分別し集約転化したとしても、積み残されたファクターを敢えて無理解におくエリートの整理切り捨て意識は、ライス、パウエルといった有色種に祖をもつ情緒には届かなかった。
また、そう考えると論理が構成できず、また「情」という彼らの考えるいい加減で無価値な事情をファクターにしたら、効率的殺戮ができないと真面目に考えるのである。つまり戦争のコストの問題なのだ。
息のかかるような白兵戦など効率的ではない、なによりも自軍の兵士の命、いや効率の問題であり、時を逸すると愚かな市民が世論という手で邪魔をする。それが朝鮮とベトナムで学んだことだ。「兵を動かすには拙速をむねとする」、司令官としては有能だが、縁あって戦闘を共有した敵味方の兵士に鎮魂をささげ、敗者に哀悼を捧げる心が乏しいのもその考えからなのだろうか。
たしかに大統領はともかく国防責任者の作業認識は、今の理屈では妥当だろう。しかし大国アメリカの愛国者はゼネラリストであり、武力の行使は政策としても、司令としても世界から「正義と公平」の認知を受けなければならない。それは誰も正面切って戦いを挑まれることのない米国だからこそ表すことのできる忠恕の心であるべきだ
あなた方は教える。弱者の正義はないと。中国も善悪問わず「力」は正義だと故事は記す。

だから負けた国は「いまにみていろ」と。米国もそのような勝ち振る舞いをする。
たとえ好奇心と阿諛迎合の軟弱精神と集団狂乱の癖があるとの事前調査結果の功があったのか、日本の戦後は誠に従順だった。
今頃になってマッカーサーのせいにしているが前線の兵士以外の軍官吏や官吏は従順だった。おかげで仮にも居心地いい社会になったが、おんな子供は烈しくなり、公職者は食い扶持に堕している。
それも占領軍政策のせいにしたがる人もいるが、かといってケネディーやレーガンに憧れ、あんな政治家が日本にも欲しいとの声も聴く。アメリカに負けてよかったと思えるのも現下の幸せ感が、いまは最上なのだろう。不可思議な国だ。
これでは武力集団も戸惑いつつ、「ます゛、実戦はない」と、囲われることに問題意識もなくなる。
居酒屋の人生論でさえ「男が一人前になるのは闘いと貧乏だ・・」といわれてもピンとこない日本男子だが、世俗では大病、疑獄、倒産の三拍子が揃うと一人前だという。
政治家は人をだまして雄弁家。軍隊は物を壊し人を殺して英雄。むかしはその様にして男子を鼓舞して育て上げた。
有能な国防長官のおかげで、また一時の安逸が味わえる一方の陣営だが、やはりコストはかかる。
疫病の蔓延を恐れて我が国は膨大なタミフルの常備在庫がある。有効も期限がある。感謝のしるしとしては些少だが合理的説明がつく、それぐらいのことしかできない国になってしまった。
【イメージ写真は関係サイトより転載】



















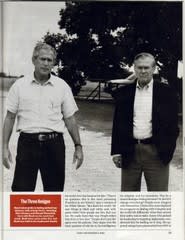





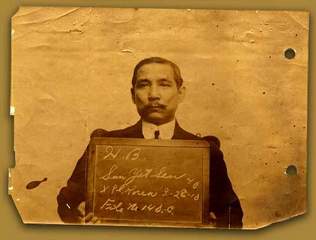



 青森県黒井市
青森県黒井市



















 編集長
編集長




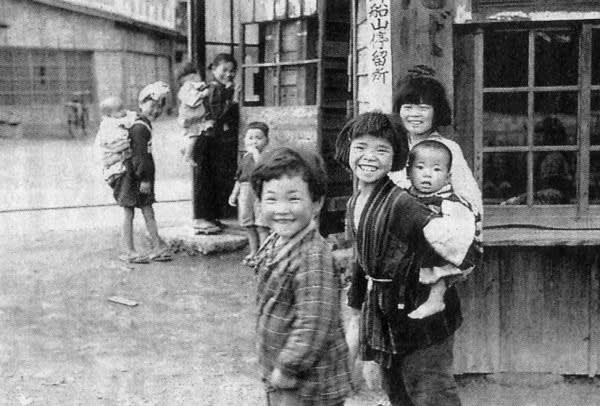
 新聞を授業に バングラデシュ
新聞を授業に バングラデシュ

 真剣な教室 北京
真剣な教室 北京