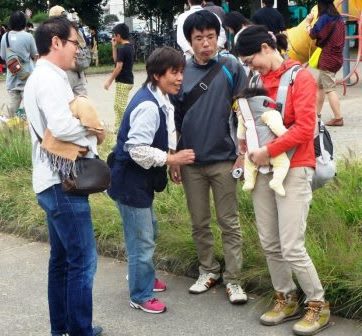月刊わらじの最新号を読む。
表紙は11月23日の見沼田んぼ福祉農園の収穫祭。
20年近く続いている総合県交渉.
現在は埼玉障害者市民ネットワークが窓口。
当時は、国際障害者年サイタマ5年目のつどいが窓口)で、
「街の中の村づくり」として福祉農園構想が出されていたことが紹介される。
とともに、埼玉の都市化の中で逆説的に障害者が生まれていく過程を描く。
「村のありかたが、障害を形作る」。
であれば、障害のある人たちだけでなく、
学生、若者、浦和北ロータリークラブの社長さんたち、
彼らが支援する留学生や若者たち、そして飯舘村の安齋さん、
高知の島岡さんなど、様々は風が吹いていく。
表紙の文章は、「その風が障害を、地域を、国境を越えて、
土のにおいを通わす」で結ばれる。

「克己絵日記」384号「赤子を抱く」にはうちの邑さんが初登場。
ちなみに母親もかつて登場したことあるので、僕以外全員登場。
また、ボランティア学...会会長の栗原彬さんも文章を寄せている。
ちなみに赤子を抱くを読んだ、孫にまごまごじいちゃんは、
「うちの孫描いているのに、絵が手抜きだなと」つぶやいた。
うーむ。このような感覚こそが、埼玉の障害者運動だよな。byコッペ
















































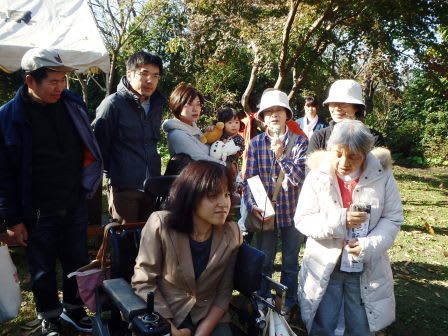



























 の振り分けに抗い、
の振り分けに抗い、