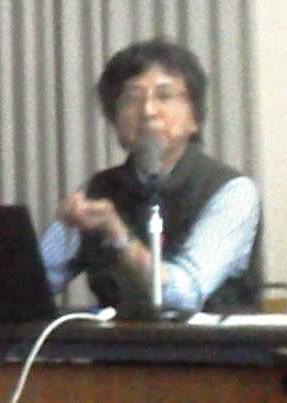共に生きる福祉講座「ひとびとの精神史の水系から―どこへ行く『埼玉流』(自立生活と共生)」と題し、
栗原彬さん(立教大学名誉教授)にお話をしていただき、語り合う機会を得られた。
会場の岩槻駅東口コミュニティセンター5階で栗原さんと事前に落ち合う前に、
窓から北を眺めると日光連山と赤城山の間に尾瀬の山々と武尊が、
また赤城山と榛名山の間に谷川連峰がくっきり白く見えた。
雪のある季節だからこそ、思い出と共に浮かび上がる遠山。
到着した栗原さんにそれを告げると、
赤城山の麓に学校で疎開したことやそこから歩いて赤城山に登ったと語る。
最近は足利に原発震災で野良になった犬や猫さらにはダチョウまで世話をしている友人がいるので、
時々通っているのだという。
昼食をともにしながら、私も大会に2回だけ参加させてもらった日本ボランティア学会の話を聞く。
そもそもの前史として80年代に、
JYVAなどのボランティア活動と草の根の市民運動との交流、つきあわせがあった。
また90年代に入りNPOをめぐる動きが煮詰まり、
阪神大震災を経て1998年にNPO法人が法制化(市民活動促進法)される過程で、
こちらは法人・団体だけでなく個人も(orを)つなげるということで、90年代末に設立したという。
わらじの会では90年からJYVAの1年間ボランティアを毎年受け入れ、
JYVAが2009年夏に解散した後、
派遣先の諸団体有志が連携してV365活動を続けたという話を栗原さんに伝えた。
それらの派遣先は日本ボランティア学会の顔ぶれと部分的に重なる。
同学会は2015年9月をもって活動を終了した。
要因は若い人の継続的参加が難しいことや事務局運営の経済的、組織的基盤が弱い等。
学会としてはひとまず終了だが、
以前から学会内有志による実行委員会形式でやってきたフラットな語り合いの場「カフェ連」を
関東・関西それぞれを中心に続けるということらしい。私たちとはほんとに稀少な遭遇だったが、
このような軌道をめぐる彗星群が数えきれないほどあるのだろうなと思いつつ聴いた。


さて、本番のお話だが、栗原さんが用意してくれた手書きのレジュメには、
「ひとびとの精神史の水系から私が学んだこと」とあった。そのレジュメの各章のタイトルは以下。
(0)学ぶこと、学びほぐすこと
(1)杉本栄子さんから学ぶことー地域、公共性、自己
(2)橋本克己さんから学ぶことー自己と地域の編み直し
(3)緒方さんから「共にいっしょに」を学ぶー共生ということ
(4)緒方正実さん、川本輝夫さn、
埼玉障害者市民ネットワーク2016年度総合県交渉「要望書」から学ぶことー生きづらさ、難民性がひらく可能性
(5)新坂光子さん、幸子さんから学ぶー不在の他者による自己と世界の構成
栗原さんは、
頭、はてなマークについて語った。
ある人のことばや身ぶりの意味が分からなくて絶句してしまう体験がしばしばある。
そこから学ばされたことについて。
水俣病の患者として生きてきた杉本栄子さんは、栗原さんによれば霊的な感性が豊かな人。
彼女が山形県高畠町の近代的な市民ホール前の広場に立った時、
「この下は何ですか」と訊いた。栗原さんは質問の意味がわからず言葉が出ない。
その時小林たかひろさんが、「田んぼです。美田でした。」と答えた。
杉本さんはうなずいた。
水俣では有機水銀を濃縮した生き物たちの亡骸であるヘドロを封じ込める埋め立て工事が行われ、
その上にエコパーク水俣というきれいな公園ができている。
かっての豊かな海もその汚染も、そこで生き死んでいった人々の暮らしや闘いも、
すべてがコンクリートに隠されている。
その現状の地域の下にあるバナキュラーな地域、「原地域」を、
杉本さんは問うたのだと感じ取る。そしてその時、
高畠の広場と水俣の埋め立て地という離れた地域同士が、互いに響き合う音を聴く。
地下の記憶を共有することを通じ、
地上に建設された公共圏とは異なる「もうひとつの公共圏」が形成されたと考える。
ここでは栗原さんのお話の冒頭部分を紹介するにとどめる。
先に章構成を示したように、「橋本克己さん」、
「埼玉障害者市民ネットワーク 2016年度総合県交渉『要望書』」
「新坂光子さん、幸子さん」というように埼玉の人々からの学びが語られた。
その中で故新坂姉妹については、「不在の他者による自己と世界の構成」として表現される。
「みずれえから外に出るな」という世間の目と、私が書いた「農家の奥の部屋に紡ぐ文化」、
栗原さんがイリッチにから教わったと述べた言葉を用いれば「バナキュラー」な文化とのせめぎあいとを、
「くりかえし引照するわらじの会の原点」と位置付けている。
栗原さんによれば、
亡くなった姉妹が同時代やさらに前の時代を生きた人々と周りの自然をひっくるめて、
この現在を根っこからいつも再構成し続けているのだと。
栗原さんのレジュメは、
「第2次大戦・日中戦争のアジア・日本・欧米の不在の受難者が構成する憲法9条。
不在の友を裏切れない。」でしめくくられていた。
後半の質疑応答、意見交換の時間に、
とつぜん栗原さんから「飯舘村に行かれた山下さんはいかがでしたか」と振られた。
私は別のことを考えていたので、まずそれについて述べ、後から飯舘村のことにふれた。
先々週の土曜に大阪に住む40年ごしの友人が、初めてわらじの会の現場に来た。
といっても、恩間新田を案内し、新坂姉妹やきみ子さんのことを伝え、
彼女らの生家や親たちが亡くなる直前に建てたオエヴィスやべしみを案内しただけ。
活動がない日なので、オエヴィスで住人のKくんと言葉を交わしたのみ。
彼は「ほっとした」と笑みを浮かべて帰った。
彼は大正区という運河に面した沖縄出身者が多い街で生まれ育ち、
現在も認知症の姉とそこで暮らしている。
中学を出てすぐ工場で働き、やがて70年安保闘争や日雇い労働者の運動に参加し、
何度も逮捕され服役もしてきた。
不況の下、寄せ場の変化が進み、野宿労働者が増えテント村が拡大し、
それに対して代執行が強行されテントが撤去され、
一方では貧困ビジネスがはびこり、
行方不明や殺人が疑われる事件も起きている修羅場のただなかに身を置いてきた。
釜ヶ崎界隈では長老格の一人だが、
わらじの会とも交流があるココルームの活動や全国協同集会で
ご一緒したNPO法人釜ヶ崎支援機構のような事業展開とは距離を置き、
野宿者一人一人とのつきあいを基本にしつつ、頑固一徹を貫いているらしい。
一時は大阪各地にあった野宿者村は、
いまや彼が「労働相談所」(テント)を置いている公園だけになっているという。
そんな中で彼が「ほっとした」と言って帰ったのは、
やはり大阪と越谷の「原地域」の通底を感じ、
「不在の他者による自己と世界の構成」を再確認したのではないか。
飯舘村を案内してくれた安齋さんも彼も頑固者だ。妥協をよしとしない。
互いに連携し、組織力をもって地域とつながり、
行政と交渉し支援施策を作らせてゆくといった活動とは相いれないところが多々あるだろう。
それらの活動からは阻害者とみなされることもあり、
時には自分自身、孤立感や奈落の底に落ちてゆく気持ちにもつながるだろう。
橋本画伯や新坂姉妹、きみ子さんを考えれば、
その孤立の極と思われる生き方の底の底に栗原さんのいう「存在の深み」が現れつつあった。
幾世代にわたる不在の他者と草木、水、石ころも含めた異なる他者によって現在のこの地域があることが見えてきた。
頑固で妥協をよしとしないということもまた、異なる他者が共に生きる上での欠かせない要素なのだ。
ひとつの太い根ではなく、細かいひげ根を無数に、しかし確実に張ってゆくことが、
やがて「ガバッとひっくり返す」(栗原さんの表現)準備作業になるだろう。
長くなったので、以下は稿を改めて報告しよう。by山下浩志











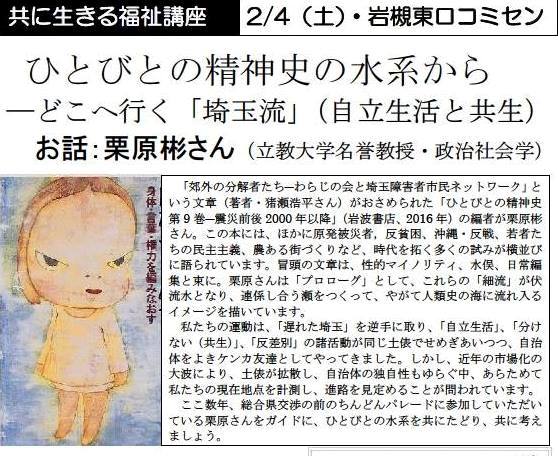








 ]
]




















 0000
0000