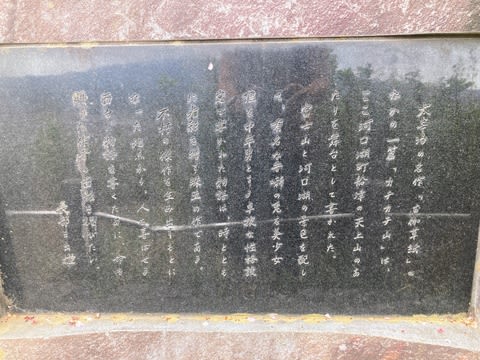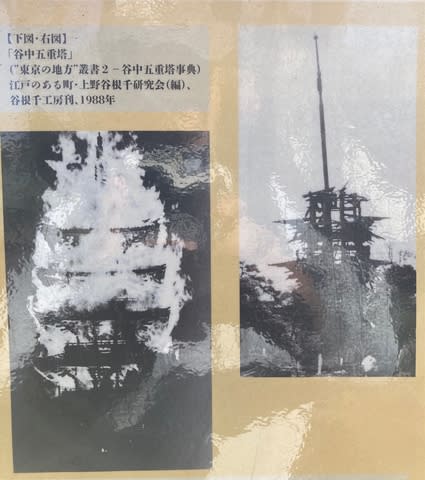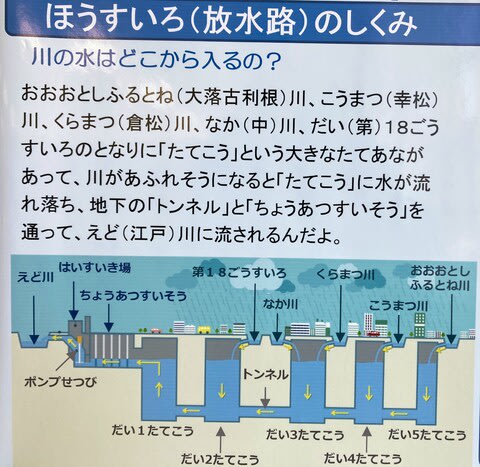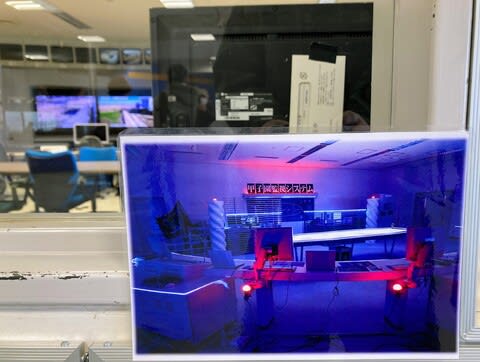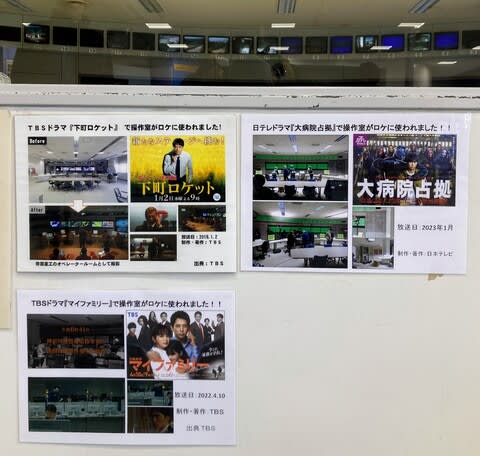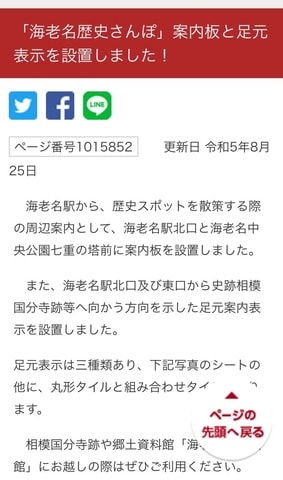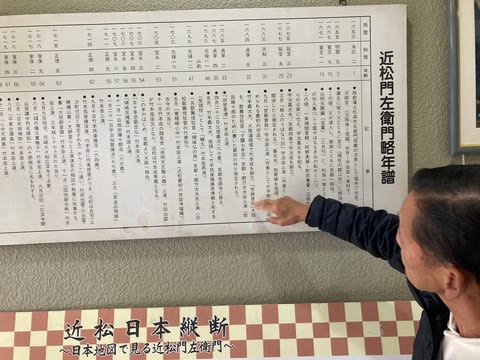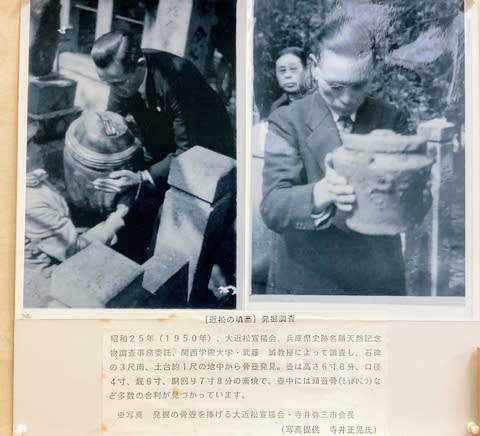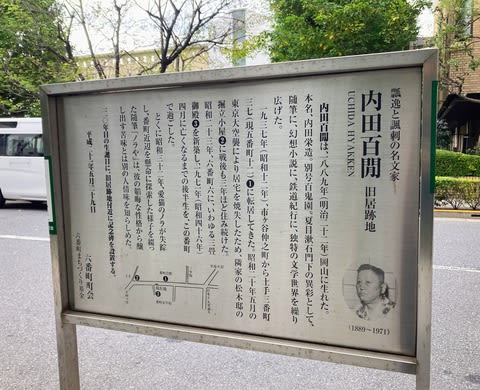大雪山から下りてきて、旭川で日数が余った。そこで駅の観光案内所に寄ったら窓口のボランティアさんが話しかけてきたので、「バスツアーの案内はしていますか?」と尋ねてみた。「市内観光バスはありませんが、富良野や美瑛に行くツアーならあります」というので、概略を聞いた。JR富良野駅、美瑛駅、旭川駅からそれぞれツアーが出ている。空きがあればスマホで前日まで予約できる。

コロナ以前なら定期観光バスの現地ツアーがあった地方も、コロナでツアーが廃止になってタクシー観光しかないところが増えた。バスツアーなら半日3,000円〜5,000円程度、1日コースでも1万円しないのが普通だったが、タクシー観光ツアーとなると3万円は覚悟すべきだろう。円の価値が暴落してるから外国人の利用はあるかもしれない。いまも多いのは定期観光バスじゃなく、大都市の発着で地元に金が落ちない企画観光バスツアーで、現地出発・現地解散できない。

そこいくと富良野・美瑛・旭川にはいまでも、現地出発・現地解散の定期観光バスが毎日のように運行している。たまには乗ってみるか。スマホでサイトにアクセスして必要事項を入力し、翌日の「あさひかわ号」を予約した。朝10時40分にJR旭川駅前で集合し、夕方17時40分ごろ旭川駅に到着する観光周遊バス「パッチワークコース」で、空港やホテルを経由する集合・解散タイミングもある。大人8,000円。

北海道といえば阿寒湖のマリモ、霧の摩周湖、屈斜路湖、知床、宗谷、洞爺湖、といったところが人気だったのに、このところ富良野・美瑛がいちばん人気なので定期観光バスが運行しているという。そういえば大雪山の旭岳、黒岳にアクセスする手段は路線バス(旭岳は1日3便、黒岳は1日7便)だった。しかも空いていた。

ベテランのバスガイドさんが北海道観光の今昔をマイク使ってしゃべる。何日か山の中にいて人とあまり話してないし、新しいことより古いことに興味を覚えるタチなので道中しっかりガイドさんの昔話に耳を傾ける。今の話も傾聴する。インバウンドの旅行客(たぶん中国大陸の人たち)も乗ってるが、トークは日本語オンリー。

旭川は盆地なので夏に気温が上がり、米づくりに適しているそうだ。しかし昭和50年ごろから政府が減反を指示して小麦や大麦を農家に作らせ、半世紀たって今度は米を作れと急に言い出した。ハイそうですかと畑を田んぼに戻しても、ろくな米などできはしないと農家が怒っている。政府が農家に罰金を課すとか言い出したのはそれも理由の一つか?

美瑛に入ると火砕流によって作られた丘のうねりが畑に覆われて、独特の景観をなしている。作物の種類で畑の色が変わりパッチワークのようだから「あさひかわ号」のツアーは「パッチワークコース」というのだろう。セブンスターやマイルドセブンといった煙草や、スカイラインといった自動車などのCMが昭和のある時期、この地でよく撮影された。

「ケンとメリーの木」は昭和47年(1972年)に日産スカイラインのCMに登場して、農道に立つ樹木がにわかに人気スポットと化した。それから半世紀以上になるわけで当時より「ケンとメリーの木」もずいぶん立派になったそうだが、CMをみたことがないので何のことやら全然わからない。「セブンスターの木」や「マイルドセブンの丘」を車窓から示されても感慨わかない。中国人はもっとだろう。

北西の丘展望公園というところ(美瑛の丘の畑が見渡せる)で、北あかりのコロッケを買い食い。ちょうどお昼どきでお腹が空いていたこともあり、美瑛はジャガイモの産地ということもあり、おいしかった。カルビーのポテトチップスになるジャガイモの拠点が美瑛にあり、コンテナを積み上げた施設を車窓から眺めた。そこらじゅうの畑に紫や白のジャガイモの花が咲いていた。

バスが農道や林道をゆくとき、まっすぐな道路がつづいてガイドさんが北海道の道の特徴として解説してくれた。原野の地図に定規で引いた通りに道をつくるから、このようにまっすぐなのだそうだ。西南戦争などで負けた不平士族が屯田兵にされて過酷な工事を課されたのだろうか? 道東の場合そうらしいから、道央もそうかも。直線ながらアップダウンが激しい。

富良野のファーム富田でラベンダー畑をみた。ジャガイモやカボチャやコーンばかり育てても金にならないので、富良野の農家は香水の原料になるラベンダーを換金作物として手がけた。しかし思ったほど金にならなかった。ラベンダーづくりから手を引く農家ばかりになり、富田さんが最後の一軒として残った。毎年やめようと思いながら続けているうちに、ドラマ「北の国から」で富良野が注目され、ラベンダー畑にも観光客が押し寄せた。それから40年。富良野は北海道いち人気のスポットだ。

ラベンダーのにおいを嗅ぐと思い出すのは「時をかける少女」の大林宣彦監督と、村西とおる監督。それから作家の筒井康隆のこと。順序がおかしいような気もするが、必ずこの通りに想起される。ラベンダーのにおいを嗅ぎながらラベンダー農場の観光カフェで「越冬じゃがいもメークイン・男爵のカレー」と「ラベンダーコーヒー」の昼食をとる。ツアーに食事は含まれていない。北海道のジャガイモうまい。

富良野をあとにして白金温泉のほうへ向かう。温泉に入るのではなく、その近くにある「青い池」を見物しに行く。わりと最近になって見出された池で、アルミニウムと温泉成分がまざることにより、とても青いのだという。今回のバスツアー、この道だけ渋滞していた。他の名所にスイスイ行けたにもかかわらず。それには理由がある。

美瑛町が「青い池」の近くに設けた駐車場に、コスト削減のため受付のおじさんを置かなくなったので、入場口でドライバーによる機械操作が必要になり、駐車場が空いてるにもかかわらず渋滞が生じるのだった。昨年までこんなことはなかった。コスト削減のやり方がまずかった。観光客が迷惑している。早急に改善が必要だ。おじさんを係として常駐させるべき。(事務所に役人がいるようだけどカーテン閉めて混乱を放置していた……!)

「青い池」は異様に青かった。十勝連峰の美瑛岳から流れ出る美瑛川そのものがアルミニウムを含み、温泉成分とまざるのか、まざらないのか流れる水がなかなか青いという。その美瑛川に設置されたブロック堰堤に水がたまって「青い池」ができ、SNSで拡散して人気スポットになった。堰堤の中の樹木は酸性の水にやられて枯れた。おそらく魚は棲めまい。

美瑛川の上流にある「白ひげの滝」がこちら。確かに流れが青い。白金温泉のホテルのそばの白い橋に大勢の観光客が佇んで滝を見下ろしている。ここも日本人より中国人が多い。まともな産業が国内になくなり、インバウンドに寄りかからざるをえない実情があるのだから、招かれてきた外国人をみてオーバーツーリズムなんて揶揄するのはお門違い。そういう陰湿な中傷は客を逃がす元だ。

白金温泉は十勝岳の登山口でもある。標高1,000mのところまで自動車で上がり、そこから2,077mの山頂までは徒歩になる。標高差1,000mはなかなかだな。大雪山系で最も高い旭岳でもロープウェイ駅と山頂の標高差は数百mだった。そう考えると登り降りが大変そうだけど、また機会があったら白金温泉を起点にして十勝岳や美瑛岳に登ってみたいような登ってみたくないような。

最後の立ち寄りスポット、美瑛神社で縁結びを求める人に評判のハート型をひとつ見物。よく探せば境内にハート型がいくつもあり、たくさん見つかると恋愛パワー上昇が叶うらしい。いまさら恋愛パワーが上昇したり、縁が結ばれたりしても困るので、ひとつでやめておく。絵馬を眺めてバスに戻る。

JR旭川駅の裏手の、こんな河川敷の木陰に熊が出没するようになってしまったそうだ。「私が子供だった頃はこんなところに熊が出るなんて考えられないことだった」とガイドさんは嘆く。子供だった頃って何時代だろう? 昭和なのは間違いないとして「ケンとメリーの木」とか懐かしむということは……謎を残したまま、バスは旭川に着いた。
関連記事: 大雪山