改めてブラジル戦総括を論じてみたい。今のコンフェデ大会を来年のブラジルワールドカップにどう活かすかという観点から。僕の結論はこうだ。
今までの方針をまだ換える必要は無いどころか、もっとはっきり打ち出せということだ。具体的には、①ボランチを含めたDFラインが低すぎたからもっと高くせよ。②その上で、前にボールが入った時は球離れ良く攻めろ。「前田の深さと、左右ウイングの幅」というザックの攻撃開始時の布陣は忠実に実行すべし。③ゴール前守備時には、もっとゾーン責任を持ちつつ、自分の相手を離すな。ゴール前では1対1が第一だというのは、ネイマールを押さえた内田の健闘からも分かることだ。ちなみに、長友よりも内田の方が遙かに良いというのもはっきりしたことだった。
さて、こういう結論に至るいろんな観点を書いてみたい。
ブラジル戦の0対3を大きく見過ぎてはいけないと思う。先ず、その根拠をいくつか述べておく。
第一に、その前のヨーロッパ遠征の戦い0対4があるし、二つとも意外な先制点とさらに二得点目も意外な取られ方をしたことだし。2試合とも先制点は、遠目からでも打ってくるブラジルへのゾーンディフェンス的備えが不足しすぎていたと思う。初めの0対4の時の2得点目は、今野のPKだ。この判定は、PKとは言えないという批判の声も大きかった。サッカーでは、「意外な先制点」が生じると、その後にカウンターを喰らって大差になりやすいとは、常識的分析の一つのはずである。
今回も意外な得点が入ったことによって、ブラジルは後半45分を自分からは攻める必要もなくなった、以上のすべてを踏まえたこん回の以下のいろんな数字はまー得点ほどの大差ある物とは言えないと思う。ボールポゼションは37対63は、キープして無理責めするから起こった事とも言える。ブラジルはのらりくらりでよかったのだし。シュート本数は10対14だったか。
さらにもう一つ、目のある人は結構こう語っている。まずご当人のザックは
『このチームの力の50%も出ていず、非常にまずい闘い方しかできなかった。その原因はまだ分からないから、選手達の声も聞いて、これから確かめていく』
現地観戦をした中田英寿の言葉はこうだ。
『負けないゲームをしようとしていた。自分(たち)の特徴を皆がもっと出すべきなのに。点差ほどの実力差など無かった』
さてワールドカップでは、中田の言う「負けないゲームをしていた」のは岡田武史。南ア大会の直前に自分がそれまで目指し続けてきた闘い方を捨てて、防御布陣に切り替えたのだった。その防御布陣のままでベスト8を決めるパラグァイ戦にも臨んでこれを落とし、ベスト8を逃したあのゲームをこう評した評論家達も多かったはずだ。
「決勝トーナメントぐらいは、リスクを冒して自分らの闘いをして欲しかった」
ただ南ア目指した岡田武史は、こう考えただけなのだろうとは、僕は今でも思っている。「選手達に勝たせてあげたかった」。すると、ドイツ大会のジーコはどうなるのか。「自分たちの特徴を出そう」が、ジーコのドイツ大会。ただし、実際のゲームでジーコ戦略に忠実であったのは中田だけで、他全員が腰が引けてびびっていたと言うしかないと、僕は見た。初戦のオーストラリア戦からして特にそうだったと。1対0から最終盤になって3点取られるなんて、正直戦略的戦闘性、つまり冷静さが足らなかったとしか、僕には思えない。そして、最後のブラジル戦ではまた、中田だけが「自分たちを出そう」と闘っていたと思う。
そこで以上のまとめとしての問題。勝つということだけのための現実的闘いだけをして自分ら最高のやり方をどこにも遺さなくとも良いのか、目指した闘いを戦闘的に貫いて、その時点では敗れても良しとするのか。僕は、絶対に最後は後者を貫いて欲しいのだ。いくら格上の相手であっても。そういう闘いをしなければ、マイナス思考からびびりやすい日本人の闘い方から、日本サッカー界がなかなか抜け出られないと見ている。
こういう二つの闘い方の岐路について、日本の評論家達もずい分無責任な言葉を平気で語ってきたと思う。現実的に闘えば、ロマンが欲しかったと言ったその人が、次にロマンを持って闘えば現実的に闘って欲しかったなどという。そんな無責任な評論ばかりが横行していると読んできた。
僕はブラジル大会に向かって、ロマンを持って闘って欲しい。どこか大事な所では、そういうスポーツ人らしい心を発揮して欲しい。スポーツは、勝ち負けだけがすべてではない。手っ取り早くそう考えるだけのような連中が、最近いろいろ問題になっている日本の上意下達の不条理なスポーツ界を作ってきたのだとも思いつづけてきた。
今までの方針をまだ換える必要は無いどころか、もっとはっきり打ち出せということだ。具体的には、①ボランチを含めたDFラインが低すぎたからもっと高くせよ。②その上で、前にボールが入った時は球離れ良く攻めろ。「前田の深さと、左右ウイングの幅」というザックの攻撃開始時の布陣は忠実に実行すべし。③ゴール前守備時には、もっとゾーン責任を持ちつつ、自分の相手を離すな。ゴール前では1対1が第一だというのは、ネイマールを押さえた内田の健闘からも分かることだ。ちなみに、長友よりも内田の方が遙かに良いというのもはっきりしたことだった。
さて、こういう結論に至るいろんな観点を書いてみたい。
ブラジル戦の0対3を大きく見過ぎてはいけないと思う。先ず、その根拠をいくつか述べておく。
第一に、その前のヨーロッパ遠征の戦い0対4があるし、二つとも意外な先制点とさらに二得点目も意外な取られ方をしたことだし。2試合とも先制点は、遠目からでも打ってくるブラジルへのゾーンディフェンス的備えが不足しすぎていたと思う。初めの0対4の時の2得点目は、今野のPKだ。この判定は、PKとは言えないという批判の声も大きかった。サッカーでは、「意外な先制点」が生じると、その後にカウンターを喰らって大差になりやすいとは、常識的分析の一つのはずである。
今回も意外な得点が入ったことによって、ブラジルは後半45分を自分からは攻める必要もなくなった、以上のすべてを踏まえたこん回の以下のいろんな数字はまー得点ほどの大差ある物とは言えないと思う。ボールポゼションは37対63は、キープして無理責めするから起こった事とも言える。ブラジルはのらりくらりでよかったのだし。シュート本数は10対14だったか。
さらにもう一つ、目のある人は結構こう語っている。まずご当人のザックは
『このチームの力の50%も出ていず、非常にまずい闘い方しかできなかった。その原因はまだ分からないから、選手達の声も聞いて、これから確かめていく』
現地観戦をした中田英寿の言葉はこうだ。
『負けないゲームをしようとしていた。自分(たち)の特徴を皆がもっと出すべきなのに。点差ほどの実力差など無かった』
さてワールドカップでは、中田の言う「負けないゲームをしていた」のは岡田武史。南ア大会の直前に自分がそれまで目指し続けてきた闘い方を捨てて、防御布陣に切り替えたのだった。その防御布陣のままでベスト8を決めるパラグァイ戦にも臨んでこれを落とし、ベスト8を逃したあのゲームをこう評した評論家達も多かったはずだ。
「決勝トーナメントぐらいは、リスクを冒して自分らの闘いをして欲しかった」
ただ南ア目指した岡田武史は、こう考えただけなのだろうとは、僕は今でも思っている。「選手達に勝たせてあげたかった」。すると、ドイツ大会のジーコはどうなるのか。「自分たちの特徴を出そう」が、ジーコのドイツ大会。ただし、実際のゲームでジーコ戦略に忠実であったのは中田だけで、他全員が腰が引けてびびっていたと言うしかないと、僕は見た。初戦のオーストラリア戦からして特にそうだったと。1対0から最終盤になって3点取られるなんて、正直戦略的戦闘性、つまり冷静さが足らなかったとしか、僕には思えない。そして、最後のブラジル戦ではまた、中田だけが「自分たちを出そう」と闘っていたと思う。
そこで以上のまとめとしての問題。勝つということだけのための現実的闘いだけをして自分ら最高のやり方をどこにも遺さなくとも良いのか、目指した闘いを戦闘的に貫いて、その時点では敗れても良しとするのか。僕は、絶対に最後は後者を貫いて欲しいのだ。いくら格上の相手であっても。そういう闘いをしなければ、マイナス思考からびびりやすい日本人の闘い方から、日本サッカー界がなかなか抜け出られないと見ている。
こういう二つの闘い方の岐路について、日本の評論家達もずい分無責任な言葉を平気で語ってきたと思う。現実的に闘えば、ロマンが欲しかったと言ったその人が、次にロマンを持って闘えば現実的に闘って欲しかったなどという。そんな無責任な評論ばかりが横行していると読んできた。
僕はブラジル大会に向かって、ロマンを持って闘って欲しい。どこか大事な所では、そういうスポーツ人らしい心を発揮して欲しい。スポーツは、勝ち負けだけがすべてではない。手っ取り早くそう考えるだけのような連中が、最近いろいろ問題になっている日本の上意下達の不条理なスポーツ界を作ってきたのだとも思いつづけてきた。










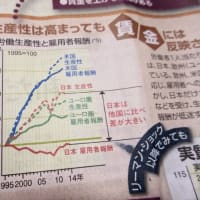
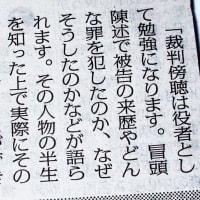





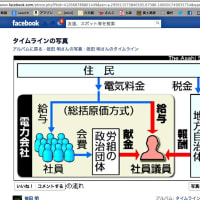
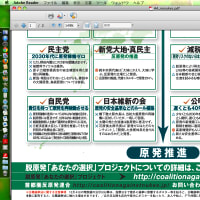




もう1人の識者、オシムがこう分析しているのを読んだ。
日本人のスピードと組織性という長所が全く生きていなかったと。その上で、選手個々をこうな評していた。
『 また、選手個々では、最年長の33歳の遠藤は安定はしていたが、それ以上ではなかった。もっと危険なプレーをするべき。得点を取るためにリスクを冒す必要がある。そのための勇気を持ってほしかった。
岡崎は攻守にわたり頑張っていた。ここ数年最も成長した選手の一人だ。
香川はドルトムントやマンチェスターUでプレーする時のように味方選手を生かし、また味方に生かされるプレーをするべきだ。日本代表でプレースタイルを変える必要はない。スタイルを変えては長所を生かせないだろう。
長谷部はドイツ人がプレーしているようだった。責任感があり、よく走りクレバーでドイツ的なスタイルになった。
長友はインテルに移籍して2シーズンが経過し、もっと成長しているかと期待していたが、少し慎重になり過ぎていた。期待度からすれば、ちょっとがっかりだった。』
こうしてオシムが本当に批判している人物が誰なのかは、賢いファンには分かろうというものだろう。日本のスポーツマスコミはこれと正反対の評論をして、監督命令に従わずまずかった人物の完敗感を伝えるだけに終わっている。無能な批評だと思う。
ザック、中田、オシムの同じ内容の声にこそ、耳を傾けるべきだろう。
しかし、力量に差がある場合の戦い方には定石がある。
先ず、前半のスタート15分迄に攻撃ラッシュを掛ける。様子見はしない。圧倒的な主導権を始めに握る。そしてそこで点を獲る。これが戦いの入り方になる。昨日のブラジルもまさにそんな戦い方をした。その結果生まれた先制点は決して事故でもまぐれでも意外でもなく必然の結果になる。サイドの守備で傍観者になった清武君のミスからの先制点。
そして定石ではその後の時間はボールを保持しながら隙をみて追加点を狙うという事になる。前半45分はこうして終了した。
そして定石の二つ目、後半開始時の攻撃になる。ハーフタイムでは負けているチームは当然攻撃プランの修正を行う。が、そもそも前半45分の殆どを相手がコントロールしている程の差がある。従って、主導権を握っている側は再度後半開始15分に攻撃のギアを入れる。
ブラジルの2点目も清武君の中途半端なポジショニングの穴をつかれた失点になった。
同じ様な時間帯、シチュエーションの得点はまぐれでは生まれない。必然の失点。
そして定石三つ目は、相手に攻めさせながらカウンターでとどめをさす。これもその通りの結果になった。
サッカーでは3点あれば十分であり、3点も絵に描いたように点が入るのは相当な力量差がある事になる。
この差を縮めるのは、人を替える、戦い方を変える、両方替えるの三通りしかなくなる。
ザッケローニの采配にはミスは無かった。替えるべき時に選手を変え、交代選手も間違いでは無かった。そうするとやはり問題は戦い方になる。90分の殆どを相手に主導権を握られる。定石通りに失点を重ねる。これを防ぐ為には失点を重ねない為の準備が必要になってくる。
幸いW杯本大会の予選はリーグ戦である。全て勝つ必要は無い。強豪国に星を落としたとしても最小失点で終われば十分に望みはある。
そんな戦い方だよね。これから考えるのは。
グランドに居た選手は痛い程力量の差を痛感した筈。3点獲られた事も90分の殆ど全てをコントロールされた事も。
1年前としては収穫の多い惨敗だったと思う。
またこの説明では、今回に前回のヨーロッパ遠征対戦時よりも日本が遙かに消極的にスタートしたたことも説明できていないと思います。相手が思いっきり出てくると思うなら、こっちはDFラインを引いて、ただ守っちゃだめでしょう。ザックはそう命じたはずです。そして、それが聞き入れられなかった結果にちょっと呆然としていると、僕はそう見ましたね。
すべてはこれから分かること。時間の経過と何をしてどういう結果になるかを、監督と選手が見せてくれることでしょう。岡田型になるのか、ジーコ型になって成功するのかチームが分裂して終わるのか。選手より内容的に高い望みを持ったザックが、ジーコと同じように強権型監督でない所が大変難しいところですが。その時に答えが出ることです。待ちましょう。
そう言えば、もう1人強権型監督がいた。02年のトルシエです。トルシエのやり方は彼の絵図面の強制押しつけでトラブルが続発していた。そういう意味ではちょっと他3人とまた違うのですがトルコ戦を除いては成果は大きかった。日本人は強権でないとだめなのかなー? それともアジアに有利な組み合わせだった?
そんじょそこらのジャーナリストよりもはるかに的確でひとつひとつ納得です。
そこでいくつか質問させてください。
次のイタリア戦はどのように考えますか。
さらにメキシコ戦は。
他にも貴方に質問したい事がありますが今回はこの2つお願いします。
貴方も僕もいずれにしても二つの闘い方の区別をするとは語っている。強者と闘う場合と、どこが対等に近い相手と見るかは別としてそこと闘う場合と。また、現実的闘いと自分らの通常の闘いを目一杯出す場合ととかの組み合わせもあるとも。
問題は、このブラジル戦をどう総括して、今後のコンフェデをどう闘うかが違ってくると、そういう違いなのだと思う。ここまでの僕の話はそういうことということでよろしく。
僕は最短の場合あと二つの相手のどちらかでは、ブルガリア戦以降曖昧になってきたザックの戦略通りに闘って欲しいということだ。そのためには、それができる選手を入れなければならないかも知れないと、そのタメに監督強権さえ使えと、そう語っているつもりだ。ラインを上げないDFとか、受け手が走っていて受けられるのに球離れが悪くて結局敵に囲まれ、攻撃を遅らせた選手とか、敵陣を縦横に広げない選手とか。そのかわり、強権を使ったらその分監督の結果責任も大きくなって、場合によっては進退も掛かってくるのだろうということも含んでいる積もりだ。オシムやナカタが言うこともそういうことを含んでいるはずだ。
ザックはどうするのだろう。ジーコのように曖昧なままで、コンフェデを過ごしてしまうのか?そこを注視したい。ただこの食い違い発生以来最も煮詰めた討論をした時は、ザックは結局こう語った。「ピッチでやるのは君たちだ」(6月2日拙エントリー参照)。
「コンフェデ・チャレンジ」は実質かけ声だけで、このままずるずると行かなければよいのだが。そんな気もする。選手にはそんなに全体が客観的には見えなくって、それを見るために監督が居るのだ。それを、監督の注意を基本的に受け入れないとすれば、そうなる可能性大で3連敗とか。
「本田の改心」てのも、結局は、そうゆう事でしょう。
本田抜きは、難しいのだから・・
自ら、監督失格を宣言したに等しいのだが
イタリア戦をどう戦うか?
ちょっとわたしの予想と違ったのは、イタリア思いの外真面目モードだなと。もっとバカンスモードだと思った(笑)。
イタリアはピルロとラベッシのチームなんでチームの重心は後ろ。この二人を好きにさせない為にはかなり前がかりに行く必要がある。メキシコも最初はそのつもりで戦ったがひとつ大問題が。
FWの怪獣が絶好調(笑)。これが最大の誤算。てっきりバカンスモードだと思ったんだが。
それによりDFラインは後退を余儀無くされた。仮にイタリアが日本戦も同じメンバーできたら相当にキツいでしょうね。純粋なワントップとしては、怪獣が世界一でしょうね。
当然日本のDFラインも釘付けになる。
ザックの事だから対策は用意するだろうが抑えるのは無理筋。日本と似たようなメキシコがズタボロにされてるので厳しいな。
一方、攻撃は前田orハーフナーを使うんじゃないかな。
そして本田でタメを作りサイドを使ういつもの形。しかし、イタリアのプレスは厳しいからチャンスは少なくなるでしょう。
ザックはコンフェデだけでは無く常に現実的な戦い方を選ぶのでおかしなスタイルは取らない。ブラジル戦もそうだが。
アジア相手に戦っていればどうしたってチーム力は上がらない。南米や欧州の強豪とやった場合いつもの戦い方は出来る訳がない。相手が段違いだから。
だからコンフェデは監督の進退を賭けるような大会でも無ければ勝ち負けに拘る大会でも無い。とりあえず現段階での世界トップクラスとの距離が分かればいい。
それが分かってからの残り1年だから。
清武君の守備のミスを書いたけど、ではJリーグの選手が清武君よりも上という事は間違っても無いので、頑張ってもらうしかない。
イタリア戦もブラジル戦に続いて惨敗するかもしれないがそれはもう相手のレベルに慣れるしかないから。
アジア予選で豪州相手に2回引き分けのチーム力が今の力だから。
この監督この選手達以上のメンバーは居ないんですよ。
という事でメキシコは改めて(笑)。
でもまあ北中米予選で大苦戦中だけあってグダグダだわメキシコ。
だからまあチームとしての慣れが必要ですわ。
FWの怪獣とはバロテッリのことですよね。
確かに強烈ですよね。
長友には頑張って欲しいと思っています。