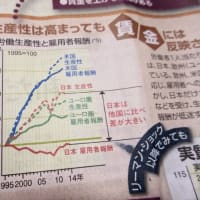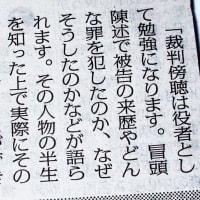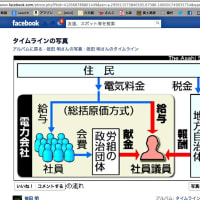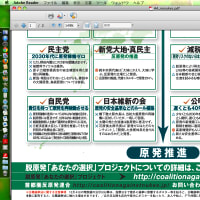今回は似た内容を扱った1、2章の要約である。『1 なぜ英国はEU離脱を選んだのか?』と『2 「グローバリゼーション・ファティーグ」と英国の「目覚め」』の。なお、ファティーグとはフランス語で疲労という意味だ。
ただ、この二つは同じような内容で、前者はかなり長いが相手の質問に答えたインタビュー報告という断片的内容。なので、一応著者が「まとまったもの」として文藝春秋16年9月号に載せたという後者を中心にして、前者の内容を付け足すという形でまとめることにする。
私が2015年の自著で英国離脱を予言したと言われて来たが、これまでの私の予言とはちがって、これは直感的、本能的なものである。対して、ソビエト崩壊、ユーロの瓦解、アラブの春などについての私の予言は、歴史人口学に基づく客観的なものだ。
イギリスは、ドイツ支配のEUから独立したのである。イギリスエリート支配にウンザリした英労働者階級が、EUからの英国議会の主権回復を選んだのだ。普通の英国エリートや、その多数は、残留を望んだのだから。この英分離は、グローバリゼーションへの反乱であり、その終わりの始まりであり、EU崩壊の引き金になるだろう。
これは一見、大衆が陥りやすいポピュリズムにも見えるが、そうではない。自分の利益だけを追求するエリートに対して、英保守党議員の半数が労働者の側に付いたことによって起こった出来事であって、これは驚くべき歴史的事件である。前ロンドン市長・ボリス・ジョンソンとか、前司法大臣・マイケル・ゴーブとかが、ポピュリズムに流れ得た大衆をそこから救い出したのである。
今後のEUは、金融関連と移民関連とか、その国の種々重大な要求によって、「これがだめならEUを出る」という形を取るだろう。ではその先の各国はどうなるか。格差のない民主国家になるのか、エリート政権が変化を拒否して行き過ぎた移民、格差、競争という現状のグローバリゼーションを続ける国のままか、大変難しい所だ。
ドイツが最も心配である。日本と同じように出生率の少ない、老人大国なのに、力にまかせた経済支配への欲望を諦めない国だ。そのために移民を無制限に入れている。スペイン、イタリア、ギリシャから熟練労働者を入れることによってこれらの国を疲弊させ、中東からは単純労働者をどんどん入れている。特にドイツ以外のEU各国エリート層が自国国民を無視するというような「エリートの無責任」を、ドイツのこの政策が促しているという不安定側面が心配だ。
アメリカは(トランプかヒラリーかという現時点なのだが)当面、自国民を大事にする民主国家に向かうのか、しばらくグローバリゼーションのままなのか、これも難しい。特に、今のような時にはこういう論点もある。
『おおきく時代が変化するときには社会全体、そして政治勢力のあり方もガラッと変わるものです。「グローバリゼーション疲労」に影響されるのは、片方の陣営だけとは限りません』
とこう述べてきて、トッドは第2章をこう結んでいる。
『私は長期的には楽観主義者ですから、近代国家の再台頭というモデルについて、いかなる疑いも持っていません。イギリスに続く「目覚め」が、フランス、そして欧州各国で起きることで、ドイツによる強圧的な経済支配から「諸国民のヨーロッパ」を取り戻せるはずです。それこそが欧州に平和をもたらす、妥当だという意味で理性的な解決策であると私は確信しています』
なおここで、トッドの歴史人口学という珍しい学問を、ちょっと説明しておきたい。各国の人口統計関連数値の変遷や比較をしながら、人類、歴史とはなんぞやを研究していく学問と言えば良いだろうか。この関連数値とは、こういうものである。家族形態、出生数や率、子ども数、国の年齢構成、自殺率、アルコール依存数、識字率、進学率、死亡率、死亡因、平均寿命、移民政策やその数、などなどである。これらについてその変遷や各国比較から、その国の来し方行く末を見ていく学問である。これらの数字には確かに、国の相対的貧富、格差や平等度、財産などの「結果」ではなく「機会均等」という意味での正当な平等度、つまり民主主義度、公正な社会であるかどうかなどなどが顕れるだろう。また、このような数値変化の国家比較をすることのなかから、その国の現状がよく見えて、その未来も見えてくるという側面もあると思う。予言がよく当たる学者として注目されてきたのも、こういう学問の性格によるのだろう。
こういう意味すべてから、トッドは己を哲学者では全くなくって、経験主義的学問の徒、実験科学者に近いと理解しているようだ。これは、抽象的な哲学を嫌うという意味であり、哲学的にはイギリスはトッドと同じケンブリッジが生んだバートランド・ラッセルら論理実証主義哲学を方法論的背景として持っている人だということにもなろう。ちなみにトッドは、ラッセルの「西洋哲学史」の変わらぬ愛読者だと述べている。
(あと1回で終わることにしました)
ただ、この二つは同じような内容で、前者はかなり長いが相手の質問に答えたインタビュー報告という断片的内容。なので、一応著者が「まとまったもの」として文藝春秋16年9月号に載せたという後者を中心にして、前者の内容を付け足すという形でまとめることにする。
私が2015年の自著で英国離脱を予言したと言われて来たが、これまでの私の予言とはちがって、これは直感的、本能的なものである。対して、ソビエト崩壊、ユーロの瓦解、アラブの春などについての私の予言は、歴史人口学に基づく客観的なものだ。
イギリスは、ドイツ支配のEUから独立したのである。イギリスエリート支配にウンザリした英労働者階級が、EUからの英国議会の主権回復を選んだのだ。普通の英国エリートや、その多数は、残留を望んだのだから。この英分離は、グローバリゼーションへの反乱であり、その終わりの始まりであり、EU崩壊の引き金になるだろう。
これは一見、大衆が陥りやすいポピュリズムにも見えるが、そうではない。自分の利益だけを追求するエリートに対して、英保守党議員の半数が労働者の側に付いたことによって起こった出来事であって、これは驚くべき歴史的事件である。前ロンドン市長・ボリス・ジョンソンとか、前司法大臣・マイケル・ゴーブとかが、ポピュリズムに流れ得た大衆をそこから救い出したのである。
今後のEUは、金融関連と移民関連とか、その国の種々重大な要求によって、「これがだめならEUを出る」という形を取るだろう。ではその先の各国はどうなるか。格差のない民主国家になるのか、エリート政権が変化を拒否して行き過ぎた移民、格差、競争という現状のグローバリゼーションを続ける国のままか、大変難しい所だ。
ドイツが最も心配である。日本と同じように出生率の少ない、老人大国なのに、力にまかせた経済支配への欲望を諦めない国だ。そのために移民を無制限に入れている。スペイン、イタリア、ギリシャから熟練労働者を入れることによってこれらの国を疲弊させ、中東からは単純労働者をどんどん入れている。特にドイツ以外のEU各国エリート層が自国国民を無視するというような「エリートの無責任」を、ドイツのこの政策が促しているという不安定側面が心配だ。
アメリカは(トランプかヒラリーかという現時点なのだが)当面、自国民を大事にする民主国家に向かうのか、しばらくグローバリゼーションのままなのか、これも難しい。特に、今のような時にはこういう論点もある。
『おおきく時代が変化するときには社会全体、そして政治勢力のあり方もガラッと変わるものです。「グローバリゼーション疲労」に影響されるのは、片方の陣営だけとは限りません』
とこう述べてきて、トッドは第2章をこう結んでいる。
『私は長期的には楽観主義者ですから、近代国家の再台頭というモデルについて、いかなる疑いも持っていません。イギリスに続く「目覚め」が、フランス、そして欧州各国で起きることで、ドイツによる強圧的な経済支配から「諸国民のヨーロッパ」を取り戻せるはずです。それこそが欧州に平和をもたらす、妥当だという意味で理性的な解決策であると私は確信しています』
なおここで、トッドの歴史人口学という珍しい学問を、ちょっと説明しておきたい。各国の人口統計関連数値の変遷や比較をしながら、人類、歴史とはなんぞやを研究していく学問と言えば良いだろうか。この関連数値とは、こういうものである。家族形態、出生数や率、子ども数、国の年齢構成、自殺率、アルコール依存数、識字率、進学率、死亡率、死亡因、平均寿命、移民政策やその数、などなどである。これらについてその変遷や各国比較から、その国の来し方行く末を見ていく学問である。これらの数字には確かに、国の相対的貧富、格差や平等度、財産などの「結果」ではなく「機会均等」という意味での正当な平等度、つまり民主主義度、公正な社会であるかどうかなどなどが顕れるだろう。また、このような数値変化の国家比較をすることのなかから、その国の現状がよく見えて、その未来も見えてくるという側面もあると思う。予言がよく当たる学者として注目されてきたのも、こういう学問の性格によるのだろう。
こういう意味すべてから、トッドは己を哲学者では全くなくって、経験主義的学問の徒、実験科学者に近いと理解しているようだ。これは、抽象的な哲学を嫌うという意味であり、哲学的にはイギリスはトッドと同じケンブリッジが生んだバートランド・ラッセルら論理実証主義哲学を方法論的背景として持っている人だということにもなろう。ちなみにトッドは、ラッセルの「西洋哲学史」の変わらぬ愛読者だと述べている。
(あと1回で終わることにしました)