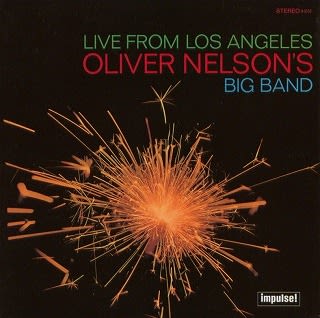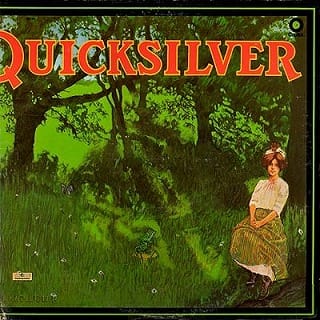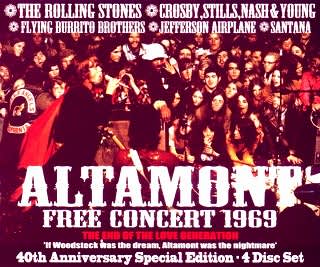■真冬の帰り道 / ザ・ランチャーズ (東芝)
昨日は久々におやじバンドでライプやってきました。
まあ、出来はそれなりでしたが、気の合う仲間が集って音を出すのは、やっぱり楽しいですね。
さて、本日のご紹介は、そんなサイケおやじが高校生の時に入れてもらっていた同好会のバンドで、最初に演じた思い出のメロディ♪♪~♪ 今やGSの定番でもあるランチャーズの大ヒット曲です。
ご存じのようにランチャーズと言えば加山雄三のバックバンドとしてスタートし、何回かのメンパーチェンジもあったわけですが、昭和40(1965)年の爆発的なエレキブームの頃から、その中心になっていたのが、加山雄三の従兄弟にあたる喜多嶋瑛と修の兄弟でした。
しかし当時は「エレキは不良」という不条理な社会の掟の所為で、特に高校生だった喜多嶋修に芸能活動は許されず、このあたりの事情は「夜空の星」や「ブラック・サンド・ビーチ」のところでも書きましたが、実際のステージやテレビ出演時には別のメンバー編成になっていました。
そしてようやく喜多嶋修が高校を卒業した昭和42(1967)年、既にGSが大ブームになっていた真っ只中の11月に発売されたのが、加山雄三から独立したランチャーズのデビュー曲「真冬の帰り道」です。
憧れの女の子と歩く真冬の道行き、それでも彼女に愛の告白が出来ない弱気な男の心情吐露を綴った歌詞にジャストミートの胸キュンメロディは、もちろん喜多嶋修の作曲で、全体としては「ラバーソウル」期のビートルズに深く影響されたフォークロック歌謡の決定版ですから、忽ちの大ヒットになりましたですね。
当時を体験されなかった皆様にしても、聴けば納得という、お馴染みの歌と演奏のはずです。
ちなみに当時のメンバーは喜多嶋修(vo,g,key)、大矢茂(vo,g)、渡辺有三(b)、喜多嶋瑛(ds) の4人組で、爽やかなルックスとスマートなファッションセンスは、明らかに「エレキは不良」では無く、ハイソなイメージも強く漂わせていました。
そして発表されるレコードには正統派GS歌謡、フォークロック、サイケデリック、クラシック趣味、さらにビートルズからの様々な影響が、喜多嶋修というグループでは音作りのほとんどを手掛ける若き天才によって表現されていたのです。
ただし、それが当時としては進み過ぎていたのも、また事実でした。そうした洗練された部分は評論家の先生方や業界の一部からは認められていたものの、一般的なファンはある意味での下世話な感覚の方を好んでいたのが、昭和40年代だったのです。
それが突然、当時の東宝ではトップのアイドル女優だった内藤洋子と喜多嶋修の恋愛関係が報じられことから再び、この「真冬の帰り道」の歌詞が意味深に取り上げられたのは皮肉でした。
ただし、後に知ったところによれば、その頃の喜多嶋修は内藤洋子に対しても、ビートルズの話ばっかりしていたそうですし、最終的には結婚した二人にしても、この歌は面映ゆいのかもしれないなんて、余計なお世話を想像するのは私だけでしょうか。
まあ、それはそれとして、ランチャーズは後に高く評価されるアルバムを2枚作っているのですが、やはり「真冬の帰り道」を抜きにしては語れないバンドでしょう。実際、この曲は何時聴いても、イイですよねぇ~~♪
最後になりましたが、若き日のサイケおやじが演じた「真冬の帰り道」の経緯について、実は高校の時のバンドは私が入学する前年までは歴とした「部」扱いでした。それが秋の学祭で学校側の警告を裏切る形で先輩諸氏がギンギンのサイケデリックをエレキの大音響で演じたとかで、「同好会」に格下げされ、しかもブラスバンド部の預かりという肩身の狭さに……。
もちろん存続出来たのは、当時の流行になっていた生ギター主体の歌謡フォークを歌いたいという隠れ蓑があったからですし、実際、エレキを使うバンド形式をやりたがっていたのは、私が入った時には僅か4人になっていました。
ですから、幸か不幸か、とにかく直ぐにレギュラーに入れたというわけですが、そんなこんなの経緯から練習はともかくも、発表会の演目は極めて制限が強く、なんとか許可を得たのが、この「真冬の帰り道」だったというわけですから、その楽曲には大人にも許容される魅力があるということです。
そしてサイケおやじは恥ずかしながら、その時にエレキギターでリードを弾かせていただきましたが、ランチャーズの演奏に聞かれるような間奏での凝ったアンサンブルを再現出来る技量はもちろん無く、オリジナルの曲メロを無難になぞるのが精いっぱいでした。
このあたりは今でも難しいと思いますよ、言い訳じゃありませんが。それほどランチャーズの演奏は洗練されたフィーリングが強かったのです。
ということで、今でも額に汗が滲む思い出なんですが、そんな初々しい気分がすっかり居直りに変化している現在の私は、やっぱり中年者の独り善がりを反省するのでした。