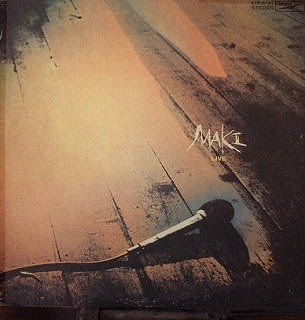■Eagles (Asylum)

最近は有名人の訃報が連続したり、日本を代表する大企業が潰れたり、また永田町が瀕死状態だったり、とにかく歴史の流れが加速しているのを感じます。そして、なればこそ、OLDWAVE な私の魂も熱くなるのでしょうか、なんとなく時の流れの中でハッとさせられた思い出のレコードを取り出してしまいます。
例えば本日ご紹介のアルバムは説明不要、ウエストコーストロックを確立させたイーグルスのデビューアルバムで、発売された1972年当時はカントリーロックと呼ばれていた歌と演奏が、実に新鮮でした。
というか、そのカントリーロックとは一線を画す、何かがあったからこそ、若き日のサイケおやじは惹きつけられたのです。
ご存じのように、件のカントリーロックとはバッファロー・スブリングフィールドから派生したポコ、結果的に解散が近づいていたザ・バーズ、ストーンズ経由で知ったアラン・パーソンズとフライング・ブリトー・ブラザース、さらにはCSN&Yや諸々のフォーク&カントリー系の歌手も含めて、そのカラッとして長閑なサウンドと覚えやすいメロディは、安心して聴けるアメリカの大衆音楽そのものでした。
つまりアブナイ雰囲気の魅力に惹きつけられ、乏しい小遣いから迷って買ったレコードが失敗するケースも間々あったサイケデリックやハードロックとは、明らかに異なっていたのです。そして、それゆえに、若き日のサイケおやじには、イマイチの刺戟が不足していたわけですが……。
そこでラジオから流れてきたのは、イーグルスのデビューヒットになったシングル曲の「Take It Easy」で、その軽快にしてハードなノリ、せつなさがそこはかとなく滲むコーラスワーク、そして何よりも和みの曲メロを活かした演奏♪♪~♪
本当に聴いた瞬間、もう一度、聴きた~い! そう思いましたですねぇ~♪
ただし当時の我国では、カントリーロックそのものが市民権を得ていなかったというか、それほど人気のあるジャンルではなく、むしろ歌謡フォークにも一脈通じた軟弱系音楽と受け取られていたフシがあります。
当然ながら、その頃の洋楽ロックの王道は所謂ブリティッシュであり、ハードロックやプログレが全盛期でしたし、それに対するシンガーソングライターという流行の中ではニール・ヤングやキャロル・キング、ジェームス・テイラー等々の歌と演奏に、カントリーロックの味わいが認められていたに過ぎませんから、そのどちらにも属さないイーグルスは中途半端だったのが、我国での実相ではなかったでしょうか。
しかし、その中途半端さが、後々に効いてきたのは言わずもがなです。
A-1 Take It Easy
A-2 Witchy Woman / 魔女のささやき
A-3 Chug All Night
A-4 Most Of Us Are Sad / 哀しみの我等
A-5 Nightingale
B-1 Train Leaves Here This Morning / 今朝発つ列車
B-2 Take The Devil
B-3 Earlybird / 早起き鳥
B-4 Peaceful Easy Feeling / 愛のやすらぎ
B-5 Tryin'
デビュー時のメンバーはグレン・フライ(g,vo,key)、バーニー・レドン(vo,g,b,etc)、ランディ・マイズナー(b,vo)、ドン・ヘンリー(ds,vo) という4人組で、リンダ・ロンシュタットのバックバンドが独立したというエピソードが定着していますが、リアルタイムの我国ではリンダ・ロンシュタットという歌手その人が一般には知られていませんでした。また後追いで聴いた彼女の当時の音源にも、イーグルスの面々が揃って参加した演奏は無いと思うんですが……。
それでも業界はかなり期待した宣伝をやっていたように記憶していますし、何よりも前述した「Take It Easy」に続き、このアルバムからカットされた「魔女のささやき」と「愛のやすらぎ」のヒットが連発されたのは、なかなか凄いことだったと、今は感慨深いのです。
そして私は、このアルバムが当時のNHKラジオFM放送で丸ごと放送された時、しっかりとエアチェックしての聴きまくり♪♪~♪
まずは最高という「Take It Easy」が、軽快な演奏とは逆もまた真なりという重たいドラムス、さらに後半で素晴らしい彩りとなるバンジョーがあってこその完成度ですよねぇ~♪
また続けてヒットした「魔女のささやき」はインディアンの太鼓のリズムをハードロックに融合させた、まさに温故知新の名曲名演ですし、個人的にはこのアルバムの中で一番好きな「哀しみの我等」は、シンミリと歌われる曲メロの良さとせつないコーラスが絶品♪♪~♪ そしてA面ラストの「Nightingale」が、これまたウエストコーストロックの典型的な響きを確立する、ギターロックの痛快な歌と演奏になっています。
こうしてB面のパートに入ると、そこにはリラックスしたカントリーロック王道の「Train Leaves Here This Morning」、妙にテンションが高く、ちょいと異端なムードさえ感じられる「早起き鳥」が、実はとても新しかったのがリアルタイムだったと思います。
その意味で、これまたシングルヒットした「愛のやすらぎ」は、ロックを通じて盛り上がっていた「ウエストコースト中華思想」を確実に煽るものでしょう。
そこにはバンドとしての纏まり、アコースティック&エレキのギターが巧みにミックスされたアレンジとサウンド作りの新鮮な感覚、コーラスの上手さとムードの良さは、何度聴いても魅力的♪♪~♪
ですから、どーしてもレコード本体が欲しくなって、ついに年末恒例だった某デパートの輸入盤セールでアルバムをゲットすると、またまたびっくり!
なんと制作には「ブリティッシュロックの音」を作り出したエンジニアにして、ストーンズやザ・フーのプロデュースにも大きく関わっていたグリン・ジョンズの名前がクレジットされていたのです。
う~ん、その瞬間、イーグルスが聞かせてくれたヘヴィな演奏のミステリが氷解しましたですねぇ。
実は私がイーグルスで特徴的に感じていたのが、ドン・ヘンリーの失礼ながら鈍重なドラミングで、それが英国伝来のヘヴィロックなムードと結びついていたといえば、贔屓の引き倒しでしょうか。ウエストコーストのバンドでありながら、セッションがイギリスで録音されたあたりも、意味深です。
そして個人的には、それだからこそ、軽快なノリが命のカントリーロックに、もうひとつの新しい命が吹き込まれたのではないかと推察していますし、新しさの源だったと思います。
もちろん録音そのものも、従来の西海岸ハリウッドポップスに共通していたヌケの良さよりも、幾分ですが曇った感覚で、このあたりの検証は今日まで、各方面でなされていますが、拙稿「レット・イット・ビーの謎13回」も、ご一読願えれば幸いです。
ということで、このアルバムはウエストコーストロックの聖典となりましたが、何よりもカントリーロックの「ロック」という部分が極めて強く出ているのが、その秘密かもしれません。例えばバーニー・レドンが聞かせてくれるバンジョーやマンドリンからは、破天荒なほどにロックビートがピンピンに感じられますし、重心の低いドラムスとベースのコンビネーションは、当たり前過ぎるほどロックしていると思います。
それと哀愁たっぷりのコーラスワーク♪♪~♪ 胸キュンフィーリングが随所に現れては消えていく、まさに刹那の曲メロ♪♪~♪ まあ歌詞についてはリアルタイムでは真意を測りかねるところもありましたが、日本人の洋楽の楽しみ方としては、充分に許容出来るヒット盤でした。
結局は、これがイーグルスでは一番に好きなアルバムかもしれません。特にA面の流れは最高の極みつき!
最後に個人的な夢想ではありますが、オーラスの「Tryin'」にストーンズバージョンがあったらなぁ~~、そう思う気持が続いているのでした。