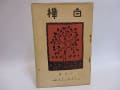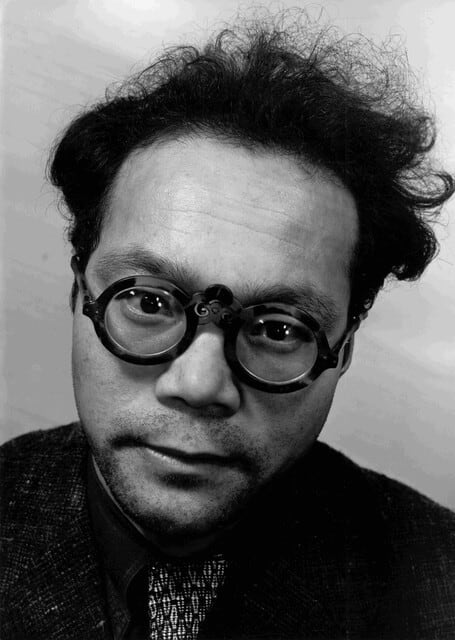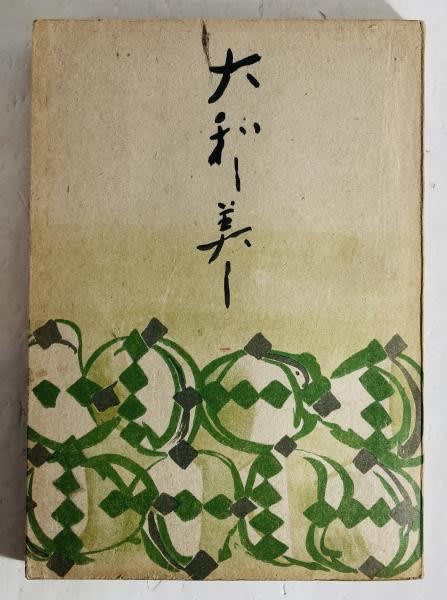無骨な手が肩先に降れるのを感じた。
チヤはぴくりと身体を震わせた。
「・・・チヤ子 ありがとう。よぉく帰ってきてくれた」」
チヤは、そっと顔を上げた。
「ったく、わかんねのか?
ワぁの命にも等しいもんは板木では、ね。・・・おメだ」
ようやく、チヤは気がついた。
自分はひまわりだ。
棟方という太陽を、どこまでも追いかけてゆくひまわりなのだ。
棟方が板上に咲かせた花々は数限りない。
その中で、もっとも力強く、美しく、生き生きと咲いた大輪の花。
それこそが、チヤであった。

終章 1987年 (昭和62年) 10月 東京 杉並
ここから、本編の主人公
棟方チヤさんの回想部分の話に入っていきます。

あの人は、多くの熱心な支援者に恵まれた、運の強い人でした。
でも、運がよかっただけじゃない。決めたことを成し遂げるまで
決してあきらめない不屈の精神、人一倍の努力を重ねたからこそ、
運気を呼び寄せたんじゃないかと思います。
私たち夫婦の人生を振り返ってみると、いくたびも、
「あのとき、もしも…」と思わずにはいられないことがありました。
出会ったあの日、もしも私がイトちゃんの家に行っていなかったら。(第2話)
再会した日、もしもお互いに弘前のデパートに居合わせなかったら。(第4話)
国画会の展示場で、もしも柳先生と濱田先生が偶然廊下を通りかからなかったら。(第9話)
戦時中、もしも疎開先を富山ではなく青森にしていたら。(14話)
大空襲の前日、こしも<釈迦十大弟子>の板木の梱包材として
送り出していなかったら。(第14話)
もしも、もう一日だけと粘って、あの夜、私がひとりで代々木の家に
残っていたら。(第14話)
もしも・・・そう、もしもあの人がゴッホと出会ったいなかったら。(第5話)
すべての「もしも」の分かれ道に、あの人も私も
最善の道を選んでいた。そういうふうにできていた。
と思われてなりません。
悲しい運命に終わった「もしも」もあります。
我が家の聖画だったゴッホの<ひまわり>。
空襲に燃え尽きた板木とともに、あの複製画も灰になってしまった。
・・・もしもあの戦争が起こらなっかったら。
大空襲の前日に、梱包して送った「家財道具」<釈迦十大弟子>の板木。
あの大混乱の中で、奇跡的に届いたんです。
命拾いした大切な板木。無駄にするわけにはいかないと、棟方は
二菩薩を彫り直して、再び六枚の板木を揃えました。
あるとき、思いがけないチャンスが舞い込みました。
ブラジルのサンパウロで開催される国際美術展、サンパウロ・ビエンナーレに
棟方の板画作品が出品されることに、新作の他、<二菩薩釈迦十大弟子>を選び
改めて摺り直し、躍動する造形が海を越えて人々の心をつかみました。

棟方が版画部門で最優秀賞を受賞したんです。
こおれにはあの人も私も驚きました。
柳先生も濱田先生も河井先生も、棟方がやってのけた。
とそれは喜んでくださって。
翌年のヴェネチア・ビエンナーレにも同様に新作と<二菩薩釈迦十大弟子>が
送り込まれました。そして棟方にもたらされたのが、ヴェネチア・ビエンナーレ
のグランプリ、国際版画大賞だったのです。
日本のゴッホになる、とあの人は最初、言いました。
だけど結局、あの人は、ゴッホにはならなかった。
ゴッホを超えて、とうとう、世界の「ムナカタ」になったんです。

最後に、とっておきの話をお聞かせしましょう。
世界的に「ムナカタ」の名前が知られるようになったあと、私たちは世界中の
あちこちからお招きを受けて、ありがたく出かけてゆきました。
アメリカ各地、ヨーロッパ諸国、インドも訪問しました。
中でも忘れられないのが、フランス。
棟方たっての希望で、ゴッホが人生の最後に暮らしたという小さな村、
オーヴェル=シュル=オワーズを訪ねました。
村はずれに共同墓地があります。
そこにゴッホと弟のテオのお墓があり、兄弟が仲良く並んで眠っています。

棟方が板画にした「ゴッホ兄弟の墓の柵」

ニューヨークやフィラデルフィアの美術館で、棟方はついにゴッホの
「本物」の絵を見ることができました。
ニューヨーク(メトロポリタン美術館)
<2本切ったひまわり> <ゴッホ自画像>
フィラデルフィア美術館 <ひまわり>

「白樺」の1ページに初めて<ひまわり>を見た日から40余年が経って
いました。
ちょうどブログをアップし始めた先月に
「 雑誌「芸術新潮」4月号が発売され

ゴッホ、ゴーギャン、セザンヌ
原田マハ のポスト印象派物語 」を読んでいました。
奇しくも・・・この中に
原田マハさん この「板画に咲く」に合わせて?
ゴッホ ゆかりの 「オーヴェル・シュル・オワーズ」を
訪ね、ゴッホ兄弟の墓地に・・・
なんと計算された・・・と。
それが この写真。
= 原田マハ ゴッホ兄弟に墓の前で =

・・・・あの人は
ゴッホ兄弟のお墓に向かって深々と頭を下げました。
そしてこう言ったんです。
お許しください、ゴッホ先生。
ワんどの墓、そっくりに造らせていただきます。
まったく、あの人ときたら。

「わだばゴッホになる」という棟方の言葉
愛するゴッホの墓と同じ形をした棟方と奥様チヤさんの墓
左が棟方とチヤさんのお墓
右は棟方家の墓
チヨさん「ずいぶん長い話になってしまいましたわね。
ありがとうございます。」
これで 「原田マハ (板画に咲く)1~15話
変?編集 私のブログも 15話で終わりたいのですが・・・
原田マハさんの小説から離れ、少し時間を戴いた後
戦後の活躍作品についてと、
まだ紹介していなかった「手紙」などを と思ってます。
「ムナカタ志向美術館」とでも題しましょうか?
私のブログも ながながとお付き合いいただき
ありがとうございました。
それでは また よろしく (^_-)-☆