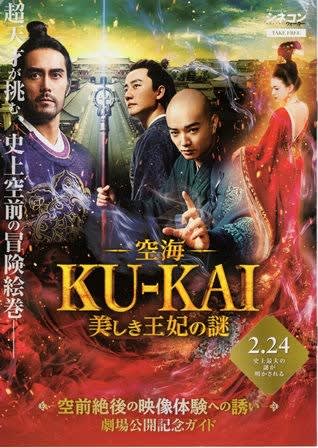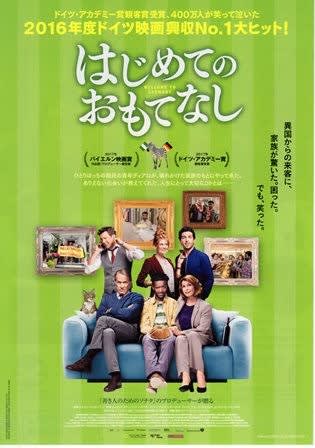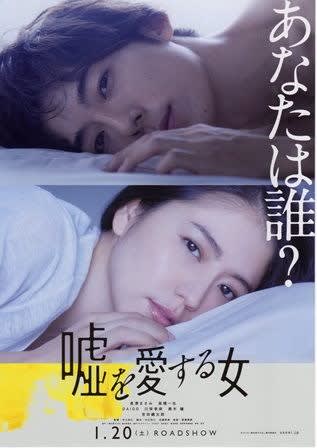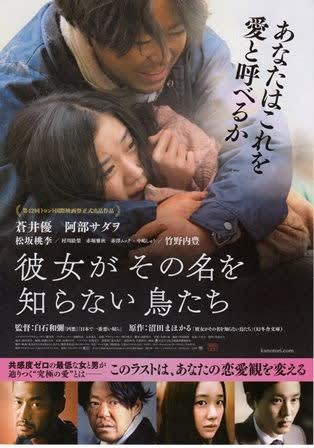アメリカの歴代政権が隠してきた、ベトナム戦争の実情を記す機密文書の報道をめぐる、政府と新聞の戦いを描いている。
スクープしたニューヨーク・タイムズが異例の差し止め命令を受ける中、入手した文書を公表に踏み切ったワシントン・ポストに焦点を当て、新聞ジャーナリズムの使命を問う迫真の展開だ。
政府が必死になって隠そうとする秘密を、報道機関が突き止め、国民に提供する。
現代の日本でも、今やそんな報道はある新聞など日常茶飯事だ。
勿論、それを快く思わない政治家も大勢いるわけで・・・。(苦笑)
この映画は、1971年のアメリカを舞台に、巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督が、メリル・ストリープ、トム・ハンクスの二人の名優を主演に、真実を伝えるべきか否か、悩む新聞人の実話を重厚なタッチで描き切っている。
ベトナム戦争が泥沼化していた1971年・・・。
ワシントン・ポストは、戦況を客観的に分析した国防省の最高機密文書の全容を、特報すべく準備をしていた。
時のニクソン政権側が、記事差し止めに動き、経営に圧力を加えるのは明らかであった。
夫の死に伴い、専業主婦からワシントン・ポスト紙の社主となったグラハム(メリル・ストリープ)は、経営陣から軽んじられていた。
ニクソンは、国の安全保障を脅かすとして、すでにニューヨーク・タイムズの差し止め命令を裁判所に要求、一方、記者の奮闘で文書を入手した編集主幹ベン・ブラッドリー(トム・ハンクス)は即座に記事化を命じる。
ライバル紙のニューヨーク・タイムズに先を越され、ワシントン・ポストとしてはこの全貌を公表しようと奔走する。
報道の自由は報道しかないとひるまないブラッドリーだったが、最後の決断はグラハムに委ねられる・・・。
政府を敵に回してまで、本当に記事にするのか、信念をかけた彼女の決断は・・・?
報道の自由は、合衆国憲法修正第1条の定める民主主義の礎だ。
報道機関の仕えるべきは国民なのだし、断じて統治者ではない。
近頃、どこか何か勘違いをしていないだろうか。
日本の統治者も、このことはよくよく心得てほしいものだ。
ドラマの中で、政権幹部と懇意で報道を躊躇するグラハムが、新聞社の矜持を自覚し、堅固な志操の経営者へと華麗な変身を遂げていく様が爽快に描かれている。
この映画の背後には、トランプ政権の誕生があったことは間違いないようだ。
主要な舞台は、新聞社やグラハムの自宅だ。
真実に迫っていく面白さにはもう一工夫が欲しいところだが、グラハムとブラッドリーこの二人のジャーナリストが、心をひとつにして戦っていくシーンが胸を熱くするのだ。
一介の専業主婦だった女性が、国家を揺るがす重大な決断を迫られ、その戸惑い、苦悩を名優ストリープが細やかに演じる。
メリル・ストリープは、急ピッチではないがたおやかに成長する強い女を演じて上手いし、トム・ハンクスは硬骨漢の役ながらちょっと格好よく役になりきっている感じがする。
二人はさすがと思わせる。
政治家はよく嘘をつき、それを糊塗しようといろいろあの手この手のよくない手段を講じて、時々ニタニタなどしながら平然としている。
国民を何と思っているのか。
出まかせの言い訳け、公文書の平然たる改竄と隠蔽、そう思うと日本もアメリカも同じではないか。
何もかも、すべては歴史が証明してくれる。
責任逃れにああだこうだと汲々としている政治家は、この映画、一本筋金の入った気骨ある力作をどう観るだろうか。
メディアが真実を追求する。
新聞社の輪転機が唸りをあげて動き出す。
民主主義は勝たねばならない。
権力側に阿るのではなく、このアメリカ映画「ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書」は、力強い脈動を感じさせる重厚な一作だ。
この作品、まず面白くないはずがない。観て損はないはずだ。
自分のことをよく書かない新聞を名指しで決めつけ、権力者の言いなりとなるテレビや新聞にニンマリしている政治家の姿をよく見かけるのだが、国民にどう映っているか。
驕れるものは久しからずである。
[JULIENの評価・・・★★★★☆](★五つが最高点)
次回はアメリカ映画「レッド・スパロー」を取り上げます。