
朝夕めっきり冷え込み、冬が駆け足でやってきたようだ。
コロナ禍で、外出を控えめにしていたが、思い切って出かけた。
もうとうに薔薇の季節は終わっていて、久しぶりに静かな鎌倉であった。
訪れた当日の早朝は、幸せなことに、来館者は私一人で、貸し切りのような閲覧者となって、かえってよかったと安堵した。
1935年から鎌倉で暮らし、日本人で初めてノーベル賞を受賞した川端康成(1899年~1972年)の数々の作品をしのびながら、一貫して自身追求してきた日本の伝統美やこの地とゆかりのある深みを感じさせて、ミニ展示なりによくまとまっている。
作品の原稿や愛蔵品、パネル紹介など80点から、故人の紡いだ日本の「美」を感じとることができる。
川端については語り尽くせぬことが多く、ノーベル賞についてはそもそも川端康成と、三島由紀夫の二人が有力候補だったが、師弟の関係にある年長者川端を、三島周辺の反対を押し切って推奨したという話は有名だ。
ノーベル賞受賞式での川端康成の講演は、「美しい日本の私」であった。
当初川端は、「美しい日本と私」というタイトルで講演を予定していたが、「美しい日本の私」となった。
いずれにしても、「抒情の美」を描いて、数々の名作を残した川端は、日本文学の名を高め、世界がそれを認めた証となった。
川端は源氏物語の現代語訳を試みていたが、こちらは果たせぬまま、自死の道を選んだことは残念でならない。
川端展については、これまで文学館などで特別展が幾たびか開かれてきたが、鎌倉文学館で手にした小冊子(図録)などダイジェストしてよくまとまっており、一見に値するだろう。
今年も残り少なくなってきた。
この特別展、12月23日(水)まで。
鎌倉文学館(TEL 0467-23-3911)へは、江ノ電由比ヶ浜駅から徒歩7分だが、私はJR鎌倉駅下車、中央図書館前から裏小路を通り抜け、歩きやすい散歩道から、吉屋信子旧邸の前を通って文学館を訪れた。
勝手知ったいつもの散歩道である。
月曜日は休館、平日、日曜祭日午前9時から入館できる。












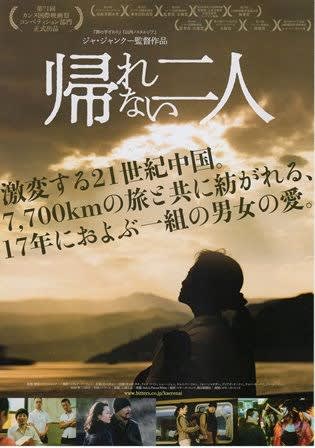
 路傍に真っ赤な彼岸花が咲いていた。
路傍に真っ赤な彼岸花が咲いていた。



