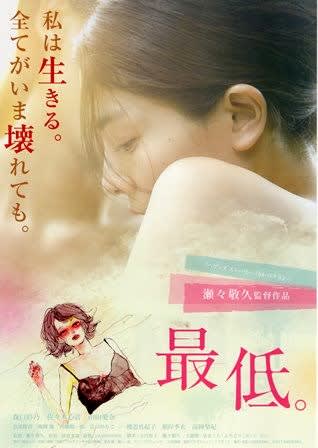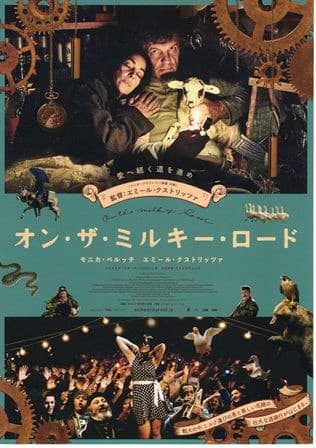明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い申し上げます。
世界史を紐解けば、いつの時代にも国や世論を巻きこむ逆転劇があるものだ。
したたかで巧妙な戦略もある。
時には巨大な勢力や政界をも敵に回して、善かろうが悪かろうが、かつてない結末を導こうとするものだ。
政治や社会さえも、その未来を見通す知識と知恵で思い通りに動かす・・・、それがロビイストという職業なのだ。
止まることを知らないスピード感で、誰もが予測不能な驚愕の結末を迎える。
「マリーゴールド・ホテル」(1910年)のジョン・マッデン監督のフランス・アメリカ合作映画である。
これは天才的な戦略を駆使して、政治を動かすロビイストの実態に迫った、社会派のサスペンスだ。
見応えは十分だ。
ワシントンD.C.で、スパークリング上院議員(ジョン・リスゴー)による聴聞会が開かれていた。
証人となっているのは、敏腕ロビイストとして名高いエリザベス・スローン(ジェスカ・チャスティン)でコール=クラヴィッツ&ウォーターマン在職中に手がけた仕事で彼女は不正を行なっていたとされ、その真偽が問われていた。
完璧を求めるエリザベスの仕事ぶりは、クライアントの要望を叶えるため、これはと思う戦略を立てたら一切妥協を許さなかった。
彼女の仕事ぶりは政治やメディアからも一目置かれており、社内でも「ミス・スローン」と呼ばれ、畏れられる存在だった。
眠る間も惜しんで、戦略の根回しや裏情報をつかむのを目的とし、私生活での交遊はゼロに等しく恋人ももちろんいない。
男性への欲望は高級エスコートサービスで満たしていた。
そして、聴聞会からさかのぼる3カ月と1週間前、本編は幕を開けるのだが・・・。
このドラマでは、アメリカの銃規制法案の賛成派と反対派が対立しており、スローンの小さなロビイ会社はこの法案に賛成の立場をとる陣営を支援していた。
ロビイストのスローンは、法案の議会可決をめぐって、彼らへの暗躍を見せ、息をもつかせぬサスペンスドラマとなった。
さすが、スローンも予期しなかった事件が起きたりする。
政敵の会話の盗聴や、スパイを潜入させることなど朝飯前だ。
次々と大胆な策を繰り出し、ついには過半数に近い議員の賛成票を取り付けるに至るのだが・・・。
自分の部下を道具のようにしか思わない、スローンの仕事と言ったら圧巻の徹底ぶりだった。
だが欠点もある。
スローンを駆り立てる動機については、よくわからない。不明確なことも多すぎる。
勝つためには手段を選ばぬ彼女の戦い方は、古巣や議員に影響力のある団体から反撃を食らうことになる。
先日だったかラスベガスで銃乱射事件があったが、タイムリーでもある。
アメリカでは何故銃規制が進まないのだろうかと思う。
これはしかし、その事の善悪を問うドラマではないので、いわばアメコミのヒロインをちょっと悪く可愛く見せるところに、スーパーウーマンの戦いを楽しもうといいう狙いもある。
フランス・アメリカ合作映画「女神の見えざる手」は、フィクションではあるけれど脚本はよく練られており、さすがは弁護士だったジョナサン・ペレラで、セリフはくどくどしく、俳優陣の喋りかたも少し早い。
観ているほうはそのあたりをクリアできれば、観て損のない映画である。
ロビイスト役のジェスカ・チャスティンはこの役なかなかハマっている。
しかしロビイストなる彼女らが、モラルや常識もなくその見えざる手で人々の心や巨大な権力すらを、自由に武器も使わずに危険な一線を越えて秘策を繰り出されたりすれば、日本はどうなってしまうだろう。
[JULIENの評価・・・★★★★☆] (★五つが最高点)
次回は日本映画「彼女がその名を知らない鳥たち」を取り上げます。