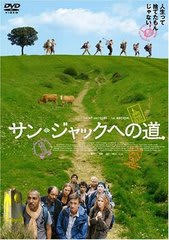
SAINT-JACQUES... LA MECQUE
2005年/フランス/112分
監督・脚本 コリーヌ・セロー
製作 シャルル・ガッソ
出演 ミュリエル・ロバン/クララ アルチュス・ドゥ・パンゲルン/ピエール ジャン=ピエール・ダルッサン/クロード マリー・ビュネル/マチルド
8世紀、現在のスペインのあるイベリア半島に、北アフリカからイスラム教徒が攻め入って来ました。彼らは瞬く間に半島を制圧すると、そのままピレネー山脈を越えて現在のフランスにまでやってきます。それを迎え撃ったのはフランク王国のカール・マルテル。イスラム教徒はここで敗れてピレネー以南まで退いたものの、それからしばらくの間、コルドバを都としてイベリア半島を支配することになりました。
イスラムの支配に対して、スペインのキリスト教徒(カトリック)たちは、奪われた国土を回復する戦いに臨んでいきます。600年近くも続くその運動を「レ・コンキスタ」と呼びますが、その長い過程の中で、カトリックの間に一つの伝説が生まれました。
それは、イエスの十二使徒の一人、聖ヤコブ(スペイン語でサン・ティアゴ、英語でセント・ジェイコブ、フランス語でサン・ジャック)の墓がスペイン北西部のガリシア地方にあるというものです。9世紀始め、星の光の導きにより墓が発見されたと言う。で、その地は「サンティアゴ・デ・コンポステーラ」、つまり「星の野原の聖ヤコブ」と呼ばれるようになり、墓の上には壮大な教会が建てられました。
聖ヤコブには、「サンティアゴ・マタモロス」(ムーア人殺しの聖ヤコブ)という物騒な異名が付けられています。カトリックがイスラム教徒(ムーア人)と死闘を繰り広げているときに、白馬にまたがった聖ヤコブが忽然と現れて勝利に導いたというのです。サンティアゴ・デ・コンポステーラは、イスラム教徒に対するレ・コンキスタの精神的な支えとなり、多くの巡礼者がこの地を訪れるようになりました。宗教改革までは、「聖遺物」に対する信仰が強かったこともあり、もっとも多かった頃には、年間50万人がこの地に巡礼したと言われています。
時は流れて1993年、この地に至るまでの巡礼の道(サンティアゴ・デ・コンポステーラへの道)が世界遺産に登録されると、再び巡礼ブームが沸き起こりました。この映画に登場してくるようなガイド付きの巡礼ツアーも行われるようになったのです。
「サン・ジャックの道」に登場する8人の巡礼参加者の中に、アラブ系の若者2人が含まれていること、さらに、ガイド自身がアラブ系というのが、この巡礼の道をめぐる歴史を振り返ってみると、何とも皮肉めいています。ただし、彼らはそれほど敬虔なムスリムでもないらしく、ムスリムの義務であるはずのメッカの方角を向いての1日5回の礼拝も、少なくとも映画では一度も描かれません。しかも、若者のうち1人は思いを寄せる女の子目当てという不純な動機だし、もう1人は、ホントかどうか定かではないけれど、「メッカへの巡礼」だと勘違いしている。
そういえば、この3人は別格としても、ほかの参加者だって、「あつい信仰心」から巡礼に参加しているとは思えない。母親の遺産を受け取る条件として嫌々参加した仲の悪い3きょうだいはもちろん、キャピキャピした女の子2人連れも、今ひとつ参加の動機がつかめない。もう1人、いつも頭をスカーフで覆っている中年女性は、何か秘密がありそうではありますが、それにしても「神に祈る」たぐいのシーンは一度も出てきません。
でも、言えるのは、全員がそれぞれに人生の「悩み」を抱えていて、それを何とかしたいとは思っているということ。3きょうだいの長男ピエールは、持病の心臓病を抱えている上に自殺願望の妻を持ち、真ん中のクララは失業中の夫と子どもを養うために教員として必死に働いている。末っ子のクロードはアル中でもう長いこと失業していて収入がなく、妻とは離婚、娘に金を無心するていたらく。アラブ系の若者は「失読症」で文字が読めないが、母親のためにも何とか字を覚えたいと思っている。
そういう、それぞれが抱える問題や悩みは、巡礼の途中、宿で見る「夢」として描かれていきます。リアルな夢、幻想的な夢。いろんな夢が出てきますが、いずれにしても「真実」につながっているところが興味深いところです。夢の中の光景と、登場人物の背景がつながっている。このあたりの描き方、コリーヌ・セロー監督はうまいなあとつくづく思う。
「巡礼の道」を取り上げながらも、この映画では、宗教についてというより、人間の生き方やコミュニケーションについて、鮮烈に描写されています。鮮烈と言えば、そうした人間模様の背景にある、美しい自然の風景も見逃せません。時にはやさしい光をたたえ、時には厳しい仕打ちを食らわす大自然が舞台になっているからこそ、人々は素直になれるし、自然に「変わって」もいける。巡礼の道というのは、もしかしたら「神への道」ではなく、人間が「自然」に抱かれるための手段なのかも、とさえ思う。
1,500kmもの道のりを、自分の足だけで踏破した者たちは、みんなそれぞれに「本来の自分」を取り戻して、元の場所に帰っていく。結ばれる人たちもいれば、離ればなれになる人もいる。新たに出会う人々もいる。ちょっとした「どんでん返し」もあったりもする。
自然のもとに「帰る」ことで、人間も人間関係も、確実に変わることができる。とてもほっとさせられる映画です。
『サン・ジャックへの道』≫Amazon.co.jp
2005年/フランス/112分
監督・脚本 コリーヌ・セロー
製作 シャルル・ガッソ
出演 ミュリエル・ロバン/クララ アルチュス・ドゥ・パンゲルン/ピエール ジャン=ピエール・ダルッサン/クロード マリー・ビュネル/マチルド
8世紀、現在のスペインのあるイベリア半島に、北アフリカからイスラム教徒が攻め入って来ました。彼らは瞬く間に半島を制圧すると、そのままピレネー山脈を越えて現在のフランスにまでやってきます。それを迎え撃ったのはフランク王国のカール・マルテル。イスラム教徒はここで敗れてピレネー以南まで退いたものの、それからしばらくの間、コルドバを都としてイベリア半島を支配することになりました。
イスラムの支配に対して、スペインのキリスト教徒(カトリック)たちは、奪われた国土を回復する戦いに臨んでいきます。600年近くも続くその運動を「レ・コンキスタ」と呼びますが、その長い過程の中で、カトリックの間に一つの伝説が生まれました。
それは、イエスの十二使徒の一人、聖ヤコブ(スペイン語でサン・ティアゴ、英語でセント・ジェイコブ、フランス語でサン・ジャック)の墓がスペイン北西部のガリシア地方にあるというものです。9世紀始め、星の光の導きにより墓が発見されたと言う。で、その地は「サンティアゴ・デ・コンポステーラ」、つまり「星の野原の聖ヤコブ」と呼ばれるようになり、墓の上には壮大な教会が建てられました。
聖ヤコブには、「サンティアゴ・マタモロス」(ムーア人殺しの聖ヤコブ)という物騒な異名が付けられています。カトリックがイスラム教徒(ムーア人)と死闘を繰り広げているときに、白馬にまたがった聖ヤコブが忽然と現れて勝利に導いたというのです。サンティアゴ・デ・コンポステーラは、イスラム教徒に対するレ・コンキスタの精神的な支えとなり、多くの巡礼者がこの地を訪れるようになりました。宗教改革までは、「聖遺物」に対する信仰が強かったこともあり、もっとも多かった頃には、年間50万人がこの地に巡礼したと言われています。
時は流れて1993年、この地に至るまでの巡礼の道(サンティアゴ・デ・コンポステーラへの道)が世界遺産に登録されると、再び巡礼ブームが沸き起こりました。この映画に登場してくるようなガイド付きの巡礼ツアーも行われるようになったのです。
「サン・ジャックの道」に登場する8人の巡礼参加者の中に、アラブ系の若者2人が含まれていること、さらに、ガイド自身がアラブ系というのが、この巡礼の道をめぐる歴史を振り返ってみると、何とも皮肉めいています。ただし、彼らはそれほど敬虔なムスリムでもないらしく、ムスリムの義務であるはずのメッカの方角を向いての1日5回の礼拝も、少なくとも映画では一度も描かれません。しかも、若者のうち1人は思いを寄せる女の子目当てという不純な動機だし、もう1人は、ホントかどうか定かではないけれど、「メッカへの巡礼」だと勘違いしている。
そういえば、この3人は別格としても、ほかの参加者だって、「あつい信仰心」から巡礼に参加しているとは思えない。母親の遺産を受け取る条件として嫌々参加した仲の悪い3きょうだいはもちろん、キャピキャピした女の子2人連れも、今ひとつ参加の動機がつかめない。もう1人、いつも頭をスカーフで覆っている中年女性は、何か秘密がありそうではありますが、それにしても「神に祈る」たぐいのシーンは一度も出てきません。
でも、言えるのは、全員がそれぞれに人生の「悩み」を抱えていて、それを何とかしたいとは思っているということ。3きょうだいの長男ピエールは、持病の心臓病を抱えている上に自殺願望の妻を持ち、真ん中のクララは失業中の夫と子どもを養うために教員として必死に働いている。末っ子のクロードはアル中でもう長いこと失業していて収入がなく、妻とは離婚、娘に金を無心するていたらく。アラブ系の若者は「失読症」で文字が読めないが、母親のためにも何とか字を覚えたいと思っている。
そういう、それぞれが抱える問題や悩みは、巡礼の途中、宿で見る「夢」として描かれていきます。リアルな夢、幻想的な夢。いろんな夢が出てきますが、いずれにしても「真実」につながっているところが興味深いところです。夢の中の光景と、登場人物の背景がつながっている。このあたりの描き方、コリーヌ・セロー監督はうまいなあとつくづく思う。
「巡礼の道」を取り上げながらも、この映画では、宗教についてというより、人間の生き方やコミュニケーションについて、鮮烈に描写されています。鮮烈と言えば、そうした人間模様の背景にある、美しい自然の風景も見逃せません。時にはやさしい光をたたえ、時には厳しい仕打ちを食らわす大自然が舞台になっているからこそ、人々は素直になれるし、自然に「変わって」もいける。巡礼の道というのは、もしかしたら「神への道」ではなく、人間が「自然」に抱かれるための手段なのかも、とさえ思う。
1,500kmもの道のりを、自分の足だけで踏破した者たちは、みんなそれぞれに「本来の自分」を取り戻して、元の場所に帰っていく。結ばれる人たちもいれば、離ればなれになる人もいる。新たに出会う人々もいる。ちょっとした「どんでん返し」もあったりもする。
自然のもとに「帰る」ことで、人間も人間関係も、確実に変わることができる。とてもほっとさせられる映画です。
『サン・ジャックへの道』≫Amazon.co.jp




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます