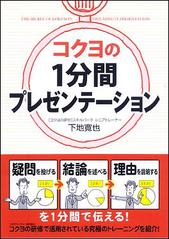
人前で話すのって皆さん得意ですか?
人前で話すの大好きって人は、あんまりいないかもしれませんね。私も、元教員でありながらナンですが、あんまり得意ではありません。好きか嫌いかと言ったら、好きに近いかもしれないけれど、決して得意ではない。
教員だから話しが上手、とは限りませんよね。教室で、子どもたちの前なら普通に話せるのに、大人の前だととたんに支離滅裂になってしまう人もいます。私も、高校教員から社会教育の世界に入って、大人の前で話しをしなければならなくなった時、子どもたちの前では感じたことのない緊張感に襲われたものです。その後、これまで立場上、何十回となく「まとまった話」をする機会がありましたが、よし!今日は満足に話せたぞー!ってことは、ただの一度もありませんです、ハイ。
で、『コクヨの1分間プレゼンテーション』。著者はコクヨファニチャー株式会社の[コクヨの研修]スキルパークでシニアトレーナーを務める下地寛也さん。この本、もっと早く読みたかった…。
言いたいことは「1分間あれば伝わる」というのがこの本のコンセプト。というか、プレゼンをする時には、「1分間」で伝えられるような準備をしなければならない、ということなんです。久しぶりに目からうろこがぼろぼろ落ちました。
1分間プレゼンテーションのシナリオは、基本的に次の3つで構成されます。
疑問(15秒) 「何だろう?」
↓
結論(10秒) 「へぇ~!」
↓
理由(35秒) 「なるほど!」
聞き手は、「疑問」の部分で興味を持ち、「結論」を聞いて驚き、「理由」で納得する。考えてみれば、単純な構成ですよね。でも、私たちは、人前で話すときに、この基本的な流れから逸脱して、あれもこれもとつい余計な情報を入れたがる。で、「まとまりのない話」になってしまうわけです。
もちろん、すべてのプレゼンを「1分間」でというわけにはいかない。でも、何分になろうが、この基本の流れは変わりません。たとえば、30分間のプレゼンなら、疑問(5分)→結論(5分)→理由(10分)として、残りの10分は質疑応答に当てるのだという。持ち時間が30分あっても、丸々話してはいけないのですね。この「質疑応答」が実は大切なのでしょう。そして、「例え時間が30分あったとしても、聴き手が覚えられるメインメッセージ(結論)は1つだけと心しておきましょう」…だって!!
伝えたいことが山ほどあるからといって、一方的にダラダラと話をしても、結局は伝えたいことが何一つ伝わらないというのはよくあることです。なるほど、「メインメッセージは1つ」と心しよう…。
さて、どんな持ち時間を与えられても、練習の段階では「1分間プレゼン」に特化して行うのがいいと言う。不要な言葉を削り、構成を練り直し、言葉を新たに選んでいく。そして、「1分間」に圧縮していく。このトレーニングを積むことによって、「取捨選択力」、「文章構成力」、「キーワード力」といったスキルが身に付いていく。これを「情報圧縮力」というのだそうです。なるほどなるほど! そうやって、本当に伝えたい情報を厳選していくのか。
さらに、「1分間プレゼンテーション」の練習は、ビデオに撮って「6回」行おうという点にも納得。なぜ「6回」なのか?
1回目…自分の声や話し方に戸惑う。
2回目…やっぱり無理と思う。
3回目…話している時の癖やミスに気づく。
4回目…いつもミスをする箇所に気づく。
5回目…ミスを改善してみる。
6回目…自分を客観的に見つめるもう一人の自分に気づく。
また、「聴き手全員を感動させることはできない」、だから「聴き手全員を感動させられなくてよい」という主張に、うろこ30枚くらい剥がれ落ちました。
「2:6:2の原則」というのだそうです。
聴き手が10人いれば、頭の回転が速い人が2人、普通の人が6人、遅い人が2人。
プレゼンの内容に関する予備知識が豊富にある人が2人、多少ある人が6人、まったくない人が2人。
好意的に考えてくれる人が2人、中立的に考える人が6人、懐疑的に考える人が2人。

これが「聴衆の割合」。だから、話が伝わるのは「8割」でいいのです。「8割の人」に伝えられたら、感動させられたらそれでいいのですね。そうだったのか~!ま、しかし、それもだいぶ大変なことではある。
この本から、まだまだ伝えたいことがたくさんありますので、続きはまた次回に。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます