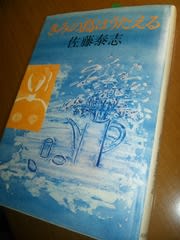
『海炭市叙景』が映画化されて再び脚光を浴びている佐藤泰志。
大学生の頃、ふと本屋で見つけて手にした彼のデビュー作『きみの鳥はうたえる』(1981年芥川賞候補作品)は、いろいろな意味でショッキングな小説だったことを今でも覚えています。当時読み始めていた村上春樹となんと対照的だったことか。同じ「僕」が語る物語なのに、どうしてこうも、こっちの「僕」とあっちの「僕」はチガっているのか!
実は、佐藤泰志を思い出したのは、先日の芥川賞受賞作の西村賢太の『苦役列車』を読んだからなのでした。ほぼ西村氏の体験に基づく、いわば「労働小説」です。主人公の貫多は、まだハタチそこそこながら、その日暮らしの荷役労働に身をやつす若者。金もない、友達もいない、もちろん彼女もいない。あちこちで家賃を踏み倒しながら生活している。珍しく気の置けない友が現れたかと思いきや、貫多の異常なふるまいに嫌気がさして離れていく。結局、また一人になる貫多。彼は、自分の「価値」は知っていたのかもしれませんが、いかんせん、その価値の使い道が分かっていない。あるいは、とことん「怠惰」な性格が、彼の「価値」を見えにくくしている。
西村氏自身が語っているように、これはいわゆる「破滅型」の私小説です。西村氏は、大正から昭和初期の私小説家、藤澤造という作家に傾倒していたそうですが、そこまで遡らなくとも、こういうタイプの作家なら佐藤泰志もそうではないかと思い出したのでした。ま、「破滅型」までいかないにしろ、「さわやか」とはおよそかけ離れた、汗だくの「青春小説」であることは間違いない。
本棚からすっかり色あせてしまった『きみの鳥はうたえる』を引っ張り出してきて読み返してみました。大学生の頃あんなに心が震えたはずなのに、読み返してみると、けっこう忘れていることに気が付く。村上春樹の小説は、細部に至るまで記憶しているというのに。思えば、村上春樹の世界は、いわば「憧れワールド」で、佐藤泰志のそれは、「こうはなりたくないワールド」だったのですね。だから覚えていないのかも。
でも、今読み返してみると、逆に新しい発見がたくさんあることにも気づかされました。本の主人公は、当たり前、あの頃と同じ年頃なのですが、こっちは歳月の分、年寄りになっているわけで、感じ方が違うのも当然ですけどね。今は、「こうはなりたくないワールド」でもないかなあと思ったりもするわけで。
『きみの鳥はうたえる』は、友人の静雄と二人で暮らしている「僕」が主人公。本屋で働いていて、同僚の佐知子とデキてしまうが、佐知子と静雄も仲良くなって。でも、「僕」は静雄も好きだから、別に嫉妬することもなく、二人を見守る。行きつけの飲み屋のマスターが恒例の静岡での海水浴に誘っても、「僕」は静雄と佐知子だけを行かせて一人で東京に残る。飲みに行っても、帰りは佐知子を真ん中にして、3人で一つの傘に入って通りを歩く。
実際、通行人はさかんに、ひとつ傘に入っている僕らを、うさんくさい、好奇心に満ちた眼で見た。幸福だった。少なくとも僕はそうだった。そのうち、佐知子のむこうに、彼女を通して新しく静雄を感じるだろう、という気持ちがした。
万事こんな感じで、「僕」はどこまでもとらえどころがない。でも、一人の友達もいない貫多に比べたら、まだこちらのほうが救いようがあります。勤め先の本屋の気に入らない同僚を路地で殴りつけたり、逆にその報復を受けたりと、いざこざもあるにせよ、「僕」は基本的に人を愛せるヤツ、なのです。だから、「事件」を起こした静雄のことも、本気で心配する。佐藤泰志の作品には、こういうタイプの男が多い。それはたぶん、彼自身の姿が反映されているのでしょうね。若い頃はあまり友達にしたくないタイプだったかもしれませんが、今なら友達になってもいいかなと思う。
佐藤泰志。芥川賞候補になること4度。一度も受賞しないまま、1990年10月10日、自死。
彼の生まれ故郷・函館を舞台とした短編集『海炭市叙景』は今読みかけですが、映画も見てから、改めて記したいと思います。
大学生の頃、ふと本屋で見つけて手にした彼のデビュー作『きみの鳥はうたえる』(1981年芥川賞候補作品)は、いろいろな意味でショッキングな小説だったことを今でも覚えています。当時読み始めていた村上春樹となんと対照的だったことか。同じ「僕」が語る物語なのに、どうしてこうも、こっちの「僕」とあっちの「僕」はチガっているのか!
実は、佐藤泰志を思い出したのは、先日の芥川賞受賞作の西村賢太の『苦役列車』を読んだからなのでした。ほぼ西村氏の体験に基づく、いわば「労働小説」です。主人公の貫多は、まだハタチそこそこながら、その日暮らしの荷役労働に身をやつす若者。金もない、友達もいない、もちろん彼女もいない。あちこちで家賃を踏み倒しながら生活している。珍しく気の置けない友が現れたかと思いきや、貫多の異常なふるまいに嫌気がさして離れていく。結局、また一人になる貫多。彼は、自分の「価値」は知っていたのかもしれませんが、いかんせん、その価値の使い道が分かっていない。あるいは、とことん「怠惰」な性格が、彼の「価値」を見えにくくしている。
西村氏自身が語っているように、これはいわゆる「破滅型」の私小説です。西村氏は、大正から昭和初期の私小説家、藤澤造という作家に傾倒していたそうですが、そこまで遡らなくとも、こういうタイプの作家なら佐藤泰志もそうではないかと思い出したのでした。ま、「破滅型」までいかないにしろ、「さわやか」とはおよそかけ離れた、汗だくの「青春小説」であることは間違いない。
本棚からすっかり色あせてしまった『きみの鳥はうたえる』を引っ張り出してきて読み返してみました。大学生の頃あんなに心が震えたはずなのに、読み返してみると、けっこう忘れていることに気が付く。村上春樹の小説は、細部に至るまで記憶しているというのに。思えば、村上春樹の世界は、いわば「憧れワールド」で、佐藤泰志のそれは、「こうはなりたくないワールド」だったのですね。だから覚えていないのかも。
でも、今読み返してみると、逆に新しい発見がたくさんあることにも気づかされました。本の主人公は、当たり前、あの頃と同じ年頃なのですが、こっちは歳月の分、年寄りになっているわけで、感じ方が違うのも当然ですけどね。今は、「こうはなりたくないワールド」でもないかなあと思ったりもするわけで。
『きみの鳥はうたえる』は、友人の静雄と二人で暮らしている「僕」が主人公。本屋で働いていて、同僚の佐知子とデキてしまうが、佐知子と静雄も仲良くなって。でも、「僕」は静雄も好きだから、別に嫉妬することもなく、二人を見守る。行きつけの飲み屋のマスターが恒例の静岡での海水浴に誘っても、「僕」は静雄と佐知子だけを行かせて一人で東京に残る。飲みに行っても、帰りは佐知子を真ん中にして、3人で一つの傘に入って通りを歩く。
実際、通行人はさかんに、ひとつ傘に入っている僕らを、うさんくさい、好奇心に満ちた眼で見た。幸福だった。少なくとも僕はそうだった。そのうち、佐知子のむこうに、彼女を通して新しく静雄を感じるだろう、という気持ちがした。
万事こんな感じで、「僕」はどこまでもとらえどころがない。でも、一人の友達もいない貫多に比べたら、まだこちらのほうが救いようがあります。勤め先の本屋の気に入らない同僚を路地で殴りつけたり、逆にその報復を受けたりと、いざこざもあるにせよ、「僕」は基本的に人を愛せるヤツ、なのです。だから、「事件」を起こした静雄のことも、本気で心配する。佐藤泰志の作品には、こういうタイプの男が多い。それはたぶん、彼自身の姿が反映されているのでしょうね。若い頃はあまり友達にしたくないタイプだったかもしれませんが、今なら友達になってもいいかなと思う。
佐藤泰志。芥川賞候補になること4度。一度も受賞しないまま、1990年10月10日、自死。
彼の生まれ故郷・函館を舞台とした短編集『海炭市叙景』は今読みかけですが、映画も見てから、改めて記したいと思います。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます