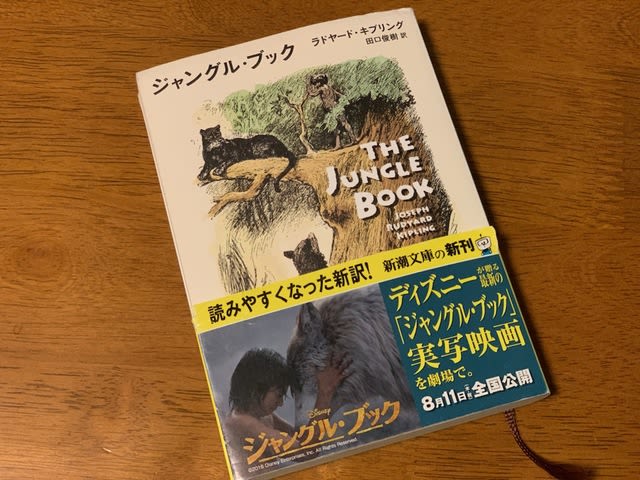
ラドヤード・キプリング著/田口俊樹訳/新潮文庫
今週はとても疲れてしまって、ブログを書く体力がない日が続いた。やっと体力的には復活してきたので、一生懸命キャッチアップしてみようと思う。
この本も、つんどくになっていた本で・・・なんで買ったかというと、確か100分de名著で、動物行動学の本をやっていた時に、言及された本だと思う。今回、意を決して読んでみたわけであるが、なんとも口あんぐりな描写が沢山あるのである。
私は今から38年前に、サブーというインド人少年(私の親族じゃありませんぜ)が主役モウグリを演じた実写版映画ジャングルブックをアメリカのテレビで見た覚えがあるが、この原作はその映画とは全然違う内容だ。
おそらくこの原作通りのジャングルブックはとても放映できないだろうと思う。作者のラドヤード・キプリングは1865年にイギリス統治下のインドに生まれ、そこで育った人だから仕方がないのかもしれないが、随所にイギリス人こそが善であり、土着のインド人を蔑む表現が見つかるからである。
オオカミに育てられたモウグリを家に招き入れ、息子として接した夫婦はインド人コミュニティから見れば魔女であり、すべてを奪われ、殺されそうになるところを、モウグリとオオカミたちによって救い出される。夫婦の避難先としてモウグリが示したのは、少し先にあるイギリス人集落。イギリス人は魔女狩りなんてしない・・というのがその理由。
で、夫婦をひどい目に遭わせたインド人集落に対してモウグリが行った制裁がひどいのだ。作物は食い荒らし、家畜を殺し、小屋を滅茶苦茶にして、貧しい村人たちを追い出し、集落をジャングルが飲み込んだ。直接人間を殺戮することは避けたとはいえ、貧しい人たちが食いつないでいくのに必要だったものをすべて壊したのである。それに対するモウグリに対する制裁はなし。鬼退治をした桃太郎よろしく、喝采で終わる。こんなことが書けるのは、作者がインド人ではなかったからであろう。
また、モウグリに敵対したシア・カーンという虎も、実に残忍な方法で踏み殺される。虎好きな私としては何とも耐えがたい。今やトラは貴重な動物なんだぞ。またドールというイヌ科の動物も、ジャングルの敵であるということで、蜂の大群の力を借りながら、こちらも実に残忍な方法で大量殺りくされる。ま、こっちはやらなければやられるという要素はあるのだが。
ドールって、昔、ズーラシアで見たことがある。

大雨で、ガラス越しだったから綺麗に写ってないのだが、見かけは狐みたいだ。イヌ科で、アカオオカミという別名を持つが、オオカミとは別種。ジャングルブックの訳の中では赤犬と称されているが、犬とオオカミが分岐するずっと前に分岐したものであるようだ。なんとなく性格はリカオンに近いのかなぁ。一度目をつけられたら、絶対逃げられないような、猛烈な持久力を持つ猛獣で、オオカミの群れよりも個体数の多い大群を作る。
見かけは結構キツネに似ている。当時、幽遊白書の蔵馬クンにハマっていた私は、キツネに対してはよい印象しかなく、したがってこのドールをみても、美しいとか可愛らしいとかしか思わなかったのだが、残忍な動物だったのか。
だが、いかに残忍とはいえ、動物同士の殺戮場面は、あまり気持ちのよいものではない。まぁ、これも生き延びるためと言えば仕方ないのだが。
ということで、本作は、ジャングルの自然の描写という意味では、元生物部の私をくすぐるものは十分あるのだが、殺戮の描写が残忍すぎ、インド人集落に対するステレオタイプな見方から、そのままお子様の目に触れさせるのはちょっと疑問符が付く作品ではある。
しかしこの本にまとめられたものは、ジャングルブックすべてではないのだ。ジャングルブックというのは全十五編あるが、モウグリ少年が登場する連作八編を選んで本にしたものだという。ひぇ~、まだあるんかい!
ということで、インド人少年サブーが演じた映画版ジャングルブックがいかに、うまいこと筋を変えて子供が見ても大丈夫な内容にしてあったか・・というのがよく分かった次第。
























