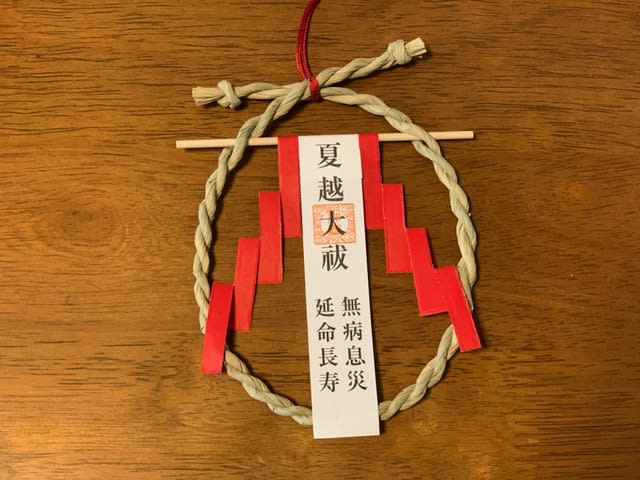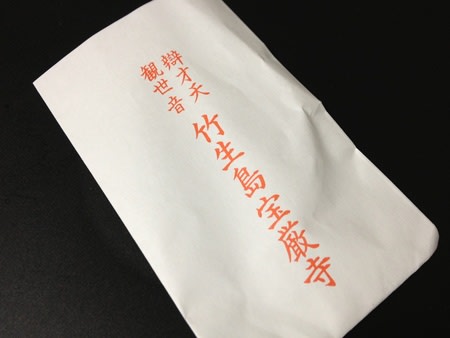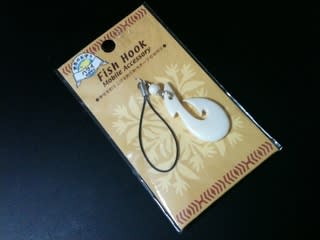ふっふっふ・・私は知る人ぞ知る数珠マニア。
今までこのブログでも
イスラム教の数珠とか
チベットの骨数珠とかを登場させたおり、数珠にまつわるウンチクを述べてきたが、世界三大宗教の数珠(ロザリオ)の原点は、インドのバラモン僧が使っていた数珠なのだ。
十二年前にトルコ旅行から帰ってきて以来、元祖ヒンドゥー教の数珠が欲しいというささやかなる野望を抱き続けていた。(何てくだらない野望だろう。)カンボジアに行った時、もしかしたらヒンドゥー教の数珠が手に入るかもしれないという淡い期待を抱いていたのだが、現地にはアンコールワットなどのようなヒンドゥー教の遺跡はあっても、現在信じられているのは仏教。しかも彼らの小乗仏教では通常数珠は使わないのだ(日本人向けのお土産の数珠はあったけどね)。

やはりインドに行かないとヒンドゥー教の数珠は手に入らないのだろうか。私が再びインドに行ける日はいつになることか・・・とほとんどあきらめていたのだが、先日ガンジーサンダルを買ったインドの通販サイトで、ガンジス川のほとりの都市バラナシでヒンドゥー教の巡礼者向けに売られているという菩提樹の実で作られた数珠を発見し、狂喜して買ってしまった。(これもお誕生日価格で。)
菩提樹の実って、何か胡桃みたいだな~。ちょっと興味を持って調べてみたら、菩提樹って意外に紛らわしいということがわかった。
私は以前インドに行った時、菩提樹の木を沢山見たが、葉っぱがハート形っぽいのがとても印象的だった。それはインドボダイジュと呼ばれるクワ科の植物で、この木の下でお釈迦様は悟りを開かれたのだ。
一方、「♪泉に沿(そ)いて 繁(しげ)る菩提樹~」で始まるシューベルトの歌曲「菩提樹」で歌われているのは、入浴剤クナイプの香りの一つにもなっているLindenbaumという木で、こちらも菩提樹と呼ばれるが、葉っぱがインドボダイジュに似ているだけで、シナノキ科の別の植物。
ところで、お釈迦様ゆかりのインドボダイジュの種は小さくて、とうてい数珠にできるような代物ではないそうだ。じゃぁ、インドで「菩提樹の数珠」として売られているものは何なのかというと、インドジュズノキとかジュズボダイジュとよばれるホルトノキ科の木の種子なのだそうだ。
まぁ、材料などどうでもよいではないか。こういうものは気持ちが大事。ガンジス川のほとりから運ばれてきたというこの数珠をありがたく手にとって繰ってみる。何て素朴な手触り・・・。珠の数が108つであることを確認した私の手の指は、数珠を染めた染料で、真っ赤に染まり上がっていた! さすがはインド!
さて、さらに解説を探してみると、ジュズボダイジュ(金剛菩提樹)は、インド名をルドラ-クシャといい、サンスクリット語で「ルドラ神(シバ神)の目」という意味だという。ヒンドゥー教でもシバ派は好んでルドラクシャの数珠を使うという。
彼らにとってルドラクシャはシバ神そのもの。ただ触れるだけでも罪は魔術のように洗われてしまうし、見ただけでもたいへんなご利益があり、不幸の兆しがある人からは、それが取り除かれるというありがた~いものだそうだ。
見ただけでもご利益あり・・・ということなんで、このブログを見た人はラッキーですね。

(ま、いじると指が赤くなるんで、見るだけでもいいというのは私にとってもありがたいことですね。)