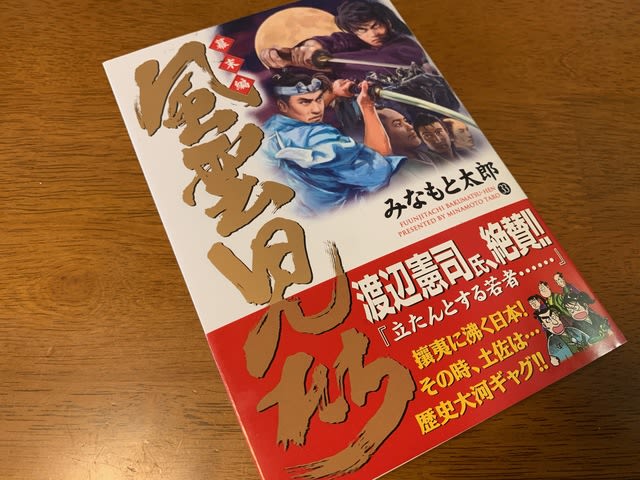
みなもと太郎/リイド社
本巻は結構難しくて、一度読んだ後、前巻の32巻から読み直した。
第32巻は生麦事件(1862年)の話であり、本巻では生麦事件の後から薩英戦争(1863年)前夜までを扱っている。
同時並行でいろんな話が進んでおり、多分すごく大事なところなので、作者も細かく書いているんだろうと思うが、この漫画が年に2回しか出ないので、ものすごく前のことのように感ずるのだが、実は同じ年のことを角度や立場を変えて書いているのである。
例えば1862年には、坂下門外の変というのが2月13日にあり(いや~ん、私の誕生日)それは本作の27巻に書かれており、それを私は3年4ヵ月前の2017年1月に読んでいる。坂下門外の変の翌月には家茂と和宮の婚礼が行われているが、公武合体と和宮の降嫁を推し進めてきた安藤信正は前月の坂下門外の変で襲撃されており、命を取り留めはしたものの、もう流れが変わってきてしまったのである。
同じ年の夏ごろには和宮降嫁を推し進めた人間達を「四奸二嬪」と称し、を排斥する運動が始まっている。四奸二嬪の一人とされた岩倉具視が坊主頭になって政界から身を引くわけで、大河ドラマ「西郷どん」に出てきた岩倉具視が最初坊主頭で登場するのは、この頃の話だったのかと合点が行った。
このように1862年というのはものすごく時代が速く動いている年であるのに、漫画的には3年4ヵ月かかっているわけで、私の体内感覚がついて来ないので、もう一度読み直してみたわけである。

ちなみに、去年私が読み直した山川の日本史では、1862年に関わる記述は1ページ程度しかない。これでは幕末を有機的に理解せよというのは難しいかもしれない。
1862年というのは、土佐では吉田東洋が暗殺され、暗殺の黒幕であった武市半平太が力を握っていた時期。暗殺の前日に脱藩していた坂本龍馬はあらぬ疑いをかけられることになる。また誰もが武市半平太を疑う中、証拠がつかめず、岩崎弥太郎と井上佐市郎が探索を命ぜられる。岩崎弥太郎は常人のほぼ倍の速度で江戸ー土佐間を駆けることが出来たという脚力の持ち主。かつ危険を察知してわざと井上と共に行動することをやめ、一方井上は武市側の岡田以蔵らに酒を飲まされ「おきゃく」にされた後、惨殺される。さすがは岩崎弥太郎の危機察知能力。そうでなければ財閥は作れん。
また「大獄の犠牲者は残らず尊皇の英雄である」と松平春嶽が主張したせいで、井伊家は完全に悪者にされてしまった。大獄の首謀者2名と2年前の桜田門外の変の警護不手際家臣全員を処罰して、藩に自浄作用があることをアピールしたがかなわず、藩主・井伊直憲の京都守護解任、蒲生・神崎二郡の領地十万石の領地召し上げ(つまり収入の3割カット)となった。長年徳川家を支えてきた井伊家の彦根藩はこの出来事をきっかけに(さらにその後も色々あるのであるが)、戊辰戦争において、新政府軍として参戦し、徳川の敵になるのであった。
その井伊家に代わって貧乏くじを引いたのは会津藩・・藩主松平容保の京都守護職拝命につながっている。京都守護職拝命に反対する西郷頼母・・・そういえば私が前の会社にいた時、一ヵ店目に東郷さんと西郷さんがいた。その西郷さんは薩摩の西郷さんじゃなくて、会津の西郷さんだった・・なんてことを懐かしく思い出したよ。
その他、私が不思議に思ったのは以下2点。
まずは、尊皇攘夷の急進派公家が学習院に集まり、天皇の勅を左右するほどの力を持っていたとのこと。え、学習院って、昔江戸川橋に住んでいた時、有楽町線の終電を逃し、よくJR目白駅から歩いて帰っていたが、あの時脇を通った懐かしの学習院かいな?と思って調べてみたが、京都の学習院はいったん廃止になり、明治10年に東京で設立された皇族・華族学校にあらためて「学習院」の名が冠されているから、連続性はないんだな。
それから、薩摩と長州と土佐・・・坂本龍馬の活躍前から、すでに連携して動いているではないか! もちろん仲良くしながら裏で主導権争いをていたわけだがね。
さて、時代は薩英戦争に向けて動いていく。通訳にあのシーボルト事件のシーボルトの息子、アレキサンダー・シーボルト君(当時16歳)が出て来る。それ以前の幕府側の通訳は、幕府に忖度した言い回しをしていたが、シーボルト君は忖度なんてしないから、生麦事件に対する英国の怒りをそのままストレートに訳してくる。幕府の要人たちが子供にののしられてあたふたする場面・・漫画的には面白かった。
先ほどの山川の日本史では「すでに薩摩藩は1863年に生麦事件の報復のため鹿児島湾に侵入してきたイギリス軍艦の砲火を浴びており(薩英戦争)、攘夷の不可能なことは明らかになった」としか書いてない薩英戦争。ずっと惨敗したのかと思っていたら、あらためてウェブサイト上で調べてみたら、実質引き分け(両軍とも損害が激しすぎて勝敗がはっきりしない)だったみたいですな。どうやらこの時も神風は吹いていたみたいで。。。薩英は戦争後急速に接近していくことになるのだが、子供の頃からどうもこのくだりはよくわかんなかったですな。子供だったから。おそらく風雲児たちの次巻もしくは次々巻あたりで薩英戦争が具体的に描かれると思うので、どのように描写されるか今から楽しみ。
























