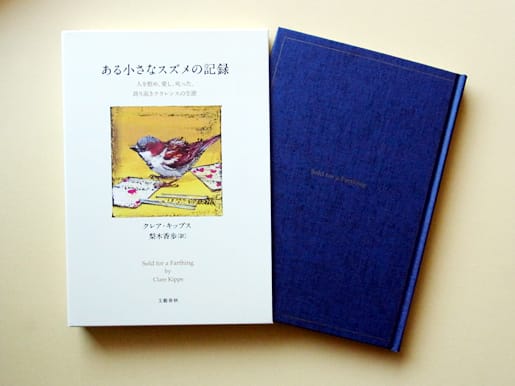ちょっとだけ鉄道が好きで、ちょっとした旅行程度ならたくさんしてみたいと思っている僕のような人間にとって、旅番組や旅系の本はいつも気になる。
そんな中、昨年4月に創刊された『鉄道ひとり旅ふたり旅』(エイ出版 933円+税)は、いや~待ってました!というムック本だった。
だったというのは、隔月間でトントントンと5号まで出て、あぁこういう本も売れる時代になったんだなぁと感心していたら、その5号巻末の「次号は2011年2月20日発売予定」という告知を最後に見かけなくなってしまったからだ。
何の断りもなく(HP上ではあったのかな)、休刊のようです。1周年目前だったのに。
ローカルあり、懐古あり、駅弁ありで、それでいてちゃんと今を伝えていて、ぼくら昭和世代にはたまらない素晴らしい本だったのになぁ。
昨年の12月で、僕の中の鉄道と旅は止まったままになっている。
行けなかった小田原アリーナは首位に勝利!