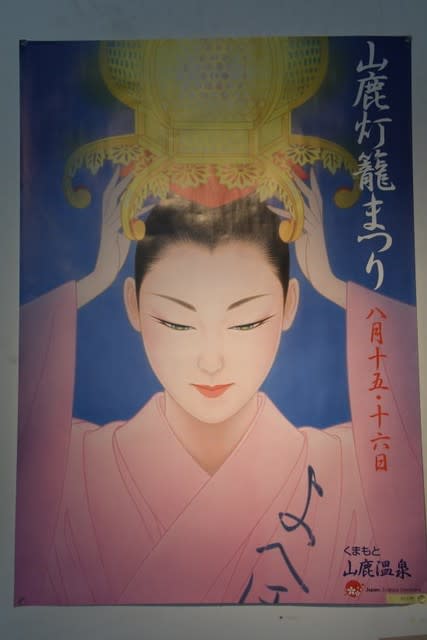久しぶりに、鞆の浦を訪ねました。滞在予定時間が2時間ほどしかなかったのでじっくり見て回る余裕はありませんでしたが、とりあえず定番の観光スポットを巡ることにしました。時刻は、午前10時ごろ、梅雨に入ったというのにこの日はカンカン照りの暑い一日でした。平日とあって駐車場はどこも「空」のマーク、港に近い中心部の駐車場に停めることができました。
(福禅寺対潮楼)駐車場から歩いて1分
最初に訪れたのが、「対潮楼」です。江戸時代に建立されたこの客殿からの眺めは特に有名で、朝鮮通信史が「日東第一形勝」と称したほどです。目の前には、弁天島、その向こうに仙酔島と形のよい島々が点々と浮かび、赤い毛氈が敷かれ開け放たれた広間から眺める瀬戸内の海は贅沢この上ありません。
お正月にかならず耳にする宮城道夫の筝曲「春の海」は、彼が失明する以前に見た父親の出身地この鞆の浦をイメージして作曲されたというのは有名な話です。曲を思い浮かべながら眺めてはいかがでしょう。境内には、赤と白のキョウチクトウが満開で、青い空とのコントラストはとてもさわやかに感じました。

対潮楼を道路側から見る

広間から見る鞆の浦

赤と白のキョウチクトウが満開でした。
(雁木と、TBSロケ地)駐車場から歩いて3分
次に向かったのが、鞆港です。江戸時代から残る雁木(がんぎ)と呼ばれる石段は鞆の浦の歴史に残る遺産です。しかし残念なことに北側の半分が修復工事中でした。9月にならないとあの完全な姿は見ることができません。ここでの新しい観光スポットが、テレビドラマのロケ地となった建物です。「流星ワゴン」というテレビドラマ、ご存知でしょうか。西島秀俊、香川照之、井川遥、吉岡秀隆が出演しました。最後の放送が、一昨年の3月でした。港の北側の建物がそうですが、鞆の浦のシーンではメインで使用されましたね。

江戸時代からの遺産 雁木(がんぎ)

ロケで使用された建物
(太田家住宅)
次に欠かせないのが、やはり太田家住宅です。以前の所有者は、江戸時代の中村家で「保命酒」を作っていました。玄関前の通りは、江戸、明治の風情が感じられる鞆の町並み一番の風情ある通りです。要所要所に置かれたプランターには花菖蒲が植えられ、さらに美しい町並みになっていました。ここでは他の団体さんに混じって説明を聞くことができました。広い土間には各地の焼き物で焼かれた保命酒の徳利などが展示されています。続いて案内されたのは、土蔵です。大きな甕や、巨大な木の棒には圧倒されます。部屋に戻ると、幕末の七卿落ちの面々が談義した部屋、そして床に掛かる絵は、江戸琳派・酒井抱一の軸と見所はたくさんあります。今回感心したのは、帳場から港が望め、入港した船が直に見えることでした。
さらに玄関から外に出て裏側の通りに回ってみると、めずらしい舟板塀を見ることができます。

太田家住宅 花しょうぶがとても町並みに合っていました

高窓をロープで上手に開ける

土蔵には備前焼の大きな甕が並ぶ

幕末の七卿落ちの面々が談義した大広間

裏の通りでは、舟板塀を見ることができる
(常夜灯)
鞆の浦を代表するスポットが、何といってもこの常夜灯ではないでしょうか?いろは丸展示館も同じエリアにあり、鞆の浦一番の撮影スポットとなっています。多くの観光客が写真を撮り合っていました。江戸時代後期に建てられたこの常夜灯、それにしても大きい建造物です。夜には灯かりが自動点灯するそうです。

鞆の浦一の撮影スポット

巨大な常夜灯
(医王寺)中心部から徒歩10分
鞆の浦に来たらかならず寄りたいのが、医王寺です。中心部から石畳の坂道を数百m.歩かなければなりませんが、ここから見る鞆の浦はまさに絶景なのです。私が一番の楽しみにしているのが、鐘楼前のベンチからの眺望です。この日は、暑い一日でしたが、ちょうど日陰になっており風が頬を撫で、何と気持ちのよいことか。他に人の姿はなく景色を占め状態でした。
さらに山道をここから数百段上ったところに、鞆の浦一の絶景ポイント太子殿があります。
前回登ったときもこの季節でしたが、蚊と格闘し息を切らしながら登った記憶があります。
まるで鞆の浦を俯瞰するようなロケーションです。

鐘楼前にはベンチがある

素晴らしい眺望、ここは欠かせない撮影ポイント

港に戻る 山の中腹に見えるのが医王寺
(SHION)ロケーション抜群のカフェ
少し歩き疲れ、休憩したいと思ったら、お勧めなのが市営の渡船場の2階にあるカフェ・SHIONはいかがでしょう。目の前が海で見下ろす感じがなんともいえません。特にカウンターに座れば、渡船(いろは丸)が眼下に見えます。そしてガラスの向こうにさえぎる物はなにもありません。ひとりだけでも十分気分に浸れます。
以上、2時間コースのお勧めポイントでした。

最後にお気に入りのカフェで一息いれる
(福禅寺対潮楼)駐車場から歩いて1分
最初に訪れたのが、「対潮楼」です。江戸時代に建立されたこの客殿からの眺めは特に有名で、朝鮮通信史が「日東第一形勝」と称したほどです。目の前には、弁天島、その向こうに仙酔島と形のよい島々が点々と浮かび、赤い毛氈が敷かれ開け放たれた広間から眺める瀬戸内の海は贅沢この上ありません。
お正月にかならず耳にする宮城道夫の筝曲「春の海」は、彼が失明する以前に見た父親の出身地この鞆の浦をイメージして作曲されたというのは有名な話です。曲を思い浮かべながら眺めてはいかがでしょう。境内には、赤と白のキョウチクトウが満開で、青い空とのコントラストはとてもさわやかに感じました。

対潮楼を道路側から見る

広間から見る鞆の浦

赤と白のキョウチクトウが満開でした。
(雁木と、TBSロケ地)駐車場から歩いて3分
次に向かったのが、鞆港です。江戸時代から残る雁木(がんぎ)と呼ばれる石段は鞆の浦の歴史に残る遺産です。しかし残念なことに北側の半分が修復工事中でした。9月にならないとあの完全な姿は見ることができません。ここでの新しい観光スポットが、テレビドラマのロケ地となった建物です。「流星ワゴン」というテレビドラマ、ご存知でしょうか。西島秀俊、香川照之、井川遥、吉岡秀隆が出演しました。最後の放送が、一昨年の3月でした。港の北側の建物がそうですが、鞆の浦のシーンではメインで使用されましたね。

江戸時代からの遺産 雁木(がんぎ)

ロケで使用された建物
(太田家住宅)
次に欠かせないのが、やはり太田家住宅です。以前の所有者は、江戸時代の中村家で「保命酒」を作っていました。玄関前の通りは、江戸、明治の風情が感じられる鞆の町並み一番の風情ある通りです。要所要所に置かれたプランターには花菖蒲が植えられ、さらに美しい町並みになっていました。ここでは他の団体さんに混じって説明を聞くことができました。広い土間には各地の焼き物で焼かれた保命酒の徳利などが展示されています。続いて案内されたのは、土蔵です。大きな甕や、巨大な木の棒には圧倒されます。部屋に戻ると、幕末の七卿落ちの面々が談義した部屋、そして床に掛かる絵は、江戸琳派・酒井抱一の軸と見所はたくさんあります。今回感心したのは、帳場から港が望め、入港した船が直に見えることでした。
さらに玄関から外に出て裏側の通りに回ってみると、めずらしい舟板塀を見ることができます。

太田家住宅 花しょうぶがとても町並みに合っていました

高窓をロープで上手に開ける

土蔵には備前焼の大きな甕が並ぶ

幕末の七卿落ちの面々が談義した大広間

裏の通りでは、舟板塀を見ることができる
(常夜灯)
鞆の浦を代表するスポットが、何といってもこの常夜灯ではないでしょうか?いろは丸展示館も同じエリアにあり、鞆の浦一番の撮影スポットとなっています。多くの観光客が写真を撮り合っていました。江戸時代後期に建てられたこの常夜灯、それにしても大きい建造物です。夜には灯かりが自動点灯するそうです。

鞆の浦一の撮影スポット

巨大な常夜灯
(医王寺)中心部から徒歩10分
鞆の浦に来たらかならず寄りたいのが、医王寺です。中心部から石畳の坂道を数百m.歩かなければなりませんが、ここから見る鞆の浦はまさに絶景なのです。私が一番の楽しみにしているのが、鐘楼前のベンチからの眺望です。この日は、暑い一日でしたが、ちょうど日陰になっており風が頬を撫で、何と気持ちのよいことか。他に人の姿はなく景色を占め状態でした。
さらに山道をここから数百段上ったところに、鞆の浦一の絶景ポイント太子殿があります。
前回登ったときもこの季節でしたが、蚊と格闘し息を切らしながら登った記憶があります。
まるで鞆の浦を俯瞰するようなロケーションです。

鐘楼前にはベンチがある

素晴らしい眺望、ここは欠かせない撮影ポイント

港に戻る 山の中腹に見えるのが医王寺
(SHION)ロケーション抜群のカフェ
少し歩き疲れ、休憩したいと思ったら、お勧めなのが市営の渡船場の2階にあるカフェ・SHIONはいかがでしょう。目の前が海で見下ろす感じがなんともいえません。特にカウンターに座れば、渡船(いろは丸)が眼下に見えます。そしてガラスの向こうにさえぎる物はなにもありません。ひとりだけでも十分気分に浸れます。
以上、2時間コースのお勧めポイントでした。

最後にお気に入りのカフェで一息いれる