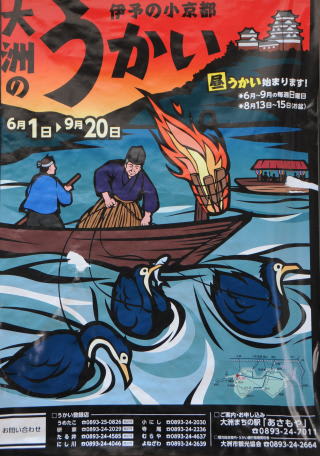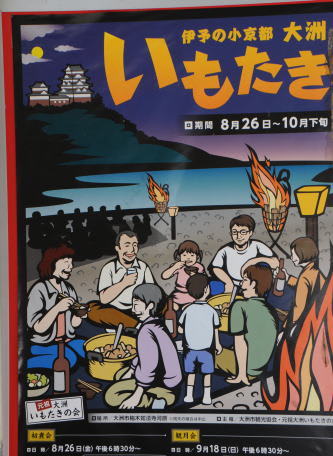川野屋醤油醸造場はどこか郷愁を感じさせる風情があります。
庭瀬往来を歩いていると、民家の向こうにあの羽釜うどんの幟が見えました。お昼はいっぱいだった駐車場も、この時刻にはもう空いているだろうと、県道につながる路地を進むと、なんだか懐かしい感じの屋根が波打つ川野屋醤油醸造場と書かれた古い建物がありました。横目に見ながら県道に出ると、タヌキが羽釜に入り、頭に木の蓋を乗せたとても大きな愛らしいキャラクターが見えます。駐車場は、予想通り空いていました。羽釜うどんの幟が目立ったため、店名はよく見ていませんでしたが、改めて見ると「あなぶき家」とありました。
このお店は、店名でもわかるように、あなぶき興産グループの穴吹エンタープライズ株式会社が昨年の5月に、岡山県で初めてオープンさせた、讃岐うどんのセルフ店です。名物は、カルシウムの入った特製の麺。店内の特性羽釜を使って茹で上げています。コシはあの丸亀製麺より少し柔らかめで弾力があります。お値段もセルフならではの低料金、味もなかなかのものでした。
こうしてお腹を満たし、陣屋町の町並み散策再開です。再び庭瀬往来に戻って東に進むと、前方の町並みのそれらしい雰囲気がだんだんとなくなり、この辺で終わりかなと、南方面の路地に目をやると、木製の大きな常夜灯が目に入り、そちらに進むことに。常夜灯あたり一帯は広く整備されていて比較的大きな水路もありました。案内板には、旧庭瀬港とありました。規模は当時のものと比較しかなり小さいもののようでしたが、近年、常夜灯と旧庭瀬港が復元されたということのようです。
ふと、背後に目をやると、立派な格式のある民家もありました。この辺で、本日の撫川・庭瀬散策を終了しようと、車を停めている庭瀬城址に戻ることにしました。途中で見る水路の多さとお寺の多さに感心しながら適当に路地を歩いていると、なんと方角を見失ってしまいました。これは困ったなと思っていると、遠くにある道標が目に留まりました。随分、東に来ていたようです。
庭瀬城址公園に戻り、次に向かったのが、吉備津神社です。ナビのまま進むと、信じられないような山道に入っていきました。途中で引き返そうと思いましたが、方向転換もままならず、覚悟を決めて前進あるのみで、急な山道を進むとなんとか山を越え、吉備津神社付近に出ることができました。
吉備津神社、急な石段を登ると山門があり、国宝の本殿が見えてきます。近年改修が行われ、屋根がとても美しいのです。少ない梅は見ごろを過ぎており、被写体も他にはなくお気に入りの長い回廊を歩いて行くと、正面の行き止まりに、愛らしいネコが一匹いました。写真を撮ろうと近寄ると、のっそりのっそりと、足の下にやって来て坐り、リラックスしている様子。なんと人懐こいネコでしょう。人をまったく怖がる様子もありません。
こうして、本日の撮影を終了し、家路に着くことにしました。
撫川・庭瀬の見どころとしては、他に犬養木堂記念館があります。このことはあとで気づきました。庭園もあるようなので、次回の楽しみとしておきましょう。
撫川・庭瀬地区のように、国の重要伝統的建造物保存地区の指定を受けるほどでもなく小さな昔の情景を留めている町並みが、県内にまだまだあるようです。今後はそういうところを少しずつ訪ねて行きたいと思っています。
次回は、3月3日の香川県梅の名所巡りのお話です。

吉備津神社 回廊で見た人懐こいネコ