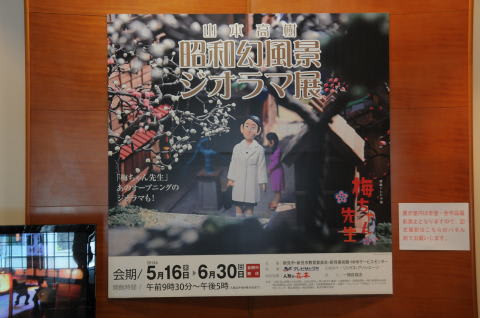大和文化館 とてもシンプルな外観です。
華鶺大塚(はなとりおおつか)美術館友の会の観賞旅行で久しぶりに奈良を訪ねました。今回の行き先は、奈良市学園町の大和文華館と唐招提寺、最後に赤膚焼きの窯元を訪ねる予定です。個人的には、先週の京都に続くバス旅行になります。井原を朝7時に出発して、大和文華館に着いたのが、予定よりも少し早い11時前ごろでした。駐車場からは美術館の建物はまったく見えません。駐車場の横にあるレトロな建物が気になりましたが、こちらは奈良ホテルのラウンジの一部を移築したものだそうです。受付からゆるやかにカーブしたスロープ状の道を100mほど歩いて行くと、白壁の土蔵のような美術館の建物が見えてきました。とてもシンプルな外観です。玄関先にササユリの鉢植えがひとつあり、とても清楚で気に入りました。
玄関を入ると、右側にミュージアムショップが見えました。私たちは学芸員さんのお話を聞くため、講堂(ホール)に案内されました。とても斬新で立派な施設です。その中の話で、特に印象に残っているのは、私立の美術館としてはめずらしく、美術品を所有しているので美術館を造るのではなく、美術館を造るという目的で、美術品を収集したというところです。発案したのは、近畿日本鉄道の当時の社長でした。そして作品の収集等に14年を要し、昭和35年に開館しました。美術品を鑑賞する場所にふさわしいということで、この地を選んだのだそうです。住宅地の一角にありますが、池(菅原池)に面した丘陵地でとても静かなところです。
この美術館は、国宝4点、重要文化財31点を含む2000点以上の美術品を所有しています。ホールから展示室に会場を移し、主だったものの説明をいただきました。展示室は、ワンフロア―で中心部に竹が植栽され自然光が取り入れられる坪庭的スペースがあるとても珍しい作りになっています。展示ですが、「中国陶磁の広がり」と題した特別企画展が、開催されていました。世界の陶磁器に大きな影響を与えた中国陶磁の魅力と、その影響を受けた日本やヨーロッパの作品、88点が紹介されています。私が一番気に入ったのが、南宋・建窯で焼かれた「油滴天目茶碗」でした。小振りなお碗に、びっしりと油滴のように見える文様がくっきり。実に美しいものでした。ひととおり美術品を鑑賞したあと、建物の周辺を散策することにしました。遊歩道が整備され、沿道に季節の花を見ることできます。
アザミの紫色の花や、ザクロのオレンジ色の花は見られましたが、残念ながら丘陵の斜面に生えているササユリは、わずか一輪だけを残し、ほとんど終わっていました。池に面した遊歩道では、アジサイが咲き始めていました。こうしてゆっくり時間を過ごして大和文華館をあとにしました。バスは、本日の昼食場所「花鹿」に向かいます。そして昼食後は、いよいよ唐招提寺です。(つづく)

タニウツギが咲いていました。