事案:
貸金返還請求訴訟の被告であるXは、弁護士Aを訴訟代理人として選任し、その委任状には、特別権限事項の和解権限も含まれていた。
Aは、Xが和解について明確に拒否しているにも関わらず、抵当権設定を内容とする和解をした。
問題となる条文:
民事訴訟法55条2項2号
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
いかなる条文の解釈適用が問題か:
「和解」の文言の解釈の問題
自分と反対の考え方:
和解の代理権は訴訟物の範囲に限定されるとする見解。
上記考え方の問題点:
包括委任の趣旨は、訴訟代理人となる弁護士資格への信頼を基礎として、包括的な代理権を弁護士に与え、手続の明確性・円滑性を担保するところにある。
上記見解の場合、訴訟代理人の権限は、争われている訴訟関係だけに限定されてしまい、たとえ、訴訟代理人が、多角的な分析のもと、経験と専門知識を持って、本人に最も適切な解決策を見いだしたとしても実行できなくなってしまうおそれがある。
特に和解では、互譲を前提とするが、その際は、相手方の提案が、訴訟物の範囲外にまで及ぶことがある。
代理権限が訴訟物の範囲に限定されると、相手方の提案に臨機応変に対応することが難しくなり、和解の成立が限定されるし、時間も要することとなり、結局、本人に不利に働くこととなる。
自分の考え方:
訴訟代理人の和解の代理権は、訴訟物に限定されず一定の範囲に及び、実体法上の代理権もその範囲に拡張されると解すべきである。
従って、本件では、Xが和解を拒否していたとしても、特別権限事項で和解権限も訴訟代理人の委任の範囲に含まれている以上、Aのした和解は有効であるし、返済確保のため抵当権を設定した行為自体も和解の代理権の範囲内の行為として一般的かつ合理的である。
以上
最判昭和38年2月21日民集17巻1号182頁(主要判例168、百選4-19)
貸金返還請求訴訟の被告であるXは、弁護士Aを訴訟代理人として選任し、その委任状には、特別権限事項の和解権限も含まれていた。
Aは、Xが和解について明確に拒否しているにも関わらず、抵当権設定を内容とする和解をした。
問題となる条文:
民事訴訟法55条2項2号
(訴訟代理権の範囲)
第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 反訴の提起
二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
五 代理人の選任
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
いかなる条文の解釈適用が問題か:
「和解」の文言の解釈の問題
自分と反対の考え方:
和解の代理権は訴訟物の範囲に限定されるとする見解。
上記考え方の問題点:
包括委任の趣旨は、訴訟代理人となる弁護士資格への信頼を基礎として、包括的な代理権を弁護士に与え、手続の明確性・円滑性を担保するところにある。
上記見解の場合、訴訟代理人の権限は、争われている訴訟関係だけに限定されてしまい、たとえ、訴訟代理人が、多角的な分析のもと、経験と専門知識を持って、本人に最も適切な解決策を見いだしたとしても実行できなくなってしまうおそれがある。
特に和解では、互譲を前提とするが、その際は、相手方の提案が、訴訟物の範囲外にまで及ぶことがある。
代理権限が訴訟物の範囲に限定されると、相手方の提案に臨機応変に対応することが難しくなり、和解の成立が限定されるし、時間も要することとなり、結局、本人に不利に働くこととなる。
自分の考え方:
訴訟代理人の和解の代理権は、訴訟物に限定されず一定の範囲に及び、実体法上の代理権もその範囲に拡張されると解すべきである。
従って、本件では、Xが和解を拒否していたとしても、特別権限事項で和解権限も訴訟代理人の委任の範囲に含まれている以上、Aのした和解は有効であるし、返済確保のため抵当権を設定した行為自体も和解の代理権の範囲内の行為として一般的かつ合理的である。
以上
最判昭和38年2月21日民集17巻1号182頁(主要判例168、百選4-19)

















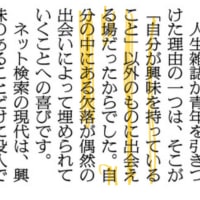








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます