年金制度の北極星は「払った分だけもらう」である。どんな少子化にあっても、子供のない人には年金を出さないことにすれば、これは貫徹できる。あとは、何を、保険料外、すなわち、税によって、もらえるようにするかを決めることになる。子供のない人でも、もらえるようにするのか、低所得で十分に保険料を払えなかった人をどうするのかなどが論点である。
北極星を知らずに、世代間の格差がどうの、主婦やパートの損得がどうのと議論しても、意味がない。今の日本は、意味がないことを悟るまでの長い勉強の過程にある。年金改革論は、積立方式への転換、税方式への転換と、無益な抜本改革の議論を繰り返し、結局、そこに出口がないことが分かったところである。(未だに分かってない有識者もいるが)
世代間格差論も、専業主婦ズルイ論も、出口はない。むろん、専門家は分かっているが、国民というか、一般有識者や新聞がこれを悟るまで、無益な議論を続けるしかない。勉強のためのコストを払い続けているのだ。そうして、真に改めるべき少子化を放置して、取り返しのつかない事態に至る。これが日本の運命である。
どうすれば良いかについては、「小論」や基本内容の「雪白の翼」で書いてきたが、これを読んでも、論理が分からない人もいるだろうし、感情的に反発して最初から受け付けない人もいるだろう。論理を突き詰めれば、そこに至るしかないけれども、常識を超えることを、多くの人が消化していくのには時間がかかる。
今日の日経が「ジレンマの年金改革」として取り上げている支給開始年齢の引き上げについて、北極星からは、どう見えるのか。結論は、払った分ももらえなくなるほど引き上げるわけにもいかないし、払った分以上にもらえるほど早くの支給もできないということである。そして、開始年齢は、給付月額を変えることで調整することが可能だ。
この問題の解決方法は極めて簡単である。支給開始年齢は固定して、寿命が延びるなどして払った分以上の給付になる場合は、徐々に給付月額を減らしていけば良い。給付月額が減るのが嫌な人は、自分で遅らせることを選択できるようにする。開始をいつにするかは、制度でなく、保険数理に従った給付額を見ながら、受給者が決めるべきなのだ。
本当は、日本の年金制度は賦課方式なので、寿命が延びた場合には、保険料率を上げ、給付月額も減らさないのがベストである。現役の負担が増すように見えるかも知れないが、子供のない人には年金を出さないことにさえすれば、将来、払った分以上の給付が返ってくる。必ず「得」になるのであって、これが賦課方式の最大のメリットでもある。
現実的な改革の方法を示せば、支給開始年齢を引き上げるより、マクロ経済スライドを長く行って、給付月額を下げ、それを嫌う人は、遅くからの給付開始を呼びかけるものだろう。そうすれば、負担の軽減そのものはできるし、支給開始が一律に遅くなって困る人を作らないことにもなる。
まあ、専門家に言わせれば、最初から結論は見えているのだが、紆余曲折を経て、そこに到達するまで、「年金をもらえるまでの空白期間ができる」という無用な不安を国民に振りまきつつ、一般有識者と新聞のお勉強の時間を作るということなのだろう。
昨日、日経が「ジレンマ」で取り上げたパートへの厚生年金の適用拡大にしても、新たな適用者には、低額の保険料を設けて負担を軽減する一方、給付は国庫負担分に加えて低保険料に応じた分しか払わないとするのが基本である。あとは、特例措置で、給付の低下などの問題を補っていくことになる。
年金にとって最も深刻な問題は、今日もところどころで触れているように、少子化である。負担と給付の公平は、子供のない人に年金を出さないことで実現できるにしても、少子化の行き着く先は絶滅であるから、制度の持続どころか、日本の存続することすら危うい。それを悟るのは、もう手遅れとなる人口崩壊が始まり、恐怖を感じてからのことだろう。そうなるまで、日本のリーダーたちのお勉強は続くのだ。
(今日の日経)
G20ファンド監視強化。タイ工場洪水被害広がる。三次補正12.1兆円で決着、公明の増額要望1000億円反映。消費増税の幅と時期示す・政調会長。復興増税15~20年論。再生支援機構の受け付け終了。ジレンマの年金改革・現役負担で世代格差対策。EU補助率上げ・インフラ・雇用事業。インドのインフレ高止まり。セブン伊藤園の隠れPB。銅の過熱感薄らぐ、新興国需要は堅調。
※小政党の役割に見合った良い動きではないか。※やはり機構はうまく働かなかったね。※EUもすべきことが分かってきたようだ。※シムズ先生の言うように、引き締めは、なかなか効かないな。中国もまだだよ。
北極星を知らずに、世代間の格差がどうの、主婦やパートの損得がどうのと議論しても、意味がない。今の日本は、意味がないことを悟るまでの長い勉強の過程にある。年金改革論は、積立方式への転換、税方式への転換と、無益な抜本改革の議論を繰り返し、結局、そこに出口がないことが分かったところである。(未だに分かってない有識者もいるが)
世代間格差論も、専業主婦ズルイ論も、出口はない。むろん、専門家は分かっているが、国民というか、一般有識者や新聞がこれを悟るまで、無益な議論を続けるしかない。勉強のためのコストを払い続けているのだ。そうして、真に改めるべき少子化を放置して、取り返しのつかない事態に至る。これが日本の運命である。
どうすれば良いかについては、「小論」や基本内容の「雪白の翼」で書いてきたが、これを読んでも、論理が分からない人もいるだろうし、感情的に反発して最初から受け付けない人もいるだろう。論理を突き詰めれば、そこに至るしかないけれども、常識を超えることを、多くの人が消化していくのには時間がかかる。
今日の日経が「ジレンマの年金改革」として取り上げている支給開始年齢の引き上げについて、北極星からは、どう見えるのか。結論は、払った分ももらえなくなるほど引き上げるわけにもいかないし、払った分以上にもらえるほど早くの支給もできないということである。そして、開始年齢は、給付月額を変えることで調整することが可能だ。
この問題の解決方法は極めて簡単である。支給開始年齢は固定して、寿命が延びるなどして払った分以上の給付になる場合は、徐々に給付月額を減らしていけば良い。給付月額が減るのが嫌な人は、自分で遅らせることを選択できるようにする。開始をいつにするかは、制度でなく、保険数理に従った給付額を見ながら、受給者が決めるべきなのだ。
本当は、日本の年金制度は賦課方式なので、寿命が延びた場合には、保険料率を上げ、給付月額も減らさないのがベストである。現役の負担が増すように見えるかも知れないが、子供のない人には年金を出さないことにさえすれば、将来、払った分以上の給付が返ってくる。必ず「得」になるのであって、これが賦課方式の最大のメリットでもある。
現実的な改革の方法を示せば、支給開始年齢を引き上げるより、マクロ経済スライドを長く行って、給付月額を下げ、それを嫌う人は、遅くからの給付開始を呼びかけるものだろう。そうすれば、負担の軽減そのものはできるし、支給開始が一律に遅くなって困る人を作らないことにもなる。
まあ、専門家に言わせれば、最初から結論は見えているのだが、紆余曲折を経て、そこに到達するまで、「年金をもらえるまでの空白期間ができる」という無用な不安を国民に振りまきつつ、一般有識者と新聞のお勉強の時間を作るということなのだろう。
昨日、日経が「ジレンマ」で取り上げたパートへの厚生年金の適用拡大にしても、新たな適用者には、低額の保険料を設けて負担を軽減する一方、給付は国庫負担分に加えて低保険料に応じた分しか払わないとするのが基本である。あとは、特例措置で、給付の低下などの問題を補っていくことになる。
年金にとって最も深刻な問題は、今日もところどころで触れているように、少子化である。負担と給付の公平は、子供のない人に年金を出さないことで実現できるにしても、少子化の行き着く先は絶滅であるから、制度の持続どころか、日本の存続することすら危うい。それを悟るのは、もう手遅れとなる人口崩壊が始まり、恐怖を感じてからのことだろう。そうなるまで、日本のリーダーたちのお勉強は続くのだ。
(今日の日経)
G20ファンド監視強化。タイ工場洪水被害広がる。三次補正12.1兆円で決着、公明の増額要望1000億円反映。消費増税の幅と時期示す・政調会長。復興増税15~20年論。再生支援機構の受け付け終了。ジレンマの年金改革・現役負担で世代格差対策。EU補助率上げ・インフラ・雇用事業。インドのインフレ高止まり。セブン伊藤園の隠れPB。銅の過熱感薄らぐ、新興国需要は堅調。
※小政党の役割に見合った良い動きではないか。※やはり機構はうまく働かなかったね。※EUもすべきことが分かってきたようだ。※シムズ先生の言うように、引き締めは、なかなか効かないな。中国もまだだよ。


















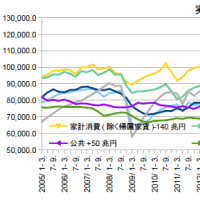
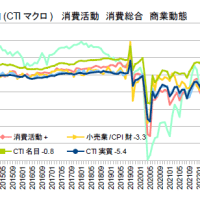





>「むろん、専門家は分かっているが、国民というか、一般有識者や新聞がこれを悟るまで、無益な議論を続けるしかない。勉強のためのコストを払い続けているのだ。そうして、真に改めるべき少子化を放置して、取り返しのつかない事態に至る。これが日本の運命である。」
・・・そうした議論がマスコミで長く続くほど、国民の将来への不安は高まりますから、老後に備えるための貯蓄志向が強くなり、消費性向の低下で、日本の成長は設備投資依存度が高くなりますね。しかし、設備投資で増えた生産能力に対して国内の消費は低いわけで(消費性向が低いわけですから)、自然と外需依存度も高まるということになる・・・というのが過去四半世紀の日本だったようにも思います(・・・もっとも、もう、所得の伸び悩みや高齢化で貯蓄性向は低下してしまいましたが)。
そもそも、20~30年くらい前から、年金や社会保障費用の問題が世上を賑わしてきましたから・・・。多分、それは日本経済の内需不足に継続的に寄与してきたと思います。
こうした問題が大きな脚光をあびてきた背景としては厚生省(厚労省)や大蔵省(財務省)が背後で係わっていたと思います。年金の将来に問題があることはわかっていた官僚達は、その問題に対応するために、マスコミや政界を通じて国民に、問題を認識してもらおうとします。
そこで問題なのは、日本のエリート官僚がゼネラリストであることです。ゼネラリストが能力を示すのは2つの場面です。一つは、複数の専門家の意見をうまく「調整し取りまとめる場面」。もう一つは「政策を実現する場面」です。特に日本で重要なのは後者です。
後者を実現するために、官僚には、利害が対立する他省庁の抵抗を封じ、国会を通すために政治家をうまく動かし、(そのためにも)マスコミをうまく動かす能力が求められます。実際のところ、ゼネラリスト官僚は特にこの後者の能力で評価されます。
・・・欧米のように官僚が専門家である場合には、専門的に妥当な政策案を策定する能力が重視され、また、それを専門的に評価できる能力が求められます。となると、かれらの議論は、その政策案の妥当性に関する専門的な議論が中心になります。
しかし、日本のゼネラリスト官僚は専門的な能力が弱いので、その政策が妥当かどうかというよりも、自府省が策定した政策(それがどんなものであれ)をうまく通す能力、つまり「ワル野ワル彦」的な能力が高く評価されることになるわけです。
そのために、特に問題が大きい場合には、官僚は当然、国民に理解してもらうことを重視します。このためには、マスコミを操作して、国民や政治家の間に「世論」(空気)を作る必要があるということになります。
この場合の目標は、解決策となる政策が実施されなかったら大変なことになるという雰囲気・印象を国民に持ってもらうことです。このために、相対的には過度に悲観的な見通しが流されることになります。
国民、マスコミ、政治家が悲観的な状況認識をすればするほど、思ったよりも軽い負担で済む落としどころ案が受け入れやすいことになるわけですから。
ということで、官僚の情報操作では、常に悲観的な将来予測が流されることになります。
そして、こうした情報操作に協力してもらうために、官僚は、日頃から、マスコミ、政治家、学者さんたちとうまくつきあう能力が求められるわけです。組織的にやっている府省もあります。つきあうための原資は、基本的には府省が持っている様々な情報です。
また、学界で言えば、審議会委員などで協力的な学者さんを見つけ、つながりをつくります。その学者さんの世論への影響力を強めるために、折に触れてマスコミへの紹介など売り込んであげたりもします(こうなるともう運命共同体ですね)。
また例えば財務省の財務総合政策研究所には、財政学や公共経済学などの若手の気鋭の学者さん達(准教授クラス)を短期間、特別研究官に任命する仕組みがあります。これは、一種の登竜門的な役割を果たしているように思います。こうした場を通じて、自省の政策について理解をしてもらっていくわけです・・・。