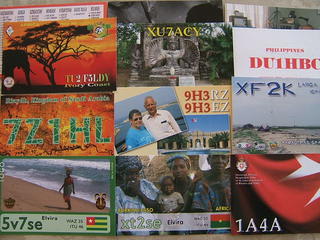“埼玉青なす”実際はもっときれいな薄緑で見るからに美味しそうなのだが、調理台上で外光・蛍光灯・裸電球とカクテル光源の撮影は失敗作の見本。特に食べ物は十分な照明も施してきれいに撮らなければならないが、カメラの高性能が仇になり照度不足などでも容易に撮れるのでつい手抜き、何時も後悔してしまう。
この“青なす”1本だけ試験的に植えてみたが、粒が大きいだけに多くは採れずこれで13個三回目の収穫。米なすとは比較にならないほど果肉が実に滑らかで軟らかくて上品な味と食感はこれがなす?と疑ってしまうほど。材料はこの他にワイン・オリーブオイル・バター・塩・胡椒・月桂樹の葉・パルメランチーズを使って

昨日リクエストに答えて、教室で習った“茄子のポロネーズ”を青なすで再び作った。ソースを完成させてからオリーブオイルでなすを焼き、塩、胡椒してソースを加えて10分ほど煮込んで完成。この“青なす”大変軟らかくて前回輪切りにして一部煮崩れしてしまったので、今回は縦割りでしかも弱火で慎重に煮あげたが、盛り付けた時の見栄えは輪切りの方に軍配。

ソースを多く作って置いたので、今日は更にベーコンの厚切りを細切りにして炒めてそのソースを加えて更に煮込んで味を調えてパスタのソースにした。一品加える事で味も変身「連日同じ?」なんて文句は言わせない、実は手抜きの一工夫。