タナカの読書メモです。
一冊たちブログ
虹をつかむ男
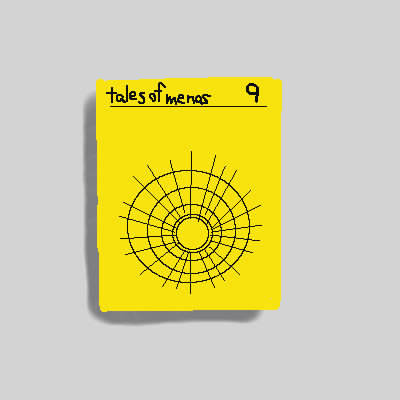
「虹をつかむ男」(サーバー 早川書房 1962)
訳は、鳴海四郎。
異色作家短編集、第9巻。
異色作家短編集は、3度装丁が改められたはず。
おおざっぱにいって、最初が黄色で次が黒、その次がピンクだったかと思う。
で、最初だけ箱入りだった気がする。
今回手元にあったのは、たまたま最初の黄色本。
表紙には、放射状に広がる線に、大きくなっていく円があしらわれている。
真似してみたけれど、こういうきっちりした図案がいちばん真似しにいくことを再確認。
本書は、ユーモア作家兼漫画家として名高い、ジェームズ・サーバーの短編集。
もっとも、映画「虹をつかむ男」の原作者としてのほうが有名かも。
収録作は以下。
「序文」
「虹をつかむ男」
「世界最大の英雄」
「空の歩道」
「カフスボタンの謎」
「ブルール氏異聞」
「マクベス殺人事件」
「大衝突」
「142列車の女」
「ツグミの巣ごもり」
「妻を処分する男」
「クイズあそび」
「ビドウェル氏の私生活」
「愛犬物語」
「機械に弱い男」
「決闘」
「人間の入る箱」
「寝台さわぎ」
「ダム決壊の日」
「オバケの出た日」
「虫のしらせ」
「決別」
「ホテル・メトロポール午前二時」
「一種の天才」
「本箱の上の女性」
訳者あとがきで、鳴海四郎さんが内容について簡単なジャンル分けをしている。
便利なので引用しよう。
まず、「虹をつかむ男」にはじまる16篇が小説風のもの。
「寝台さわぎ」にはじまる6篇が回想風のもの。
「ホテル・メトロポール午前二時」と「一種の天才」が犯罪実話もの。
最後の「本箱の上の女性」は、作者の漫画と、自作漫画についてのエセー。
さらに、小説はこんな風に分けられる。
「夫婦離反もの」
「白昼夢もの」
「機械嫌悪もの」
「愛犬もの」などなど。
いろいろあるけれど、面白かったのはやっぱり小説(でも、思い出そうとすると回想ものが思い出される。なぜだろう)。
なかでも面白かったのは以下。
「虹をつかむ男」
妻に頭が上がらない、ウォルター・ミティ。
妻が美容院にいっているあいだに買い物をしながら、さまざまに白昼夢にふける。
ウォルター・ミティは、「なにを見てもなにか思い出す」式に、隙あらば、強く劇的な自分を妄想する。
8発海軍飛行艇を指揮する、暴風雨をものともしない中佐、百万長者の銀行家を手術する医者、検事にパンチを食らわす被告人、爆撃機乗りの大尉…。
ミティの戯画化された妄想と、だれからも軽くあつかわれる情けない生活の対比が、短い分量のなかで見事に表現されている。
それに、ミティはちゃんと機械にも弱く、車の運転も下手。
正にサーバー的主人公。
映画化されたことを除いても、サーバーの代表作だろう。
「空の歩道」
小さなころから、相手がいおうとしていることを先回りして口走るくせのあったドロシー。
成長したドロシーは、男のことばづかいを細かく訂正する美しい娘に。
チャーリー・デシュラーが、そのドロシーと結婚すると発表したときは、たちまち気が変になるぞと評判が立ったのだったが…。
「虹をつかむ男」のミティは、白昼夢に日々の逃げ場をもとめたけれど、本作のチャーリーはその白昼夢まで妻に蹂躙されてしまう。
ユーモラスな筆致のなかに、恐ろしいものが混じった一編だ。
「ブルール氏異聞」
糖液糖菓会社の会計係をしている、平凡な一市民のサミュエル・O・ブルール氏。
左の頬にクツ型の傷跡があるブルール氏は、たまたまギャングのクリニガンとそっくり。
敵方のギャングに撃たれ、入院中のクリニガンは、退院してもまた撃たれるだろうと報道されている。
すると、ブルール氏の行動が奇妙になっていき…。
クリニガンの代わりに自分が殺されるのではないかというのが、ブルール氏の妄想。
と、こう書けばひとことで終わってしまうけれど、それをいくつかのエピソードでみせる手際がみごと。
それに、ブルール氏がまったく妄想の住人になってしまうというラストが大変うまい。
「マクベス殺人事件」
イングランドの湖畔地方のホテルに宿泊していた〈私〉。
ミステリと思って「マクベス」を買ってしまったというアメリカ人女性と知りあいになる。
どうでしたかと〈私〉が訊くと、訊くと、「つまらなかった」と彼女。
「マクベスがやったとはとても考えられないわ」
どうしても、「マクベス」をミステリとして解釈する女性の話。
ほとんど会話で進むので読みやすい。
彼女いわく、怪しいのにかぎって絶対シロ、マクベスも夫人もやっていない、シェイクスピアは利口よ、犯人はマクダフです、ダンカンの死体をだれが発見したとお思いになって?、マクダフがみつけるんです、そうして階段を駆けおりてきてペラペラまくし立てるんです、全部あらかじめ用意していたことばよ、さもなきゃブッツケにあんな調子でペラペラいえますか――。
で、後半、彼女から「マクベス」借りた〈私〉は、殺人にかんする別の解釈を披露する。
くせのない、ただ単純にナンセンスで愉快な作品だ。
「ビドウェル氏の私生活」
やたらと深呼吸をするビドウェル氏と、それにイライラしてしょうがない夫人の話。
夫人は、深呼吸をしたり、パーティーの最中どれくらい息をとめられるか計っている夫がカンにさわってしょうがないし(気持ちはわかる)、ビドウェル氏のほうは、どうしてほっといてくれないんだと思っている(この気持ちもわかる)。
すれちがいの原因は、どうでもいいささいなことだけれど、その書きぶりは憂鬱になるほどリアルだ。
「決闘」
毎晩、アメリカ副大統領エアロン・バーのでてくる夢をみるようになってしまったアンドルース。
エアロン・バーは卑怯なやつで、アンドルースと話していたアレキサンダー・ハミルトンをさんざん小突きまわす。
そのうえ、決闘して射殺までしてしまう。
心配をする細君のよそに、アンドルーはピストルの練習をはじめ…。
夢が現実に侵入するというパターンの一編。
このたぐいの小説がとても好きだ。
読んだら、中島敦の「幸福」という作品を思い出した。
後味はぜんぜんちがうけれど。
「人間の入る箱」
箱のなかに隠れたいという強烈な欲望にとりつかれた〈私〉の話。
何箇所もの食料品店で箱をさがす〈私〉は、なんでまたと訊く店員にこうこたえる。
「まあ、逃避の一形式ですね」
やけになった作品というか、疲れ切った作品というか、投げやりというか。
悲哀感のある不気味な感じが印象に残った。
さて。
手元に「空中ブランコに乗る中年男」(ジェームズ・サーバー 講談社文庫 1987)があったのでそれも読んでみた。
訳者は、西田実・鳴海四郎。
「虹をつかむ男」に収録された作品が、何作か補筆されて収録されている。
「虹…」に収録されていない作品だけ挙げておこう。
「サリバント学校の思い出」
「大学時代の思い出」
「徴兵委員会にて」
「紳士は寒いのがお好き」
「ある犬の肖像」
「続 ある犬の肖像」
「インディアンのタメイキ」
「アイダおばさんの思い出」
「南北戦争式電話番号記憶法」
「夜中の騒動」
「オンボロ車レオ」
「わがやの台所太平記」
「現代イソップ物語」
「インディアンのタメイキ」と「現代イソップ物語」は小説。
残りは回想記。
「現代イソップ物語」はおそらく晩年の作品なのだろう。
ずいぶんユーモアが苦にがしいものになっている。
ところで、この本に収録された「ウォルター・ミティの秘められた生活」は、「虹をつかむ男」とおんなじ話だ。
「ウォルター・ミティの秘められた生活」は、原題を直訳したもの。
これを「虹をつかむ男」と訳したのは、いったいだれなのだろう。
きっと天才にちがいない。
訳は、鳴海四郎。
異色作家短編集、第9巻。
異色作家短編集は、3度装丁が改められたはず。
おおざっぱにいって、最初が黄色で次が黒、その次がピンクだったかと思う。
で、最初だけ箱入りだった気がする。
今回手元にあったのは、たまたま最初の黄色本。
表紙には、放射状に広がる線に、大きくなっていく円があしらわれている。
真似してみたけれど、こういうきっちりした図案がいちばん真似しにいくことを再確認。
本書は、ユーモア作家兼漫画家として名高い、ジェームズ・サーバーの短編集。
もっとも、映画「虹をつかむ男」の原作者としてのほうが有名かも。
収録作は以下。
「序文」
「虹をつかむ男」
「世界最大の英雄」
「空の歩道」
「カフスボタンの謎」
「ブルール氏異聞」
「マクベス殺人事件」
「大衝突」
「142列車の女」
「ツグミの巣ごもり」
「妻を処分する男」
「クイズあそび」
「ビドウェル氏の私生活」
「愛犬物語」
「機械に弱い男」
「決闘」
「人間の入る箱」
「寝台さわぎ」
「ダム決壊の日」
「オバケの出た日」
「虫のしらせ」
「決別」
「ホテル・メトロポール午前二時」
「一種の天才」
「本箱の上の女性」
訳者あとがきで、鳴海四郎さんが内容について簡単なジャンル分けをしている。
便利なので引用しよう。
まず、「虹をつかむ男」にはじまる16篇が小説風のもの。
「寝台さわぎ」にはじまる6篇が回想風のもの。
「ホテル・メトロポール午前二時」と「一種の天才」が犯罪実話もの。
最後の「本箱の上の女性」は、作者の漫画と、自作漫画についてのエセー。
さらに、小説はこんな風に分けられる。
「夫婦離反もの」
「白昼夢もの」
「機械嫌悪もの」
「愛犬もの」などなど。
いろいろあるけれど、面白かったのはやっぱり小説(でも、思い出そうとすると回想ものが思い出される。なぜだろう)。
なかでも面白かったのは以下。
「虹をつかむ男」
妻に頭が上がらない、ウォルター・ミティ。
妻が美容院にいっているあいだに買い物をしながら、さまざまに白昼夢にふける。
ウォルター・ミティは、「なにを見てもなにか思い出す」式に、隙あらば、強く劇的な自分を妄想する。
8発海軍飛行艇を指揮する、暴風雨をものともしない中佐、百万長者の銀行家を手術する医者、検事にパンチを食らわす被告人、爆撃機乗りの大尉…。
ミティの戯画化された妄想と、だれからも軽くあつかわれる情けない生活の対比が、短い分量のなかで見事に表現されている。
それに、ミティはちゃんと機械にも弱く、車の運転も下手。
正にサーバー的主人公。
映画化されたことを除いても、サーバーの代表作だろう。
「空の歩道」
小さなころから、相手がいおうとしていることを先回りして口走るくせのあったドロシー。
成長したドロシーは、男のことばづかいを細かく訂正する美しい娘に。
チャーリー・デシュラーが、そのドロシーと結婚すると発表したときは、たちまち気が変になるぞと評判が立ったのだったが…。
「虹をつかむ男」のミティは、白昼夢に日々の逃げ場をもとめたけれど、本作のチャーリーはその白昼夢まで妻に蹂躙されてしまう。
ユーモラスな筆致のなかに、恐ろしいものが混じった一編だ。
「ブルール氏異聞」
糖液糖菓会社の会計係をしている、平凡な一市民のサミュエル・O・ブルール氏。
左の頬にクツ型の傷跡があるブルール氏は、たまたまギャングのクリニガンとそっくり。
敵方のギャングに撃たれ、入院中のクリニガンは、退院してもまた撃たれるだろうと報道されている。
すると、ブルール氏の行動が奇妙になっていき…。
クリニガンの代わりに自分が殺されるのではないかというのが、ブルール氏の妄想。
と、こう書けばひとことで終わってしまうけれど、それをいくつかのエピソードでみせる手際がみごと。
それに、ブルール氏がまったく妄想の住人になってしまうというラストが大変うまい。
「マクベス殺人事件」
イングランドの湖畔地方のホテルに宿泊していた〈私〉。
ミステリと思って「マクベス」を買ってしまったというアメリカ人女性と知りあいになる。
どうでしたかと〈私〉が訊くと、訊くと、「つまらなかった」と彼女。
「マクベスがやったとはとても考えられないわ」
どうしても、「マクベス」をミステリとして解釈する女性の話。
ほとんど会話で進むので読みやすい。
彼女いわく、怪しいのにかぎって絶対シロ、マクベスも夫人もやっていない、シェイクスピアは利口よ、犯人はマクダフです、ダンカンの死体をだれが発見したとお思いになって?、マクダフがみつけるんです、そうして階段を駆けおりてきてペラペラまくし立てるんです、全部あらかじめ用意していたことばよ、さもなきゃブッツケにあんな調子でペラペラいえますか――。
で、後半、彼女から「マクベス」借りた〈私〉は、殺人にかんする別の解釈を披露する。
くせのない、ただ単純にナンセンスで愉快な作品だ。
「ビドウェル氏の私生活」
やたらと深呼吸をするビドウェル氏と、それにイライラしてしょうがない夫人の話。
夫人は、深呼吸をしたり、パーティーの最中どれくらい息をとめられるか計っている夫がカンにさわってしょうがないし(気持ちはわかる)、ビドウェル氏のほうは、どうしてほっといてくれないんだと思っている(この気持ちもわかる)。
すれちがいの原因は、どうでもいいささいなことだけれど、その書きぶりは憂鬱になるほどリアルだ。
「決闘」
毎晩、アメリカ副大統領エアロン・バーのでてくる夢をみるようになってしまったアンドルース。
エアロン・バーは卑怯なやつで、アンドルースと話していたアレキサンダー・ハミルトンをさんざん小突きまわす。
そのうえ、決闘して射殺までしてしまう。
心配をする細君のよそに、アンドルーはピストルの練習をはじめ…。
夢が現実に侵入するというパターンの一編。
このたぐいの小説がとても好きだ。
読んだら、中島敦の「幸福」という作品を思い出した。
後味はぜんぜんちがうけれど。
「人間の入る箱」
箱のなかに隠れたいという強烈な欲望にとりつかれた〈私〉の話。
何箇所もの食料品店で箱をさがす〈私〉は、なんでまたと訊く店員にこうこたえる。
「まあ、逃避の一形式ですね」
やけになった作品というか、疲れ切った作品というか、投げやりというか。
悲哀感のある不気味な感じが印象に残った。
さて。
手元に「空中ブランコに乗る中年男」(ジェームズ・サーバー 講談社文庫 1987)があったのでそれも読んでみた。
訳者は、西田実・鳴海四郎。
「虹をつかむ男」に収録された作品が、何作か補筆されて収録されている。
「虹…」に収録されていない作品だけ挙げておこう。
「サリバント学校の思い出」
「大学時代の思い出」
「徴兵委員会にて」
「紳士は寒いのがお好き」
「ある犬の肖像」
「続 ある犬の肖像」
「インディアンのタメイキ」
「アイダおばさんの思い出」
「南北戦争式電話番号記憶法」
「夜中の騒動」
「オンボロ車レオ」
「わがやの台所太平記」
「現代イソップ物語」
「インディアンのタメイキ」と「現代イソップ物語」は小説。
残りは回想記。
「現代イソップ物語」はおそらく晩年の作品なのだろう。
ずいぶんユーモアが苦にがしいものになっている。
ところで、この本に収録された「ウォルター・ミティの秘められた生活」は、「虹をつかむ男」とおんなじ話だ。
「ウォルター・ミティの秘められた生活」は、原題を直訳したもの。
これを「虹をつかむ男」と訳したのは、いったいだれなのだろう。
きっと天才にちがいない。
コメント ( 1 ) | Trackback ( 0 )
| « びんの悪魔 | ヴォネガット... » |





副題は、「ロスとショーンと愉快な仲間たち」。
この、雑誌「ニューヨーカー」についての回想録を読んでいたら、サーバーの肖像が捉えられていたのでメモ。
初期のニューヨーカー編集部には、壁やドアのあちこちにサーバーの落書きがあったそう。
そればかりではなく、メッセージもあった。
そのメッセージはいつも、「手遅れだ」だったそう。
サーバーの容姿についてはこう。
「サーバーは本来肥らない体質の、鳥のような骨格で、よく見かけるおそろしく背の高い人ではあったが、年齢をとるにつれて身体に締まりがなくなり腹が出てきて、三分の二は痩せた男、三分の一は肥満漢という体形になってしまった」
また、サーバーは作品からなんとなくわかるけれど、ずいぶん偏屈なひとだったらしい。
ブレンダ・ギルはこんなことも書いている。
「サーバーがホワイトを友人に持ったことに感謝してしかるべきだという事情は容易に想像できるのだが、それにしても、一体ホワイトはどうしてサーバーに我慢できたのか?」
このホワイトとは、E・B・ホワイトのことだ。
引用したように、本書は皮肉と抒情が巧みに溶けあった、洗練された文章で記されていて、読むのがじつに楽しい。
ただ、上下組みで350ページを超すので、読み通すのが大変(なぜ、むこうの回想録は大部なものばかりなのだろう)。
親切なことに、巻末に索引がついているから、気になるところだけ読むことも可能だ。