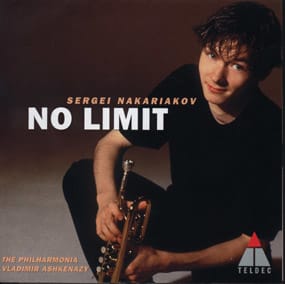ずいぶん前のコンテンツですが、
たくさんの人にアクセスしていただいているので、
以前の記事(以下の)のお詫びと訂正をさせていただきます。
※ピストが固定ギアであるかのように書いていますが、
ピスト、そのものは自転車競技(トラックレーサー)のことであって、こていぎあのメカニズムを指すものではありません。
僕も混同していましたし、世の中的にもピストは固定ギアということになっていますが、以前ご指摘いただいたとおり、ピストそのものは自転車構造ではありません。
ウィキのこのページに詳しいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%88
ブレーキ無しのフックスドギア自転車(フィクシーというようです)の参考記事はこちら。いい記事でした。
http://wiredvision.jp/archives/200504/2005040802.html
そして以下が、私が書いている
オリジナルのこの日のブログの記事です。
--------------------------------------------------
きょーも徹夜明けではなくオハヨーブログでございます。
先日昼飯に弁当を会に出たら、会社の近くにこんな自転車が止まっていた。おお。
これはブルホーンで、ピストで、革シートで、しかもカーボンホイール、クロモリだ。
って、全然わかんないでしょう。自転車マニアすぎでしょうか。
ハンドルが不思議な形をしていますが、これはブルホーンといって、文字通り牛の角のような形をしたハンドルです。
よーく考えてみるといわゆるレースの時のドロップハンドルの下の部分を切ったとも言えます。これは実に合理的で、レースの時のマジ走りでない限りハンドルの下の部分は持ちませんので、街乗りでブルホーンというのは理に適った話。しかも、実際にとても持ちやすいと言えます。個人的にはストレートハンドル(しかも幅が広いもの)に比べればずいぶん持ちやすい。
ただ、この写真のブルホーンはやや、特殊な形状ですね。市販のものではないかも、競輪用のハンドルを本当に切ったモノかも知れません。
さらにこのハンドルにブレーキが一切付いていないのにお気づきでしょうか。もう、潔くついていませんが、これは命知らずなのではなく「ピスト」という構造に由来しています。この自転車には変速機がない、チェーンが後輪と直結していて、フリー(逆回転)もない。つまりタイヤが回ればペダルも回る。タイヤが逆回転すればペダルも逆回転する、というもっともコアなピスタです。なのでブレーキは足でかけます。ペダルを止めるのです。ピストには乗ったことがありません。たぶん足ブレーキはかなり筋肉が必要でしょうし、慣れないと止まれないでしょう。特に急ブレーキは厳しい。時々自転車便のメッセンジャーの人が乗ってますね。
そして、革シート、これはま、文字通りですが、自転車乗りとしては憧れるところです。新品の状態だと革シートはとんでもなく痛いらしいですが、乗り込んでくると革がなめされつつ、自分のお尻の形状に合ってくるようで、非常に使いやすいものとなるそうです。これも未経験ですが、1万円から2万円ぐらいでいい革シートがあるのでBROCKSとか。試してみたいと思っています。
さて、最後ですが、タイヤを取り付けているホイールが、この自転車はカーボンホイールです、鉄でなく、アルミでもなく、カーボンでできてます。軽いし、なんか戦車みたいにごつい。これも乗ったことがないですが、自転車レースに出場したときに、後ろからこういうホイールの人にガンガン抜かれたことがありました。「ゴー」っていう凄い音で後ろから迫られると、怖いです。周回コースだったので(茂手木100キロサイクルマラソンというレースでした、茂手木のコースを20周囲乗します)何度も何度も先頭集団に抜かれましたが、そのたびにあの威圧的な音がしました。
自転車の師匠、ウメちゃんによると、カーボンホイールはアップダウンが少なく直進の多いレースでは非常に有用だそうです。そういえばツール・ド・フランスでもタイムトライアルではカーボンホイールが多いように思います。
最後に「クロモリ」ですが、これはクロームモリブデン鋼という、鉄の素材で、この自転車のフレームがクロームモリブデン鋼でできていることを示唆しています。自転車はフレームが全てを左右しますが(というか他のモノは全て交換可能)いま、多くの自転車は軽いアルミ製。クロモリはやや重いが、素材に弾性があって柔らかく(アルミに比べて)ノリ心地がいいとされています。僕もロード車を買うときなクロモリを候補にしていました。ジェイミスとかね。でも師匠がロッシンRossinというイタリヤのレース車を紹介してくれたので、それに乗ってます。いい自転車です。
さ、ここまで読んだあなたは、もう自転車通です。ぜひ自転車通勤をしてみてください。僕も今日は自転車で通勤しようと思います。

たくさんの人にアクセスしていただいているので、
以前の記事(以下の)のお詫びと訂正をさせていただきます。
※ピストが固定ギアであるかのように書いていますが、
ピスト、そのものは自転車競技(トラックレーサー)のことであって、こていぎあのメカニズムを指すものではありません。
僕も混同していましたし、世の中的にもピストは固定ギアということになっていますが、以前ご指摘いただいたとおり、ピストそのものは自転車構造ではありません。
ウィキのこのページに詳しいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%94%E3%82%B9%E3%83%88
ブレーキ無しのフックスドギア自転車(フィクシーというようです)の参考記事はこちら。いい記事でした。
http://wiredvision.jp/archives/200504/2005040802.html
そして以下が、私が書いている
オリジナルのこの日のブログの記事です。
--------------------------------------------------
きょーも徹夜明けではなくオハヨーブログでございます。
先日昼飯に弁当を会に出たら、会社の近くにこんな自転車が止まっていた。おお。
これはブルホーンで、ピストで、革シートで、しかもカーボンホイール、クロモリだ。
って、全然わかんないでしょう。自転車マニアすぎでしょうか。
ハンドルが不思議な形をしていますが、これはブルホーンといって、文字通り牛の角のような形をしたハンドルです。
よーく考えてみるといわゆるレースの時のドロップハンドルの下の部分を切ったとも言えます。これは実に合理的で、レースの時のマジ走りでない限りハンドルの下の部分は持ちませんので、街乗りでブルホーンというのは理に適った話。しかも、実際にとても持ちやすいと言えます。個人的にはストレートハンドル(しかも幅が広いもの)に比べればずいぶん持ちやすい。
ただ、この写真のブルホーンはやや、特殊な形状ですね。市販のものではないかも、競輪用のハンドルを本当に切ったモノかも知れません。
さらにこのハンドルにブレーキが一切付いていないのにお気づきでしょうか。もう、潔くついていませんが、これは命知らずなのではなく「ピスト」という構造に由来しています。この自転車には変速機がない、チェーンが後輪と直結していて、フリー(逆回転)もない。つまりタイヤが回ればペダルも回る。タイヤが逆回転すればペダルも逆回転する、というもっともコアなピスタです。なのでブレーキは足でかけます。ペダルを止めるのです。ピストには乗ったことがありません。たぶん足ブレーキはかなり筋肉が必要でしょうし、慣れないと止まれないでしょう。特に急ブレーキは厳しい。時々自転車便のメッセンジャーの人が乗ってますね。
そして、革シート、これはま、文字通りですが、自転車乗りとしては憧れるところです。新品の状態だと革シートはとんでもなく痛いらしいですが、乗り込んでくると革がなめされつつ、自分のお尻の形状に合ってくるようで、非常に使いやすいものとなるそうです。これも未経験ですが、1万円から2万円ぐらいでいい革シートがあるのでBROCKSとか。試してみたいと思っています。
さて、最後ですが、タイヤを取り付けているホイールが、この自転車はカーボンホイールです、鉄でなく、アルミでもなく、カーボンでできてます。軽いし、なんか戦車みたいにごつい。これも乗ったことがないですが、自転車レースに出場したときに、後ろからこういうホイールの人にガンガン抜かれたことがありました。「ゴー」っていう凄い音で後ろから迫られると、怖いです。周回コースだったので(茂手木100キロサイクルマラソンというレースでした、茂手木のコースを20周囲乗します)何度も何度も先頭集団に抜かれましたが、そのたびにあの威圧的な音がしました。
自転車の師匠、ウメちゃんによると、カーボンホイールはアップダウンが少なく直進の多いレースでは非常に有用だそうです。そういえばツール・ド・フランスでもタイムトライアルではカーボンホイールが多いように思います。
最後に「クロモリ」ですが、これはクロームモリブデン鋼という、鉄の素材で、この自転車のフレームがクロームモリブデン鋼でできていることを示唆しています。自転車はフレームが全てを左右しますが(というか他のモノは全て交換可能)いま、多くの自転車は軽いアルミ製。クロモリはやや重いが、素材に弾性があって柔らかく(アルミに比べて)ノリ心地がいいとされています。僕もロード車を買うときなクロモリを候補にしていました。ジェイミスとかね。でも師匠がロッシンRossinというイタリヤのレース車を紹介してくれたので、それに乗ってます。いい自転車です。
さ、ここまで読んだあなたは、もう自転車通です。ぜひ自転車通勤をしてみてください。僕も今日は自転車で通勤しようと思います。

 | ロードバイクメンテナンス―完全保存版エイ出版社このアイテムの詳細を見る |
 | ヴィンテージロードバイク―ロードバイク100年の歴史〓出版社このアイテムの詳細を見る |
 | 自転車ツーキニスト疋田 智知恵の森このアイテムの詳細を見る |
 | 自転車生活の愉しみ疋田 智朝日新聞社出版局このアイテムの詳細を見る |
 | それでも自転車に乗り続ける7つの理由疋田 智朝日新聞社出版局このアイテムの詳細を見る |
 | 疋田智の自転車生活スターティングBOOK疋田 智,自転車生活ブックス編集部ロコモーションパブリッシングこのアイテムの詳細を見る |
 | ただマイヨ・ジョーヌのためでなくランス アームストロング,Lance Armstrong,安次嶺 佳子講談社このアイテムの詳細を見る |
 | ミラクルトレーニング―七週間完璧プログラムランス アームストロング,クリス カーマイケル,Lance Armstrong,Chris Carmichael,本庄 俊和未知谷このアイテムの詳細を見る |
 | 毎秒が生きるチャンス! ナリッシュブックスランス・アームストロング,曽田 和子学習研究社このアイテムの詳細を見る |
 | ロードバイクメンテナンス (エイムック―Bicycle club how to series (861))藤原 富美男〓出版社このアイテムの詳細を見る |
 | ロードバイクトラブルシューティング―自転車メンテナンスのプロ直伝 (サイクルメンテナンスシリーズ (1))飯倉 清圭文社このアイテムの詳細を見る |
 | 新版 MTBメンテナンス永井 隆正エイ出版社このアイテムの詳細を見る |