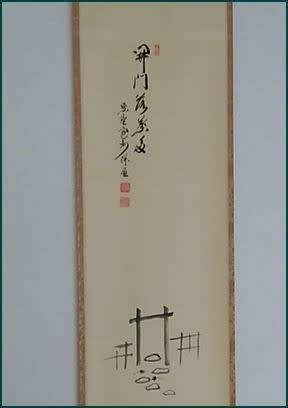戌年の稽古始に、干支茶碗を出しました。
可愛らしい犬が付いています。
暮れに「確か12年前の茶碗があったはず」と用意しておきました。
おかげさまで、十二支のお茶碗はそろっているようです。
それぞれに趣も、手にしたいきさつも違いますが、
みなその年を一年間、彩ってくれそうです。
兎や辰などは、道具組に都合よく時々使われるので、
中には立派な茶碗も目にすることがありますが、
総じて干支の物は、主役にはならないことが多いので、
楽しめるものが一つあればと、気軽に手に入れているうちに、
いつのまにか一回り揃いました。
干支の色紙も一回り揃っていると良いのですが、
これはどうも偏っているようです。
来年は自分の干支ですから、ちょっと頑張ってみようかしらなんて。
そんなことを考えているうちに、
一年はきっと瞬く間に過ぎてしまうのでしょう。
やりたい事をできるだけやって、悔いなく過ごさなくてはと思いますね。
まずは楽しく稽古の日々を送りたいです。