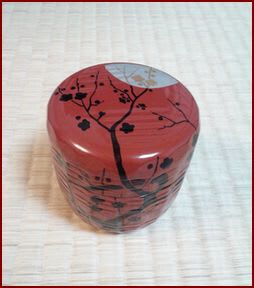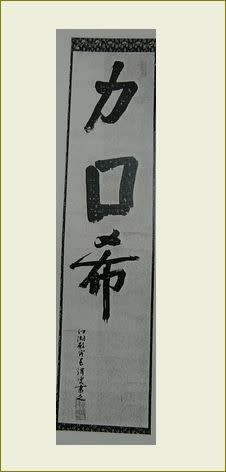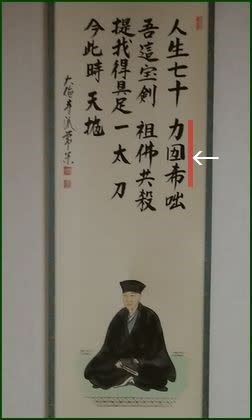今日は初めて伺う学校での茶道体験授業でした。
盆略点前を手本に見せながら、説明をした後、
全員がお茶を点てる体験をしました。
お菓子は「ちびどら」。
小さなどら焼きですが、やはりあんこの苦手な児童かいました。
それでも、お茶を頂くためにはと、一生懸命食べていましたよ。
インフルエンザはピークを過ぎたということですが、
マスクをしている児童も何人かいて、点てるときはマスク姿ですが、
さすがにお茶を頂くときはそうはいきませんね。

オープンスペースに畳を敷いて、盆略点前を楽しみました。
少しでも雰囲気を出したいと、花を置き、
軸代わりに掛けた色紙は「一期一会」です。
易しく説明しましたので、なんとかわかってもらえたと思います。
卒業まで大切な時間を、
友達と仲良く過ごしてもらいたいとの願いを伝えましたが。
15枚の畳に一クラス35人の児童です。
六年生は体も大きいですから、多少窮屈だったと思いますが、
皆さん仲良くお菓子を頂いて、お茶を点て合うことができました。
お手伝いの方に一緒に来ていただけたので、
両手に大荷物ということにならずに、助かりました。
もう少し若いころは、大きな荷物も苦にならず、
ふうてんの寅さんの営業と同じよ、などと言いながら、
茶道体験クッズ一揃えを下げて、
ひょいひょいとどこへでも駆けつけたものですが。
明日も、もう一クラスのために伺います。