
★「沖縄写真展」や元沖縄県知事大田氏を迎えての「平和の集い」を企画している私たちにとってタイムリーなテレビ番組「白旗の少女」が30日九時からテレビ愛知から放映されます。是非ご覧ください。
==================
<白旗の少女 とは、沖縄戦で白旗を掲げ投降した少女。大田昌秀編著『これが沖縄戦だ』に写真が初めて登場。1986年公開の記録フィルム「沖縄戦・未来への証言」の中の笑顔が県民の印象に残った。少女は当時7歳の比嘉富子。(琉球新報)>
日米で計20万人が犠牲になった沖縄戦(昭和20年4~6月)で、白旗を掲げて米軍に投降した当時7歳の少女の手記「白旗(しらはた)の少女」(講談社)がドラマになり、30日午後9時からテレビ東京系で放送される。原作者の比嘉富子さん(71)は、平和なはずの現代社会に自殺が多いことに心を痛め、「このドラマを通じて、命の大切さを感じ取ってほしい」と訴える。
沖縄南部の首里で生まれ育った比嘉さんは20年5月、米軍が迫っていることを聞き、姉や兄と避難を始めたが、途中ではぐれて一人になってしまう。家族を探してさまよううち、ガマ(自然の洞穴)で出会った優しい老夫婦の勧めに従い、フンドシで作った白旗を掲げて米軍に投降した。
投降の様子は米軍に写真と映像で撮影され、手を振る白旗の少女として広く知られる存在になった。比嘉さんは昭和62年に「少女は私」と名乗り出た後、今回の原作となる手記を出版した。
比嘉さんは「米軍のカメラを武器かもしれないと思ったが、『敵に泣きっ面を見せるな、笑って死ね』という父の言葉を思いだし、笑ってカメラに手を振った」と真相を明かす。
当時の映像では、比嘉さんの後ろを2人の日本兵が歩いている。「私が名乗り出るまでは、『弾よけのために少女を盾にした』などと、うそが一人歩きしていた。実際は、たまたま私の後ろを歩いていただけ」。白旗の少女を名乗る別人もいて、真実を公にしなければとの思いから名乗り出たという。
今回のドラマでは、比嘉さんの少女時代を八木優希(8)、大人になってからを黒木瞳(48)が演じる。「私はガマにいたおじいちゃん、おばあちゃんから命の尊さを教わった。今は平和なのに子供の自殺が多いが、命は一人のものではないことを感じてほしい」と、特に若い世代にアピールしている。(草下健夫)
(産経ニュースより)http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/090929/acd0909290821007-n1.htm
==================
<白旗の少女 とは、沖縄戦で白旗を掲げ投降した少女。大田昌秀編著『これが沖縄戦だ』に写真が初めて登場。1986年公開の記録フィルム「沖縄戦・未来への証言」の中の笑顔が県民の印象に残った。少女は当時7歳の比嘉富子。(琉球新報)>
日米で計20万人が犠牲になった沖縄戦(昭和20年4~6月)で、白旗を掲げて米軍に投降した当時7歳の少女の手記「白旗(しらはた)の少女」(講談社)がドラマになり、30日午後9時からテレビ東京系で放送される。原作者の比嘉富子さん(71)は、平和なはずの現代社会に自殺が多いことに心を痛め、「このドラマを通じて、命の大切さを感じ取ってほしい」と訴える。
沖縄南部の首里で生まれ育った比嘉さんは20年5月、米軍が迫っていることを聞き、姉や兄と避難を始めたが、途中ではぐれて一人になってしまう。家族を探してさまよううち、ガマ(自然の洞穴)で出会った優しい老夫婦の勧めに従い、フンドシで作った白旗を掲げて米軍に投降した。
投降の様子は米軍に写真と映像で撮影され、手を振る白旗の少女として広く知られる存在になった。比嘉さんは昭和62年に「少女は私」と名乗り出た後、今回の原作となる手記を出版した。
比嘉さんは「米軍のカメラを武器かもしれないと思ったが、『敵に泣きっ面を見せるな、笑って死ね』という父の言葉を思いだし、笑ってカメラに手を振った」と真相を明かす。
当時の映像では、比嘉さんの後ろを2人の日本兵が歩いている。「私が名乗り出るまでは、『弾よけのために少女を盾にした』などと、うそが一人歩きしていた。実際は、たまたま私の後ろを歩いていただけ」。白旗の少女を名乗る別人もいて、真実を公にしなければとの思いから名乗り出たという。
今回のドラマでは、比嘉さんの少女時代を八木優希(8)、大人になってからを黒木瞳(48)が演じる。「私はガマにいたおじいちゃん、おばあちゃんから命の尊さを教わった。今は平和なのに子供の自殺が多いが、命は一人のものではないことを感じてほしい」と、特に若い世代にアピールしている。(草下健夫)
(産経ニュースより)http://sankei.jp.msn.com/culture/academic/090929/acd0909290821007-n1.htm










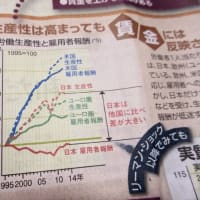
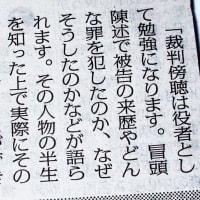





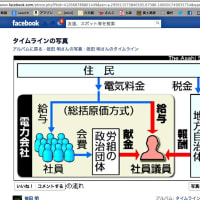
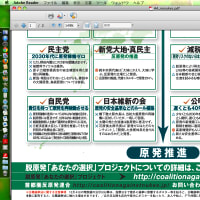




===============
めったにテレビを見ない人種なのですが、涙を禁じえないドキュメントでした。幾重もの偶然をかいくぐって、もららされた彼女の生から改めて沖縄戦の狂気の惨劇に思いをはせています。
ことに、姉を探してガマを覗き込む少女を、うるさいと追い返す兵は、何を狂ったのか、6歳のその少女を刀を抜いて追廻し、崖の淵で切り殺そうとするのですが、彼女は崖から転落、しかし、崖に生えている木にひっかかり、さらに落下。かろうじて生きながらえる奇跡に恵まれますが、ここで彼女が死んでいたのなら、兵が彼女を殺そうとしたことすら、後世の者にはわかりません。
少女に、壕から出るように諭し、彼女に白旗を持たせた老人夫婦の話も驚きでした。少女が出たあとに彼ら老夫婦に待っているのは米軍の爆弾投擲という運命なのに、、、。
やがて白旗を持った少女は、投降した人たちに混じり歩いてゆきます。
白旗を持つ少女にカメラを向ける米人。彼女はカメラを向けられたことで銃殺されると思い、苦しいときには笑顔を作れ、という兄の
(この兄も8-9歳だと思われますが、死亡)言いつけをまもって、恐怖のどん底の中で、カメラマンに笑顔で手をふって見せるけなげさに
は泣けてしまいます。
捕まれば、男は戦車に轢き殺され、女は陵辱の挙句に殺される、というマインドコントールは、かくも沖縄の人たちを、殺戮してゆきました。
父親が軍の食料調達に出かけるとき、娘たちに言います。
自分が万一戻れないときには、自分の頭でよく考えて行動せよ、と。農民であった彼は、軍の戦陣訓には無縁であったことを思うと、皇国
思想の何たるかを思い知らされます。
以上、まとまりませんが、、、。
そんな感想を持ちました。
お知らせくださった方に感謝です。
この文章自身が非常に良いドキュメントと読ませて頂きました。誰か個人のと言うよりも、戦争というものの悲惨さ、旧皇国というものの無惨がよく伝わってきます。
この戦争の異常さを異常と言わずに、逆にこういう人々がいるのですね。
「これが、この異常が人間なんだ。『人間の本質』なんだ。だからこそ、それに備えねばならないのである。軍備は必要だ」
冷戦も終わり、中国も体制に入った今は、北が責めてくると言っています。
人間のことを人間の希望では決められないという変な主張ですが、歴史上いつも出てきたものでした。警戒したいです。
これを読んで、こんな長い感想が書きたくなったというわけです。