既載の3回連載を1回にまとめてみました。気を入れた僕にとって大事な記事とて、できるだけ多くの方々に内容を知って欲しいと思いまして。よろしくお願いします。
「ルポ 難民追跡 バルカンルートを行く」(著者は、坂口裕彦・毎日新聞外信部。岩波新書)の内容をご紹介したい。
二〇一五年に西欧への難民大移動が特に激しかった時期、著者はウィーン特派員。記者として避けて通れない問題と考えた。ルポとはルポルタージュの略で、「現地報告」を決意したのである。それも、西欧への入口トルコ・ギリシャからドイツへという典型的ルートを通るだろう一家族に密着同行取材を認められて、その家族が属していた千人程の一団を追跡していくことになる。
いろいろ断られた揚げ句の取材相手は、イランから来た三人家族。アリ・バグリさんはアフガニスタンはバーミヤンの出身で三二歳、蒙古人の血を引く日本人に似た容貌のハザラ人。彼がイランに亡命したのが二〇一〇年、そこで同じアフガン出身のハザラ人、タヘリー・カゼミさん三〇歳と結婚した。一人娘のフェレシュテちゃんが四歳になったこの年に、ドイツへの移民を決意したのである。彼らに坂口さんが出会ったのは二〇一五年一一月二日。約一か月前イランを後にしてドイツに向かうべく移動し続けた末に、ギリシャ領レスボス島からアテネ・ピレウス港行きの難民船乗り込みを待って延々数百メートルも続いた隊列の中のことだ。なんとか英語が話せるアリさんが密着同行取材を快諾してくれたと、これがこのお話の始まりなのである。ちなみにレスボス島とは、トルコ領北西端の沖十キロにあるギリシャの島で、この島への渡航が密航業者で有名なすし詰め、決死のゴムボート。ここからアテネのピレウス港までは一日がかりのフェリー航海になった。
それからのこの家族の行程は、アテネには一一月一〇日まで居て、一一日がマケドニア、一二日がセルビアで、一三日にクロアチア、スロベニアを経て一四日には目的のドイツは南部メステュテッセンに着いている。マケドニア、クロアチア、スロベニアなどは特別列車を仕立てて、他は難民用バスで、千人単位以上を次の国に送り込んでいく。なんせ一五年に欧州に渉った中東難民は凄まじい数とあって、オーストリア、ドイツ、スェーデンなどの大量受け入れ国へと、どんどん送り込んでいくというやり方である。このルートは、二〇一五年春から二度変更された末に自然に出来あがったものと述べられている。セルビア・ハンガリー国境などをハンガリーが塞いでしまったことから以降二度大移動の流れが変わっていたということだ。
「世界総人口の一一三人に一人が強制移動」
これは、二〇一六年六月二〇日の国連難民高等弁務官事務所発表の見出しである。二〇一五年末で紛争や迫害で追われた人々が過去最多の六五三〇万人を、世界総人口七三億四九〇〇万人で割り出した数字だ。一五年度の新しい数字は一二四〇万人である。よって、一五年度末難民総数の五分の一近くが、一五年度に生まれたことになる。一五年度に生まれた難民の出身国内訳の五四%が、シリア、アフガン、ソマリアの三か国で占められているともあった。また、いわゆる地中海ルートなどを除いたこの本の舞台・バルカン半島北上ルートで多い順を見れば、シリア、アフガン、イラクの順になる。よって、難民が、戦争、内乱などから家族の命を守るために生まれるというのも明らかだろう。ただ、この本に書いてあったことだが、「豊かな人しか国外脱出難民にはなれない」のである。家など全財産を売って旅費が作れる家族とか、親族の「希望」が込められた金を掻き集めて「先遣隊(後には「本国に残った親族などの呼び寄せ隊」に変わる)」として出かけてきたという人々が多いと言われていた。彼らは希望を求めて難民の旅に出たのである。掲載された写真にある顔はほぼ全員明るく微笑んでいて、僕が持っていた難民というイメージとはかなり隔たっている。
さて、これを受け入れる側には明確に二種類の国がある。その両巨頭がドイツとハンガリーなのだが、この本の四,五章の題名が「排除のハンガリー」と「贖罪のドイツ」となっている。貧しいハンガリーは一五年秋に四メートルのフェンスを設けてセルビア、クロアチアとの国境を閉ざしてしまった。クロアチア国境のそれは約三百キロにも及ぶもの。他方のドイツは、「ドイツ、ドイツ!」、「メルケル、メルケル!」との掛け声が出る局面もあるような凄まじさだ。なぜドイツか。その理由は、想像にお任せする。
断る国の理由は当然理解できる。が、関ヶ原の戦い直前に、岐阜や三重に逃げてきた人々が居るとしたら、人としてどう接するべきか。その答えもまた、自明だろう。いわゆる経済難民との区別も難しいし、とても難しい問題だ。そして、この難問に向けて今の日本政府が世界一遅れた先進国だということだけははっきりしている。上記「排除のハンガリー」でさえ、排除策実施前の一五年夏時点では、首都ブダベスト東駅が列車待ちをするシリア、アフガン難民の「難民キャンプ」と化していたという事実もあったのだ。
最後に、この本末尾における、アリさんら三人家族の置かれた状況を、報告しておこう。著者は、最後に別れた仮収容の土地、ドイツ南部メスシュテッテンで再会してから、約四か月ぶりにチュービンゲンの新しい仮住まいを訪れている。当時チュービンゲンに身を寄せた難民は約一二〇〇人で、その九割はシリア、イラク、アフガンの人々という。三人家族は街の中心部からタクシーで十分程の閑静な住宅街の古い二階建て住宅に住んでいた。一階には三部屋があって、シリア人など他の二家族と十畳一間ずつをルームシェアしている。この三家族皆が難民申請が認められる日を待ってドイツ語教室にバスで通いながらいろんな猛勉強をしているということだった。
「フェレシュテちゃんは、相変わらず快活だ。ギリシャのレスボス島で、ボランティアにもらった象のぬいぐるみは、ベッドに大切そうに置かれていた。二週間前から、バスで五分程の幼稚園に、午前八時から午後一時まで通っているという。こちらも無料だ」
なお、こういう難民ルートとか受け入れ状況などの事実はすべて、仲間の難民や出身国に残された親類などに瞬時に伝わっていくのである。現代の難民らは皆、スマートフォンを持参し、ワイファイなども使いこなすから、これが難民の爆発的増加に拍車を掛けているようだ。酷い国は捨てられるということ。これも貧し過ぎ、人を虐げすぎる世界へ民衆が投げかける究極の抗議なのだろう。
「ルポ 難民追跡 バルカンルートを行く」(著者は、坂口裕彦・毎日新聞外信部。岩波新書)の内容をご紹介したい。
二〇一五年に西欧への難民大移動が特に激しかった時期、著者はウィーン特派員。記者として避けて通れない問題と考えた。ルポとはルポルタージュの略で、「現地報告」を決意したのである。それも、西欧への入口トルコ・ギリシャからドイツへという典型的ルートを通るだろう一家族に密着同行取材を認められて、その家族が属していた千人程の一団を追跡していくことになる。
いろいろ断られた揚げ句の取材相手は、イランから来た三人家族。アリ・バグリさんはアフガニスタンはバーミヤンの出身で三二歳、蒙古人の血を引く日本人に似た容貌のハザラ人。彼がイランに亡命したのが二〇一〇年、そこで同じアフガン出身のハザラ人、タヘリー・カゼミさん三〇歳と結婚した。一人娘のフェレシュテちゃんが四歳になったこの年に、ドイツへの移民を決意したのである。彼らに坂口さんが出会ったのは二〇一五年一一月二日。約一か月前イランを後にしてドイツに向かうべく移動し続けた末に、ギリシャ領レスボス島からアテネ・ピレウス港行きの難民船乗り込みを待って延々数百メートルも続いた隊列の中のことだ。なんとか英語が話せるアリさんが密着同行取材を快諾してくれたと、これがこのお話の始まりなのである。ちなみにレスボス島とは、トルコ領北西端の沖十キロにあるギリシャの島で、この島への渡航が密航業者で有名なすし詰め、決死のゴムボート。ここからアテネのピレウス港までは一日がかりのフェリー航海になった。
それからのこの家族の行程は、アテネには一一月一〇日まで居て、一一日がマケドニア、一二日がセルビアで、一三日にクロアチア、スロベニアを経て一四日には目的のドイツは南部メステュテッセンに着いている。マケドニア、クロアチア、スロベニアなどは特別列車を仕立てて、他は難民用バスで、千人単位以上を次の国に送り込んでいく。なんせ一五年に欧州に渉った中東難民は凄まじい数とあって、オーストリア、ドイツ、スェーデンなどの大量受け入れ国へと、どんどん送り込んでいくというやり方である。このルートは、二〇一五年春から二度変更された末に自然に出来あがったものと述べられている。セルビア・ハンガリー国境などをハンガリーが塞いでしまったことから以降二度大移動の流れが変わっていたということだ。
「世界総人口の一一三人に一人が強制移動」
これは、二〇一六年六月二〇日の国連難民高等弁務官事務所発表の見出しである。二〇一五年末で紛争や迫害で追われた人々が過去最多の六五三〇万人を、世界総人口七三億四九〇〇万人で割り出した数字だ。一五年度の新しい数字は一二四〇万人である。よって、一五年度末難民総数の五分の一近くが、一五年度に生まれたことになる。一五年度に生まれた難民の出身国内訳の五四%が、シリア、アフガン、ソマリアの三か国で占められているともあった。また、いわゆる地中海ルートなどを除いたこの本の舞台・バルカン半島北上ルートで多い順を見れば、シリア、アフガン、イラクの順になる。よって、難民が、戦争、内乱などから家族の命を守るために生まれるというのも明らかだろう。ただ、この本に書いてあったことだが、「豊かな人しか国外脱出難民にはなれない」のである。家など全財産を売って旅費が作れる家族とか、親族の「希望」が込められた金を掻き集めて「先遣隊(後には「本国に残った親族などの呼び寄せ隊」に変わる)」として出かけてきたという人々が多いと言われていた。彼らは希望を求めて難民の旅に出たのである。掲載された写真にある顔はほぼ全員明るく微笑んでいて、僕が持っていた難民というイメージとはかなり隔たっている。
さて、これを受け入れる側には明確に二種類の国がある。その両巨頭がドイツとハンガリーなのだが、この本の四,五章の題名が「排除のハンガリー」と「贖罪のドイツ」となっている。貧しいハンガリーは一五年秋に四メートルのフェンスを設けてセルビア、クロアチアとの国境を閉ざしてしまった。クロアチア国境のそれは約三百キロにも及ぶもの。他方のドイツは、「ドイツ、ドイツ!」、「メルケル、メルケル!」との掛け声が出る局面もあるような凄まじさだ。なぜドイツか。その理由は、想像にお任せする。
断る国の理由は当然理解できる。が、関ヶ原の戦い直前に、岐阜や三重に逃げてきた人々が居るとしたら、人としてどう接するべきか。その答えもまた、自明だろう。いわゆる経済難民との区別も難しいし、とても難しい問題だ。そして、この難問に向けて今の日本政府が世界一遅れた先進国だということだけははっきりしている。上記「排除のハンガリー」でさえ、排除策実施前の一五年夏時点では、首都ブダベスト東駅が列車待ちをするシリア、アフガン難民の「難民キャンプ」と化していたという事実もあったのだ。
最後に、この本末尾における、アリさんら三人家族の置かれた状況を、報告しておこう。著者は、最後に別れた仮収容の土地、ドイツ南部メスシュテッテンで再会してから、約四か月ぶりにチュービンゲンの新しい仮住まいを訪れている。当時チュービンゲンに身を寄せた難民は約一二〇〇人で、その九割はシリア、イラク、アフガンの人々という。三人家族は街の中心部からタクシーで十分程の閑静な住宅街の古い二階建て住宅に住んでいた。一階には三部屋があって、シリア人など他の二家族と十畳一間ずつをルームシェアしている。この三家族皆が難民申請が認められる日を待ってドイツ語教室にバスで通いながらいろんな猛勉強をしているということだった。
「フェレシュテちゃんは、相変わらず快活だ。ギリシャのレスボス島で、ボランティアにもらった象のぬいぐるみは、ベッドに大切そうに置かれていた。二週間前から、バスで五分程の幼稚園に、午前八時から午後一時まで通っているという。こちらも無料だ」
なお、こういう難民ルートとか受け入れ状況などの事実はすべて、仲間の難民や出身国に残された親類などに瞬時に伝わっていくのである。現代の難民らは皆、スマートフォンを持参し、ワイファイなども使いこなすから、これが難民の爆発的増加に拍車を掛けているようだ。酷い国は捨てられるということ。これも貧し過ぎ、人を虐げすぎる世界へ民衆が投げかける究極の抗議なのだろう。










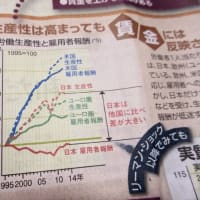
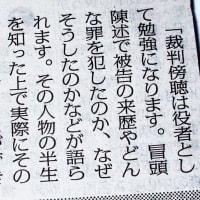





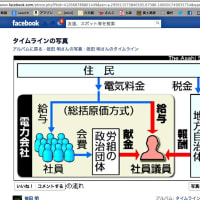
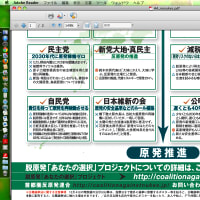




なにか、日本と酷く違う国民性のように感じるのは、僕だけだろうか? ヒューマニズムとか世界同朋主義のような精神を感じる。それも民衆の自主的な姿勢だから、大東亜共栄圏(思想)のような偽物ではない。
対するに日本為政者たちの目線は「労働力として必要かどうか」、「日系移民の子孫であるか否か」みたいだが、西欧と日本為政者、この二つはえらく開きあるような。
治安悪化の代償を支払ってまで、難民を受け入れようって人は、日本では少ないかもね。
在日南北朝鮮人だけで、十分大変な事になっている。
まず、アルカイダを育てたのはアメリカである。旧ソ連からアフガンを引き離すためにアルカイダを支援し続けた。武器を与え、訓練までしてね。ここで、ビンラディン自身も元はといえばアメリカに育てられたということ。
次いで、イラク戦争。国連の制止を振り切って有志国で強行したこの「嘘の理由」戦争から、イスラム国も生まれた。旧フセイン軍隊残党が、イスラム国の一大部隊とは、すでに有名な話。
次いでシリアへの、アメリカによる内戦工作。ここでイスラム国がさらに大きくなって、イラク・シリアに跨がる大勢力になった。
さて、以上を抜きにしたら、今回の独テロも、ちょっと前のフランス・テロもなかったはずだ。つまりこういうこと。今のテロは元はといえば、「世界の警察」として勝手に振る舞ったアメリカが作ったものばかりである。すべて国連を無視してやったこととて、アメリカ最大の悪事と言える。
何でこんなことを、日本のマスコミは報道しないのだろうか。南スーダン国連決議で日米が対立した今、日本マスコミも少しは変われよなと思う。アルカイダやイスラム国の上記の出生因などもちゃんと報道すべきなのだ。これらすべてがそもそも、今西欧を中心に世界を騒がせている難民問題の発生因でもあるのだし。安倍による報道統制も熾烈なのだろうが、それにしても日本のマスコミは程度が低くて、ツマラン。
国連が強くならなければ上記国々の問題は解決できないし、そうであれば日本の問題もなおさら解決できないと、そんな気がするのである。福島原発問題も、本来ならば国連が世界の世論を組織して解決に向かわせるべきなのだ。日本国民の声とともに、そういう世界からの、何か酷い国の事件への声も必要な時代になったのだと思う。国連をそっちのけにしたG7とかのイニシアティブは碌なもんじゃないと言いたい。世界の趨勢から見れば、G7方針よりもまだ、BRICS方針の方がマシと感じるほどだ。
アメリカはトランプになっても相変わらず国連を骨抜きにする努力は続けるだろう。が、各先進国民主主義勢力は、自国の民主化と同等に国連民主化にも努めるべきだと愚考する。
なんせ、アメリカの酷い意見は国連総会ではいつも通らないようになりつつあるのだから。
そもそも、世界が貧乏になれば日本の輸出はじり貧になっていくばかりなのだし、資源などを含めて現在世界ではアフリカが最も搾取されていると思うのである。石油で贅沢三昧の中東王族のように、資源独裁政府の方が相手国には都合良いということもあるのだろう。
などなど、とにかくこのエントリー関連4本はお読み願いたい。よろしくお願いします。
シリア情勢という時は先ず、この独立国に7年間も内戦を仕掛けてきたアメリカ、イラクと並んでここにイスラム国を作ることになったアメリカを思うべきであると愚考する。オバマが折角不干渉・先ずイスラム国鎮圧に動いたのに、トランプが元に戻してしまった。寄って難民問題はまたまた続いていく。アサド政権嫌いからの難民も居るだろうが、圧倒的多数は内戦を避ける人人だということだ。イラクを観ても、内戦は地獄を作っていく。
例えば、こう考えてみたらよい。
第1回目の化学兵器使用(疑惑)以来ずっと反乱軍が居る。そこに武器も供給し、反乱軍兵の訓練までをアメリカはやっている。それを公表さえしている。イスラム国に手を焼いている上の、反乱軍だ。このイスラム国もアメリカが生んだに等しいものである。さて、シリアと米国とどちらが罪が重いか。
誰が考えても答えは明確。
「アメリカは自国に帰れ。こんな遠くに戦争工作に来るな」
これは当たり前の話だろう。
難民問題はイラク戦争以降の世界最大不幸である。そしてこの全てが、アメリカの世界戦略上の罪だということもはっきりとしている。
アメリカの対シリア戦略は、長年にわたった米の仇敵イラン対策の一環。「シリアの化学兵器使用」も、「イラク大量破壊兵器」と同様で、いまだに実に根拠薄弱なもの。反政府軍地域での反政府軍貯蔵庫が爆発というニュースさえ存在するのである。「シリア軍がもたらした虐殺数」ですら、反政府軍支配地域での死者数は全て政府軍によるものと観た数字なのである。
これら全て、わざわざ地球の裏側まで出かけて戦争をする側を疑いの目で観るというやり方の方が適切だろう。そんなことは人として当たり前の理屈に思えるのである。
「イラク大量破壊兵器が嘘だったと分かってしまったから、今度はこうやった。嘘だと分からないようなドサクサを作り出して、ドサクサ紛れのニュースを世界に流した」と。
因みに、ホワイトヘルメット発の映像など「現地ニュース」だけが世界に出回っているという事態があるが、これこそフェイクニュースというものであろう。このホワイトヘルメットこそ、西欧のどこかの団体が資金を出している「人命救助・慈善団体」なのである。どうせその資金元は、世界石油資本なのだろう。近い過去にはリビアの石油を手に入れ、今後はイランの原油を狙っていると。