ちょっと遅れたが、7月27日の独スーパーカップ戦を報告・分析してみたい。このゲームは言うまでもなく、本年5月のチャンピオンズリーグ決勝戦を2ヶ月遅れで再現したものでもある。この1年、ドイツのみならずこの5月CL決勝戦も含めて世界を席巻したと言えるバイエルン相手に、ドルトムントがどれだけ盛り返せるか。来年以降のヨーロッパを占うに最良のゲームとも言えたのである。
4対2でドルトムントの勝利という結果以上に、結論を言うとドルトムント恐るべしと見た。どのように、であるか。4対2までの点差推移でドルトが終始攻勢、先ずこれを見ておこう。1対0、1対1、3対1、3対2、4対2という経過であった。この推移以上に、全体として意外に差があったと思う。それは、こんなところに現れていたと、皆が見たはずだ。
①球際にかなりの差があると感じた。ドルトの相手ボールへの寄せが非常に速くて、強くて、鋭い。味方ボールの繋ぎも相手を充分に引きつけておいたうえで、余裕を持って鋭くて速いパスを出す。それもサイドチェンジなど長いのもふんだんに織り交ぜてのことだ。香川や乾のように、ダッシュを終盤近くまで繰り返せる選手ばかりをそろえて、さらにそのダッシュ本数を急激に伸ばしているということだろう。そうでなければ、あんなふうにいつも良いポジションをとれるわけがない。
②それでも、金に飽かして世界超一流の選手ばかりを擁しているバイエルン相手だから、めまぐるしいターンオーバーになる。が、バイエルンが全体として、次第にどこか緩く見えてきたものだった。それほどに、ドルトが1対1の競り合い練度において、鍛え方が違うと感じた。まず、球際における、技術はともかくとして、今流行の言葉インテンシティーの差。それ以上に、ダッシュ回数で次第に相手を押し込めていくと、そんな感じだった。ダッシュ回数・そのインテンシティーで負け始めると、持てる技術も発揮できないということではないか。もちろん、チーム全体の良いポジション取りが最重要の前提になるはずだが。
③確かに、バイエルンの強さも見た思いはあった。バイエルンの敵ゴール前プレーだけはちょっと違うのである。ラームのクロスと、それへのロッベンの技巧などは肌寒さを覚えるほどだった。新人アルカンタラ・チアゴも、あわや得点というスルーパスを2本見せていた。とは言え誰もがこう感じたゲームだったはずだ。「ドルトムントはとにかく元気だ!」。こういう感じの表現を①②で試みたつもりである。
ドルトは2ヶ月前のチャンピオンズリーグ敗戦時よりかなり強くなっていると見た。でなければ、この1年世界無敵のバイエルン相手に、これだけのゲームができるわけがない。クロップがチャンピオンズリーグ敗戦を充分に研究してこの2ヶ月を過ごし、この間に狙った成果が充分にあったということだろう。やはり、恐ろしい監督だと再認識した。マルコ・ロイスやレパンドフスキ、フンメルツはもちろん、特にギュンドガンと、結局レアルから戻ってきたシャヒンら、全員が上述の①②でさらに伸びているということだと思う。
なお、このゲームだけで監督としてのペップの才能を語るのは間違っていると言いたい。1部監督初体験にしてバルサをあれほどに伸ばした人物だということを忘れてはならない。今の世界サッカーで、クロップに次いでモウリーニョと並ぶ監督だと、僕は信じて疑わない。クロップを世界20年に1人出るかどうかという監督とすると、この二人もそれに近い監督だと思う。ただクロップは何度も言うように、クライフかアリゴ・サッキか(ファーガソンか)という実績を創るほどの可能性を秘めた人物と、改めて感じたものだった。
ゲーム後にユルゲン・クロップが語った言葉がふるっている。
『2013─14年シーズンは「バイエルンはわれわれのライバルではない」と自信を示した』
なお、このゲームがここ数年の世界サッカー界でどれだけ大きな意味を持つかという資料を上げておこう。このバイエルンミュンヘンというチームがここ5年のCLでどれだけ健闘してきたか。優勝1回、準優勝2回、ベスト8と16が各1回である。バルセロナに接近して、ダントツの2強クラブだ。ただ、ペップがいなくなってからここ2年のバルサはベスト4続きである。本田が憧れているミランなどは、この5年間にベスト8が1度という実績でしかないのである。世界サッカー界は大きく変わり始めている。
4対2でドルトムントの勝利という結果以上に、結論を言うとドルトムント恐るべしと見た。どのように、であるか。4対2までの点差推移でドルトが終始攻勢、先ずこれを見ておこう。1対0、1対1、3対1、3対2、4対2という経過であった。この推移以上に、全体として意外に差があったと思う。それは、こんなところに現れていたと、皆が見たはずだ。
①球際にかなりの差があると感じた。ドルトの相手ボールへの寄せが非常に速くて、強くて、鋭い。味方ボールの繋ぎも相手を充分に引きつけておいたうえで、余裕を持って鋭くて速いパスを出す。それもサイドチェンジなど長いのもふんだんに織り交ぜてのことだ。香川や乾のように、ダッシュを終盤近くまで繰り返せる選手ばかりをそろえて、さらにそのダッシュ本数を急激に伸ばしているということだろう。そうでなければ、あんなふうにいつも良いポジションをとれるわけがない。
②それでも、金に飽かして世界超一流の選手ばかりを擁しているバイエルン相手だから、めまぐるしいターンオーバーになる。が、バイエルンが全体として、次第にどこか緩く見えてきたものだった。それほどに、ドルトが1対1の競り合い練度において、鍛え方が違うと感じた。まず、球際における、技術はともかくとして、今流行の言葉インテンシティーの差。それ以上に、ダッシュ回数で次第に相手を押し込めていくと、そんな感じだった。ダッシュ回数・そのインテンシティーで負け始めると、持てる技術も発揮できないということではないか。もちろん、チーム全体の良いポジション取りが最重要の前提になるはずだが。
③確かに、バイエルンの強さも見た思いはあった。バイエルンの敵ゴール前プレーだけはちょっと違うのである。ラームのクロスと、それへのロッベンの技巧などは肌寒さを覚えるほどだった。新人アルカンタラ・チアゴも、あわや得点というスルーパスを2本見せていた。とは言え誰もがこう感じたゲームだったはずだ。「ドルトムントはとにかく元気だ!」。こういう感じの表現を①②で試みたつもりである。
ドルトは2ヶ月前のチャンピオンズリーグ敗戦時よりかなり強くなっていると見た。でなければ、この1年世界無敵のバイエルン相手に、これだけのゲームができるわけがない。クロップがチャンピオンズリーグ敗戦を充分に研究してこの2ヶ月を過ごし、この間に狙った成果が充分にあったということだろう。やはり、恐ろしい監督だと再認識した。マルコ・ロイスやレパンドフスキ、フンメルツはもちろん、特にギュンドガンと、結局レアルから戻ってきたシャヒンら、全員が上述の①②でさらに伸びているということだと思う。
なお、このゲームだけで監督としてのペップの才能を語るのは間違っていると言いたい。1部監督初体験にしてバルサをあれほどに伸ばした人物だということを忘れてはならない。今の世界サッカーで、クロップに次いでモウリーニョと並ぶ監督だと、僕は信じて疑わない。クロップを世界20年に1人出るかどうかという監督とすると、この二人もそれに近い監督だと思う。ただクロップは何度も言うように、クライフかアリゴ・サッキか(ファーガソンか)という実績を創るほどの可能性を秘めた人物と、改めて感じたものだった。
ゲーム後にユルゲン・クロップが語った言葉がふるっている。
『2013─14年シーズンは「バイエルンはわれわれのライバルではない」と自信を示した』
なお、このゲームがここ数年の世界サッカー界でどれだけ大きな意味を持つかという資料を上げておこう。このバイエルンミュンヘンというチームがここ5年のCLでどれだけ健闘してきたか。優勝1回、準優勝2回、ベスト8と16が各1回である。バルセロナに接近して、ダントツの2強クラブだ。ただ、ペップがいなくなってからここ2年のバルサはベスト4続きである。本田が憧れているミランなどは、この5年間にベスト8が1度という実績でしかないのである。世界サッカー界は大きく変わり始めている。










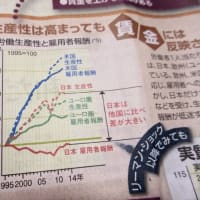
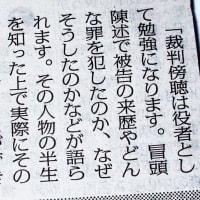





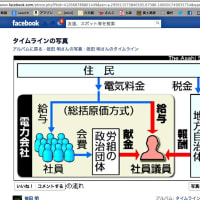
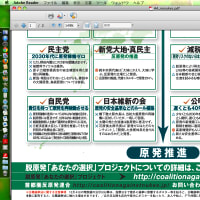




1500字ほどの中に「最も重要な」二つの事項を書いた積もりです。サッカーのゲーム分析として最も重要なこと。
一つは、2チームの「組織的鍛錬」として最も差があったところを。
今一つは、このゲームの意味です。後者についてはさらにこう言う事実も追加したかった。
①ここ5年のCLでこれほど強いバイエルンが、去年までドルトムントに2連覇を許してきたという事実。
②それをやっと、バイエルンが今年雪辱できたのだ。リーグ戦、カップ戦などと、CL決勝で。ほぼ完勝!
③こういう事実を踏まえると、今回のスーパーカップは来年の世界動向を占いうる最重要ゲームであったはず。そして、これをドルトが巻き返した意味! 大げさに言えば歴史的なものと思います。二チームの戦力差を考えると、ドルトの戦略(の質と、その選手への浸透力と)がいかに世界最良のものかということでしょう。しかもCLの敗北からわずか2ヶ月で逆転して見せた、この力!
今後もご批判など、よろしくお願いします。日本のヨーロッパ雀の方々が僕には、保守的に思えて仕方ないんですよね。だから、批判があるのはある意味当然と覚悟しています。
『アタッカーだけを見るのが、素人。ちょっと分かってくると、そのアタッカーに気持ちよく打たせているセッターを見始める。最も分かっている奴は、セッターによいトスを出させるパス組織に注目する』
サッカーも同じでしょうね。
①名のあるFWばかりを見て「結局、個人能力!」とか言っているのは、素人。
②ちょっと分かってくると、スルーパスやクロスなどアシスト段階を見る。
③最も分かった奴は、良いアシスト段階に至ることが多い組織作りを見る。
さて、以上は、点取りの側面のことだけですが、まー真実でしょう。世界的に名のある超一流選手がいないドルトの強さは、特に③でないと分からない点が重要と、僕は思いますね。
①特に敵ボール奪取で目立つ、例えばあるボランチばかりを見る。
②①の彼のところでボールを取りやすくしている、前からのプレスなどを見る。
③後など全体がパスの出し先を塞ぎ、敵ボールを出しにくくまた敵ボールを囲いやすくしているコンパクト陣形などを見る。