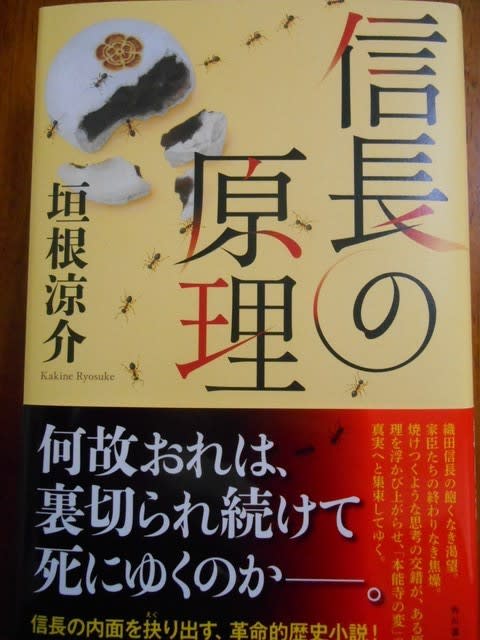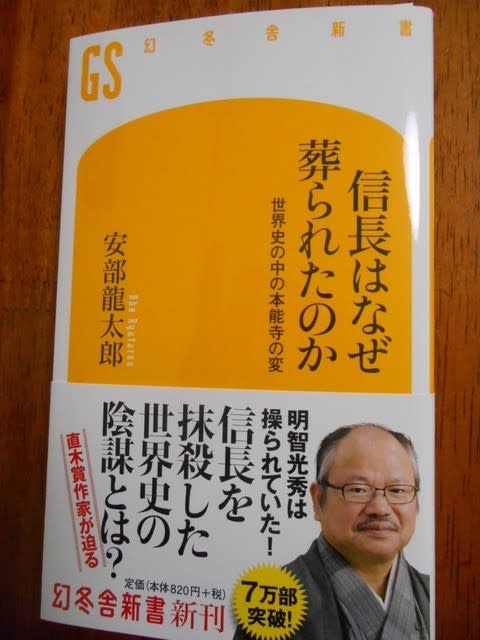時は「秋」
秋の味覚と言えば…「柿」
でしょ!
先日、地区の老友会の日帰りバスハイクで柿の故郷を訪ねた。
私は、旅行会社に勤めていたので、仕事中には「土産物」を
提げて帰ることはなかった。
リタイアした今でも、出かけた先での「土産物」は
ほとんど買わなかった。
特別に頼まれれば…という程度です。
その後に、何という縁なのか~ 毎日毎日、「柿」が我が家に。
自宅の庭になったから、珍しくもないけれど食べてと…
艶々した小ぶりの柿・・・・おいしそう

翌日には
自宅で毎年、祖母が手づくりの「干し柿」を作っているからと
まだ「干し柿」になる前の、卵で言えば…「半熟」状態。
これがまた格別にうまい!
冷蔵庫で冷やしておくと、熟した実がとろりと
舌にまとわりつく、なんとも言えない、甘さが…
ちょうど晩酌のワインの友に、最適でした。

さらに、びっくり、ちょっと出かけてきたから~
と、土産に1袋と 頂いたのが…
なんと、また「柿」
しかし、これは、干し柿の一段、上を行く?
「乾燥柿」だった。

なんで、どうして…いっぺんに「柿」の襲来です。
先ほどの自宅に庭で収穫した…とある話。
ほんとうにうらやましい話です。
松尾芭蕉の「柿」の1句に。
「里ふりて 柿の木もたぬ 家もなし」
というのがある。
私も リタイヤするまでの40余年、全国を転勤で渡り歩いた?
身としては ~
この芭蕉の心境も納得です。
ちゃんとした田舎の農家?の庭には必ず柿の木が
植えられている…
「桃、栗三年、柿八年」 その在所にずっと住む人
家も村も 古い歴史がそこにはある。
だから… と
「漂泊の詩人」芭蕉も
私のような永年 マンション生活を過ごしてきた人間には
できない相談だと。
現在、ふるさとに帰って~16年。
「柿」を 植えておれば…今頃、立派に秋の収穫が~
と、気が付いたが…
もう、いいか。
こうして、思いがけなく「柿」の襲来を
これからも 期待することに?
そりゃ ちいと甘いよ と 言われそう。
頂けない話
きっと「渋い」話ですよね。
すぐ隣の 柿の木

聞いてみたら…渋柿でした。
鳥獣愛護の為に 鳥の餌だって…ご立派!