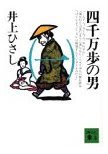図書館に行ったら、『映画力のある人が、成功する』(中谷彰宏著、ダイヤモンド社)という本が目に飛び込んできました。「社会力」とか「人間力」とか、「ナントカ力」という言い方が最近やたらと目につきますが、「映画力」とはいったいなんぞや?
同じ映画を見ても感じることは人によって違うのは当然のことです。面白いと思うか思わないか、どのシーンが印象に残ったか、どんなセリフにぐっときたか、結末は満足できたか、主 . . . 本文を読む
映画の予告編を見て、高校生バンドがブルーハーツ、という取り合わせが面白そうかなと思い、本屋でノベライズを見かけたのでとりあえず買って読んでみました。しかし…。
深みのないオハナシ。ノベライズだから映画の方もほとんどこのままのストーリーなんだろうけど、どんな映画か想像がつきます。ソンが「リンダ リンダ」をどう歌うのかは見てみたくもありますが、そのためだけに映画館のシートに身を沈めることはないでしょ . . . 本文を読む
高校時代、中原中也と立原道造と谷川俊太郎が好きでした。いつも持ち歩いていた角川文庫の詩集は3冊とも同じように色あせ、ページはボロボロになっています。今でも時折ひもとかせるのは、詩そのものを読むというよりは、あの頃の自分の感覚をなぞりたいという気持ちからなのかもしれません。
中也、道造の順に読んで、谷川俊太郎に初めて出会った時、前二人の「感傷」の世界にどっぷり浸っていた私は、どうにも落ち着かないも . . . 本文を読む
ガストン・ルルーの『オペラ座の怪人』(三輪秀彦訳、創元推理文庫)とスーザン・ケイの『ファントム』を続けて読みました。
『オペラ座の怪人』は、いくつか翻訳がありますが、その中でも三輪訳はもっとも古典風で荘厳な訳ではないでしょうか。そのせいもあり、読みにくい、という点は否定できません。たとえば、怪人(エリック)が住む地下室の様子など、なかなか具体的にイメージできないのにはまいりました。
「オペラ座 . . . 本文を読む
関節話法
2005-04-29 | ■本
職場にしょっちゅう指の関節をポキポキ鳴らしている人がいます。けっこういい音がします。私は関節が鳴らないほうなので、関節で音が出ること自体、とっても不思議です。
筒井康隆に「関節話法」という短編小説があります(『宇宙衛生博覧會』所収)。「間接話法」ではなく、「関節」話法です。
マザング星という惑星では、「関節話法」つまり、全身の関節を鳴らすことによって会話が行われています。マザング星は地球とよく . . . 本文を読む
ちょっと勘違いをしていたらしく、村上春樹が米国で出した短編集を「再翻訳」して日本で出版したもの、と思っていました。訳したのは彼本人?そんな馬鹿な。でも日本語→英語→日本語となると、けっこう面白いかも。もともとの「原作」と比べてみるのもいいぞ、なんて一人で勝手に想像しながら、本屋でペーパーバック風の黄色い本を手にしました。
ところが、買ってからよく本を見たら「英語版と同じ作品構成で贈る」と帯にある . . . 本文を読む
私たちが小さい頃に「少年少女世界の名作」として読んだ作品の多くは、19世紀の欧米諸国で書かれたものです。「宝島」、「八十日間世界一周」、「十五少年漂流記」といった冒険小説は、イギリスやフランスの海外進出を背景にしています。「クオレ」は「母を訪ねて三千里」など9つの物語から構成されていますが、そのほとんどがイタリアの統一、イタリア人の愛国心を根底としています。「厳窟王」(「モンテクリスト伯」)や「あ . . . 本文を読む
NHKで放映しているドラマ「ハチロー」を初めて見ました。
サトウハチローを演じているのは唐沢寿明。ハチロー本人を知らないし、原作の『血族』(佐藤愛子)を読んでもいないのでイメージと合っているのかどうかわかりませんが、滑舌の良さは相変わらずで、落ち着いて見ていられますね。
父・佐藤紅緑に反抗しながらも、結局は父と同じハチャメチャ人生を送ったハチローですが、その血には、父の故郷津軽の風土が色濃く反 . . . 本文を読む
昨日書いた『華氏451度』で、モンターグを助ける元大学教授フェイバーがこんなことを言っています。
─書物とは、忘れ去ってしまうには惜しい事物を保存しておくための道具で、書物自体には、なんら魔術的なものは存在しておらん。魔術的なものがあるのは、書物が語っておるその内容です─
ところが、書物自体に「魔術的なもの」を見いだしてしまった人たちを描いたミステリーがあります。ジョン・ダニングの『死の蔵書』 . . . 本文を読む
「華氏911」ではありません。
レイ・ブラッドベリの『華氏四五一度』。ハヤカワ文庫の帯には、「マイケル・ムーア監督は、本書に敬意を表して「華氏911」をつくった」とあります。ところが、ブラッドベリ氏がマイケル・ムーア氏を非難しているとも伝えられており、タイトルに関しては、マイケル・ムーア監督の一方的な片思いのようです。それにしても、御年83歳ブラッドベリ氏の怒りようはすさまじいらしく、単にタイト . . . 本文を読む
柄刀一の『ifの迷宮』。タイトルと、宮部みゆきの解説に惹かれて買ったものの、3頁目くらいから「あれ?」という感じ。文章が全然ついていけない。文体が、というより、すんなりと読み進むことができない表現が多い。どうにも気になって突っかかってしまう。違和感。
それでも、近未来の遺伝子医療とくに障害の有無に関わる出生前診断の話などに興味をそそられる形で何とか読み進めていましたが、遺伝子医療の最先端をいく同 . . . 本文を読む
浅田次郎の本って今まで読んだことがありませんでしたが、今回初めて手にしたのが『シェラザード』(講談社文庫、上・下巻)です。
太平洋戦争中に金塊を積んだまま台湾沖に沈んだ豪華客船「弥勒丸」をめぐり、現代と当時を往復する物語です。絶対に沈められることがないはずの「緑十字船」弥勒丸の「誤爆」による沈没をクライマックスに、当時の乗組員たちの思い、そして現代に生き残る人たちの弥勒丸引き揚げに関わる駆け引き . . . 本文を読む
伊能忠敬が星学暦学を志し、日本の海岸線を測量し始めたのは56歳の時だという。
当時の平均寿命なら、既に鬼籍に入っていてもおかしくない年である。それまでの彼は下総佐原村の商家の旦那としてまた村の素封家として知られていたに過ぎない。
ところが彼は、その「第二の人生」によって後世に名をその名を残すことになる。
「第二の人生」といっても、もちろんそれまでの人生とかけ離れたものになるはずはなく、「第一の . . . 本文を読む