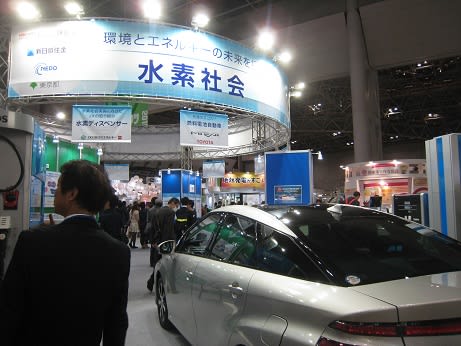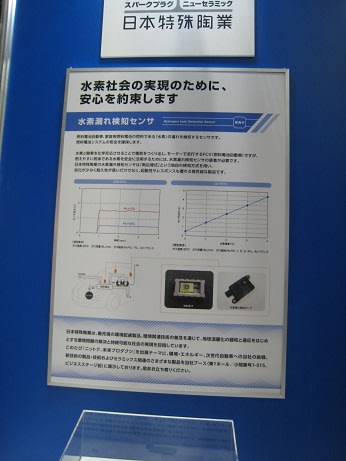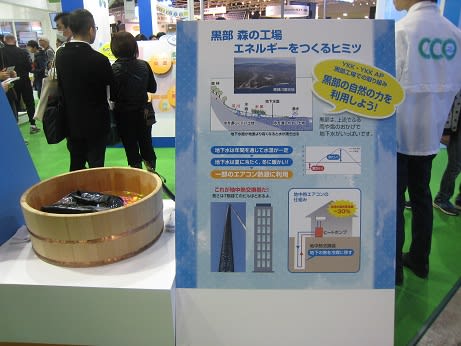このブースは「JOGMEC/日本地熱協会」というものらしいです。
「JOGMEC」とは、独立行政法人 石油天然ガス金属鉱物資源機構。
石油・天然ガス・金属・石炭・地熱に関する開発支援やメタンハイドレートなどの新エネルギーの開発・資源備蓄事業などをやっている。
ブースの看板の写真を撮ってこなかったのですが「地熱」という文字に引かれて見に行きました。

撮ってきた写真は、これ1枚ですが、日本各地各所で地熱発電が行われているんだなあと驚きました。
原発事故の後、地熱発電がこれからの発電方法として注目されていましたが、火山があるところは国立公園の場合が多く、温泉施設等もあり、そういうところに工場のような施設を作ることができないということで、なかなか開発ができないと聞いていました。その後の状況はどうなのでしょう。
地熱クイズをやりました。
正解
・地熱発電は、マグマの熱を利用しています。
・日本の地熱資源量は、世界で3番目に多いです。
・昼も夜も、また天候に関係なく、いつでも発電できるのは、地熱発電です。
・石油火力発電・太陽光発電・地熱発電のうち、一番二酸化炭素が出る量が少ない発電方法は、地熱発電です。
クイズに答えて、何か貰ったようですが、忘れてしまいました。
パンフレットをいろいろもらってきました。

なかなか興味深いことが載っているようです。



先ほどのクイズで、日本の地熱資源は世界で第3位とのことでしたが、発電量では2015年で、9位です。
1位アメリカ、2位フィリピン 3位インドネシア 4位メキシコ
5位ニュージーランド 6位イタリア 7位アイスランド 8位ケニア 9位日本です。
アメリカは16600GWh/yearで、日本は2687GWh/yearです。
アメリカはすごいですね。日本に形や環境が似ていると言われているニュージーランドでも7000あります。
世界のグラフを見ると、地熱発電の設備容量が急激に増えていることがわかります。
しかし、日本の1年当たりの発電量は、2010年で3064GWhだったのに対し、2015年では2687と減っているようです。これはなぜなのでしょうか?
・・・・・・・・・・
この冊子には、たとえば、日本の地熱発電の歴史なんかも載っています。
1919年に、海軍中尉・山内万寿治氏が大分県別府市で噴気孔の掘削に成功しました。
1966年に、日本初松川地熱発電所(岩手県)が運転を開始しました。
1974年に、サンシャイン計画=石油代替エネルギー政策が始まりました。
1970年代、オイルショックのため、東北・九州地方を中心に発電所が相次いで建築されました。
1990年代は、石油価格が安定したので、地熱発電は横ばいになりました。
2011年、東日本大震災による。再生可能エネルギーの見直しで、地熱発電が期待されるようになりました。
短期間のうちに、地熱発電の場所を決め、発電所を作るのは難しいと思いますが、今後期待される発電方法だと思います。
今回いただいた資料は、時間のあるときに、じっくり読んでみたいと思います。
「JOGMEC」とは、独立行政法人 石油天然ガス金属鉱物資源機構。
石油・天然ガス・金属・石炭・地熱に関する開発支援やメタンハイドレートなどの新エネルギーの開発・資源備蓄事業などをやっている。
ブースの看板の写真を撮ってこなかったのですが「地熱」という文字に引かれて見に行きました。

撮ってきた写真は、これ1枚ですが、日本各地各所で地熱発電が行われているんだなあと驚きました。
原発事故の後、地熱発電がこれからの発電方法として注目されていましたが、火山があるところは国立公園の場合が多く、温泉施設等もあり、そういうところに工場のような施設を作ることができないということで、なかなか開発ができないと聞いていました。その後の状況はどうなのでしょう。
地熱クイズをやりました。
正解
・地熱発電は、マグマの熱を利用しています。
・日本の地熱資源量は、世界で3番目に多いです。
・昼も夜も、また天候に関係なく、いつでも発電できるのは、地熱発電です。
・石油火力発電・太陽光発電・地熱発電のうち、一番二酸化炭素が出る量が少ない発電方法は、地熱発電です。
クイズに答えて、何か貰ったようですが、忘れてしまいました。
パンフレットをいろいろもらってきました。

なかなか興味深いことが載っているようです。



先ほどのクイズで、日本の地熱資源は世界で第3位とのことでしたが、発電量では2015年で、9位です。
1位アメリカ、2位フィリピン 3位インドネシア 4位メキシコ
5位ニュージーランド 6位イタリア 7位アイスランド 8位ケニア 9位日本です。
アメリカは16600GWh/yearで、日本は2687GWh/yearです。
アメリカはすごいですね。日本に形や環境が似ていると言われているニュージーランドでも7000あります。
世界のグラフを見ると、地熱発電の設備容量が急激に増えていることがわかります。
しかし、日本の1年当たりの発電量は、2010年で3064GWhだったのに対し、2015年では2687と減っているようです。これはなぜなのでしょうか?
・・・・・・・・・・
この冊子には、たとえば、日本の地熱発電の歴史なんかも載っています。
1919年に、海軍中尉・山内万寿治氏が大分県別府市で噴気孔の掘削に成功しました。
1966年に、日本初松川地熱発電所(岩手県)が運転を開始しました。
1974年に、サンシャイン計画=石油代替エネルギー政策が始まりました。
1970年代、オイルショックのため、東北・九州地方を中心に発電所が相次いで建築されました。
1990年代は、石油価格が安定したので、地熱発電は横ばいになりました。
2011年、東日本大震災による。再生可能エネルギーの見直しで、地熱発電が期待されるようになりました。
短期間のうちに、地熱発電の場所を決め、発電所を作るのは難しいと思いますが、今後期待される発電方法だと思います。
今回いただいた資料は、時間のあるときに、じっくり読んでみたいと思います。