何を通して「世界」を見るか。
本であったり、音楽であったり、演劇であったり、映画であったり、アートであったり。それがサッカーのようなスポーツである人も多いだろう。当然のことながら、世界を見つめる“接点”が多ければ多いほどオレたちの「世界」は拡がり、よりクリアに見えてくる。見えるというのは大げさかもしれないけれども、少なくともオレたちは世界を意識する。
思考に言葉のハードルはあっても国境のハードルはない。
オレたちがサッカーで見ているものは「世界」の豊かさだ。
「JAPANESE ONLY」問題。
すでに開幕戦で特定のプレーヤーに対して人種差別的なブーイングが起きたという話も出回っていた。土曜日は日本平に行って負けてヤケ酒を呑んでいたので、それどころじゃなかったのだが、日付に変わったあたりで事件を伝えるニュースを目にした。
「JAPANESE ONLY」という横断幕が意味するものはレイシズム以外にないのは多くの記事やブログで指摘されている通りだし、世界中のメディアに拡散されている現状では、この件に関していくら言い繕っても無駄としか言いようがない。10日の報道ではダンマクの提出者は浦和フロントの聞き取り調査に対して「差別の意図はない」と答えているようだが(またメディアでは、ヘイトスピーチ擁護とも取れるような様々な“意訳”を交えて報道しているが)、日本の、そして世界中のレイシストが使う、この言葉を選んだ時点でアウトなのだ。
すでにレイシズムを監視する市民の会によって、Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)宛てた、<差別的横断幕 "JAPANESE ONLY" を出したサポーターおよびこれを放置した浦和レッドダイヤモンズ株式会社に対する断固たる処置を求める署名>も行われている。これはJリーグの中の話だけでは済まない。
JAPANESE ONLY(『オシムの伝言』公式ブログ)
「外国人お断り」-浦和レッズのゴール裏に差別主義横断幕(清義明/連載.jp)
Jではアジア枠が設けられているように、アジア系のプレーヤー、特に日中と共に東北アジアの3強リーグである韓国出身プレーヤーの獲得、起用はもはや特別なものではない。むしろ外国人枠3名とは別に有望な“外国人”が取れるのだから、多くのクラブはこれを有効活用するし、ほとんどのサポーターもそれを歓迎する(たぶん)。スタジアムレベルでは、Jリーグは少なくとも人種差別的な行為は皆無で、健全なリーグだと言える。
しかしJサポのアングラサイトでもある2ちゃんねるのドメサカ板では、半島出身者や在日を獲得すると必ず揶揄する書き込みが現れる。エスパルスならば「チョンパルス」といった具合に。主催者の系列団体に問題があったとはいえ、健太体制時代に韓国で開催されたピースカップに参加したときも中傷が酷かった。さすがにネトウヨの巣窟である。サポの文化(ネタ化)の少なくない部分は2ちゃんねる経由で行われ、熟成される。2ちゃんねるの最大勢力のひとつであり、現実にも決して“アジア枠”を使おうとしなかったレッズの姿勢は少々特殊ではあった。
月刊浦和レッズマガジン3月号に掲載されている「浦和ウルトラ師弟問答」なる企画で、URAWA BOYSの元リーダーである相良純真氏が、こうコメントしている。
<浦和のウルトラは韓国が嫌いだからね。ウチの歴史にはないことだから、最初はいろいろな反応が渦巻くと思う。昔はチョウ(・キジェ)さんがいたけれど、今ほど嫌韓の雰囲気はなかったからね。クラブのスタッフが本人には伝えているそうだけど、本人が相当の覚悟を持って浦和に来ていることは僕も感じるんだよね。そういう選手に対して、僕は頭ごなしに『でもダメだ』とは思えない。>
問題は「クラブのスタッフが本人には伝えている」という部分だ。これはクラブがレイシストの存在を明らかに認めているということだろう。ダンマク提出者の責任やコアサポ周辺の問題だけではなく、フロントがレイシストを看過してきたと言わざるを得ないのではないか。
浦和レッズやJリーグが国内完結型の方向性を持っているならともかく、出自を理由にした排除を求めるレイシズムは、サッカーというスポーツとJリーグのベクトルとは明らかに真逆なのだから、リーグやクラブの処分は適正に行われることを求めたい。
まあ、しかし正直なところ、浦和のフロントやリーグがどのような「処分」を下すのかは現時点では疑問ではある。
去年の清水エスパルスに対するサポーターの軟禁事件、選手バス襲撃事件に対するリーグ、フロントの処分は激甘だったという印象は否めない。さらに「差別事案」といえば、2011年5月のゴトビ核爆弾横断幕事件でのリーグの見解はあまりにも甘かった。浦和フロントは勿論、これまでトラブルに対するリーグの姿勢はほとんど事なかれ主義に近いものだったと言える。それはいかにも「差別に無自覚」な日本らしい立ち振る舞いだった。今回の件に関しても、リーグは「どのようなものであるかは分からないが、万一差別的行為であるならば看過はできない」とコメントしている。「どのようなものであるかは分からないが」ではない。レイシストのメッセージは明らかろう。
これはホームタウン、サポーターといった言葉で、これまで20年に渡ってサッカーを通して日本人の意識に変革を起こしてきたはずのJの理念に反するものといわざるを得ない。
ヘイト行為は一瞬にして多くの人を傷つける。そして残念ながら、「差別の意図はなかった」と安易に言い訳して取り下げることができる。ヘイトダンマクは簡単に降ろすことができるのだ(実際には信じられないことにゲーム終了まで降ろされなかったらしいが…)。実に簡単な話だ。
でも“そのダンマク”を降ろせば話は終わるのか。
日曜日には、またひとつサポーターの行動について残念なニュースがあった。千葉サポーターがゲームに勝ったにもかかわらず、また唯一の得点を挙げたプレーヤーにも関わらず、そのプレーヤーが「ライバルクラブからの期限付き移籍」というだけで、ライバルクラブを中傷するタオルマフラーを手渡してゴール裏でスピーチさせたという事件だ(また悪いことにチームカラーが同色なのだ)。
何て陰湿で、残酷なんだろう。何て男らしくないんだろうと思う。
勿論ゴール裏同士を口汚く罵り、煽り合うことはサポーターの習い性で、ある意味でエンタテイメントとも言える。
そんな煽り合いにも“社会”のルールはある。オレたちはサッカーを通して世界を、そしてオレたちが生きている社会(コミュニティ)を体感する。これは出自や年齢、性別を超えて、自分の愛するクラブの勝利のみを願い、サポートすることを共有する、シングルイシューの社会だ。それを逸脱するような行為は許されるべきではないだろう。そんなものを“相手”として認められるだろうか。
オレたちがスタジアムで争うのはサッカーへの理解、自分たちのクラブへの愛情の深さと熱さだ。
浦和レッズは、10年前の2004年に優勝したというだけで「サポーターだけ」を特集した前代未聞のMOOKが作られるようなクラブだ。こんなクラブは今のところレッズ以外、日本にない。愛情の深さも熱さも認めざるを得ない。
しかし、こんな事件はあまりにもセコ過ぎて、なんて男らしくないんだろうと思う。
そして、こんなことを繰り返すのは、レッズだけではなく、サッカーへの裏切り行為とも言えるものだ。ダンマク首謀者の“彼”は誰と、何を戦っているのか。
最後に、ある浦和サポーターの言葉を引用する。
<僕は、最後まで、サッカーに対してだけは裏切っちゃいけない、と固く誓っている。なぜならば、サッカーは僕のことを決して裏切らないからなんです。>
ヘイトダンマクは降ろされても、サッカーは一生続く。スタジアムのヘイト問題は適正な処分が下ることを願うし、サッカーに興味のない人たちや去年一年ヘイトスピーチと闘ってきた人たちにまでロックオンされてしまった以上は、これまでのような処分では済まされないことは確実だろう。
次の浦和のホームゲームはオレたち、清水戦である。今回の件で心を痛め、署名活動などに動いている浦和サポーターの皆さんには申し訳ないが、オレたちは違うところを見せてやろうぜ(やっぱし煽っておく)。
つまらない連中に四角四面に仕切られる前に、煽り合いながら一緒に前に進むんだよ。
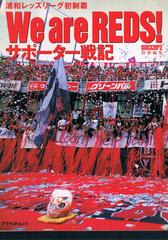
サッカーとレイシズムの問題については、昨年7月に清義明さん主催のイベントが行われたので、こちらも参考に。
挑発と憎悪/サッカーと愛国-フットボールvsレイシズム-(1)
「憎悪」だけでサッカーは楽しめるのか/サッカーと愛国-フットボールvsレイシズム-(2)
【追記】
(当事者ブログ)サガン鳥栖戦における埼スタゴール裏ゲートでの人種差別的弾幕について。(「想像力はベッドルームと路上から」2014年3月9日付)
史上初の勝ち点剥奪か無観客試合 浦和にJが厳罰検討(中日スポーツ 2014年3月12日付)
横断幕 村井チェアマン「差別と認識」(デイリースポーツ 2004年3月12日付)
五野井郁夫 サッカーファンの名誉を挽回する(上)――人種差別に立ち向かった浦和レッズのサポーターたち(WEB RONZA 2014年03月21日)
五野井郁夫 サッカーファンの名誉を挽回する(下)――スポーツが持つ自浄能力(WEB RONZA 2014年03月22日)
本であったり、音楽であったり、演劇であったり、映画であったり、アートであったり。それがサッカーのようなスポーツである人も多いだろう。当然のことながら、世界を見つめる“接点”が多ければ多いほどオレたちの「世界」は拡がり、よりクリアに見えてくる。見えるというのは大げさかもしれないけれども、少なくともオレたちは世界を意識する。
思考に言葉のハードルはあっても国境のハードルはない。
オレたちがサッカーで見ているものは「世界」の豊かさだ。
「JAPANESE ONLY」問題。
すでに開幕戦で特定のプレーヤーに対して人種差別的なブーイングが起きたという話も出回っていた。土曜日は日本平に行って負けてヤケ酒を呑んでいたので、それどころじゃなかったのだが、日付に変わったあたりで事件を伝えるニュースを目にした。
「JAPANESE ONLY」という横断幕が意味するものはレイシズム以外にないのは多くの記事やブログで指摘されている通りだし、世界中のメディアに拡散されている現状では、この件に関していくら言い繕っても無駄としか言いようがない。10日の報道ではダンマクの提出者は浦和フロントの聞き取り調査に対して「差別の意図はない」と答えているようだが(またメディアでは、ヘイトスピーチ擁護とも取れるような様々な“意訳”を交えて報道しているが)、日本の、そして世界中のレイシストが使う、この言葉を選んだ時点でアウトなのだ。
すでにレイシズムを監視する市民の会によって、Jリーグ(公益社団法人日本プロサッカーリーグ)宛てた、<差別的横断幕 "JAPANESE ONLY" を出したサポーターおよびこれを放置した浦和レッドダイヤモンズ株式会社に対する断固たる処置を求める署名>も行われている。これはJリーグの中の話だけでは済まない。
JAPANESE ONLY(『オシムの伝言』公式ブログ)
「外国人お断り」-浦和レッズのゴール裏に差別主義横断幕(清義明/連載.jp)
Jではアジア枠が設けられているように、アジア系のプレーヤー、特に日中と共に東北アジアの3強リーグである韓国出身プレーヤーの獲得、起用はもはや特別なものではない。むしろ外国人枠3名とは別に有望な“外国人”が取れるのだから、多くのクラブはこれを有効活用するし、ほとんどのサポーターもそれを歓迎する(たぶん)。スタジアムレベルでは、Jリーグは少なくとも人種差別的な行為は皆無で、健全なリーグだと言える。
しかしJサポのアングラサイトでもある2ちゃんねるのドメサカ板では、半島出身者や在日を獲得すると必ず揶揄する書き込みが現れる。エスパルスならば「チョンパルス」といった具合に。主催者の系列団体に問題があったとはいえ、健太体制時代に韓国で開催されたピースカップに参加したときも中傷が酷かった。さすがにネトウヨの巣窟である。サポの文化(ネタ化)の少なくない部分は2ちゃんねる経由で行われ、熟成される。2ちゃんねるの最大勢力のひとつであり、現実にも決して“アジア枠”を使おうとしなかったレッズの姿勢は少々特殊ではあった。
月刊浦和レッズマガジン3月号に掲載されている「浦和ウルトラ師弟問答」なる企画で、URAWA BOYSの元リーダーである相良純真氏が、こうコメントしている。
<浦和のウルトラは韓国が嫌いだからね。ウチの歴史にはないことだから、最初はいろいろな反応が渦巻くと思う。昔はチョウ(・キジェ)さんがいたけれど、今ほど嫌韓の雰囲気はなかったからね。クラブのスタッフが本人には伝えているそうだけど、本人が相当の覚悟を持って浦和に来ていることは僕も感じるんだよね。そういう選手に対して、僕は頭ごなしに『でもダメだ』とは思えない。>
問題は「クラブのスタッフが本人には伝えている」という部分だ。これはクラブがレイシストの存在を明らかに認めているということだろう。ダンマク提出者の責任やコアサポ周辺の問題だけではなく、フロントがレイシストを看過してきたと言わざるを得ないのではないか。
浦和レッズやJリーグが国内完結型の方向性を持っているならともかく、出自を理由にした排除を求めるレイシズムは、サッカーというスポーツとJリーグのベクトルとは明らかに真逆なのだから、リーグやクラブの処分は適正に行われることを求めたい。
まあ、しかし正直なところ、浦和のフロントやリーグがどのような「処分」を下すのかは現時点では疑問ではある。
去年の清水エスパルスに対するサポーターの軟禁事件、選手バス襲撃事件に対するリーグ、フロントの処分は激甘だったという印象は否めない。さらに「差別事案」といえば、2011年5月のゴトビ核爆弾横断幕事件でのリーグの見解はあまりにも甘かった。浦和フロントは勿論、これまでトラブルに対するリーグの姿勢はほとんど事なかれ主義に近いものだったと言える。それはいかにも「差別に無自覚」な日本らしい立ち振る舞いだった。今回の件に関しても、リーグは「どのようなものであるかは分からないが、万一差別的行為であるならば看過はできない」とコメントしている。「どのようなものであるかは分からないが」ではない。レイシストのメッセージは明らかろう。
これはホームタウン、サポーターといった言葉で、これまで20年に渡ってサッカーを通して日本人の意識に変革を起こしてきたはずのJの理念に反するものといわざるを得ない。
ヘイト行為は一瞬にして多くの人を傷つける。そして残念ながら、「差別の意図はなかった」と安易に言い訳して取り下げることができる。ヘイトダンマクは簡単に降ろすことができるのだ(実際には信じられないことにゲーム終了まで降ろされなかったらしいが…)。実に簡単な話だ。
でも“そのダンマク”を降ろせば話は終わるのか。
日曜日には、またひとつサポーターの行動について残念なニュースがあった。千葉サポーターがゲームに勝ったにもかかわらず、また唯一の得点を挙げたプレーヤーにも関わらず、そのプレーヤーが「ライバルクラブからの期限付き移籍」というだけで、ライバルクラブを中傷するタオルマフラーを手渡してゴール裏でスピーチさせたという事件だ(また悪いことにチームカラーが同色なのだ)。
何て陰湿で、残酷なんだろう。何て男らしくないんだろうと思う。
勿論ゴール裏同士を口汚く罵り、煽り合うことはサポーターの習い性で、ある意味でエンタテイメントとも言える。
そんな煽り合いにも“社会”のルールはある。オレたちはサッカーを通して世界を、そしてオレたちが生きている社会(コミュニティ)を体感する。これは出自や年齢、性別を超えて、自分の愛するクラブの勝利のみを願い、サポートすることを共有する、シングルイシューの社会だ。それを逸脱するような行為は許されるべきではないだろう。そんなものを“相手”として認められるだろうか。
オレたちがスタジアムで争うのはサッカーへの理解、自分たちのクラブへの愛情の深さと熱さだ。
浦和レッズは、10年前の2004年に優勝したというだけで「サポーターだけ」を特集した前代未聞のMOOKが作られるようなクラブだ。こんなクラブは今のところレッズ以外、日本にない。愛情の深さも熱さも認めざるを得ない。
しかし、こんな事件はあまりにもセコ過ぎて、なんて男らしくないんだろうと思う。
そして、こんなことを繰り返すのは、レッズだけではなく、サッカーへの裏切り行為とも言えるものだ。ダンマク首謀者の“彼”は誰と、何を戦っているのか。
最後に、ある浦和サポーターの言葉を引用する。
<僕は、最後まで、サッカーに対してだけは裏切っちゃいけない、と固く誓っている。なぜならば、サッカーは僕のことを決して裏切らないからなんです。>
ヘイトダンマクは降ろされても、サッカーは一生続く。スタジアムのヘイト問題は適正な処分が下ることを願うし、サッカーに興味のない人たちや去年一年ヘイトスピーチと闘ってきた人たちにまでロックオンされてしまった以上は、これまでのような処分では済まされないことは確実だろう。
次の浦和のホームゲームはオレたち、清水戦である。今回の件で心を痛め、署名活動などに動いている浦和サポーターの皆さんには申し訳ないが、オレたちは違うところを見せてやろうぜ(やっぱし煽っておく)。
つまらない連中に四角四面に仕切られる前に、煽り合いながら一緒に前に進むんだよ。
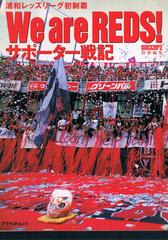
サッカーとレイシズムの問題については、昨年7月に清義明さん主催のイベントが行われたので、こちらも参考に。
挑発と憎悪/サッカーと愛国-フットボールvsレイシズム-(1)
「憎悪」だけでサッカーは楽しめるのか/サッカーと愛国-フットボールvsレイシズム-(2)
【追記】
(当事者ブログ)サガン鳥栖戦における埼スタゴール裏ゲートでの人種差別的弾幕について。(「想像力はベッドルームと路上から」2014年3月9日付)
史上初の勝ち点剥奪か無観客試合 浦和にJが厳罰検討(中日スポーツ 2014年3月12日付)
横断幕 村井チェアマン「差別と認識」(デイリースポーツ 2004年3月12日付)
五野井郁夫 サッカーファンの名誉を挽回する(上)――人種差別に立ち向かった浦和レッズのサポーターたち(WEB RONZA 2014年03月21日)
五野井郁夫 サッカーファンの名誉を挽回する(下)――スポーツが持つ自浄能力(WEB RONZA 2014年03月22日)

















