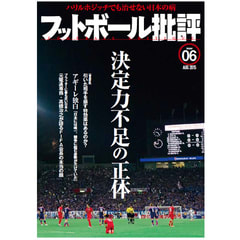ドキュメンタリー~The REAL~「NCAAアメフト モーリス・クラレット 誘惑に負けた全米勝者」
<スポーツを愛するアメリカ国民にとって最大の興味を抱く競技はアメリカンフットボールである。長きにわたるアメリカンフットボールの歴史の中でNFLとカレッジフットボールは洗練されたシステムを築きあげており、それとともに“伝統”や相互利益による“不文律”も数多く存在するようになっている。今回のドキュメンタリーは、その不文律に意義を唱え、その結果選手としてのキャリアも失ったかつてのNCAAスターランニングバック、モーリス・クラレットのストーリーをお送りする。>
(
Jsports ドキュメンタリー~The REAL~)
Bruce Springsteen - Youngstown
堕ちたスーパースターとして名前を挙げられることも多いカレッジフットボールのスーパースター、モーリス・クラレットを描く本作。原題はYoungstown boysという。
かつて鉄鋼の町として栄えながら70年代には鉄鋼業の衰退とその不況が直撃した町は、スプリングスティーンによってバラッドが歌われ、今なお殺人率ではデトロイトを超えるほど治安は悪い。少年時代のクラレットが育ったのはそういう町で、家の中で玄関から撃ち込まれた銃弾が頭をかすめた経験さえあるという。作品の中に登場するクラレットの兄弟、友人もヤングスタウンの「ストリートライフ」を当然のように語る。
そんな土地をそれでも愛し、そこから這い上がろうとしていたのがクラレットだった。抜け出す手段はご多聞に漏れずスポーツかエンタテイメントの世界しかない。
ハイスクール時代にフットボールで頭角を現したクラレットが進路に選んだ選んだのは、90年代にヤングスタウン州立大学で黄金時代を築いたジム・トレッセルが監督を務めるオハイオ州立大学だった。
NFLがアメリカのスポーツの世界では圧倒的王者であるからして、カレッジフットボールの強豪校もそこら辺のプロチームには敵わないほどの熱狂的な人気を誇る。<洗練されたシステム>というのはプロ組織であるNFLと下部組織、育成組織ともいえるNCAAが一体化した高度な<洗練された>スポーツ興行のシステムを作り上げているということで、スーパースターを目指すクラレットにとって避けては通れない道である。
ここでクラレットは通常ならばゲームに出ることすら難しい1年生からランニングバックとして圧倒的な成績を収める。そして無敗を誇っていたマイアミ大学も撃破して全米王者にまでチームを牽引していく。ヤングスタウンの少年は一気にオハイオのスーパースターに駆け上がり、アイドルとなった。そして少年に多くの「大人」が群がり、彼を祭り上げる。
<誘惑>があったとしたらこの瞬間だろう。しかしクラレットがこの誘惑に<負けた>とはどうも思えない。
全米王者を決めるマイアミ大学戦の直前にヤングスタウンの幼馴染がドラッグに関係した射殺事件で殺される。
クラレットはオハイオ州立大の担当者の手配で決戦翌日には葬式に参列するつもりでいたのだが、体育部長のガイガーは大学の規定と書類提出の不備を盾に参列を認めなかった。担当者を通じて書類提出をしていると主張するクラレットはドラッグに絡む事件にスタープレーヤーが関係することを大学関係者が避けたのではないかと訝しみ、「ガイガーは嘘つきだ」と発言する。
この発言が亀裂と憎悪を生むことになる(オハイオ州立大の体育部長という強力な「権力」を持つガイガー氏が慇懃無礼を絵に描いたような白人の悪役ヅラをしている)。クラレットは優勝決定戦後に発覚した車上荒らし疑惑などと併せて全試合、無期限の出場停止処分を受けてしまう。
この騒動にクラレットの味方として伝説のプレーヤーであるジム・ブラウンが参戦した。
曰く、
「ガイガーはまるで奴隷を扱う主人のように行動した」
「ガイガーは敵だ」
黒人でもあるブラウンの主張はそれはそれで間違っていないと思うのだが、クラレットの兄は言う。
「事態が悪化し、これで後に引けなくなった」
NFLと<洗練されたシステム>の中で、絶大な権力を持つ名門大学の体育部長でプライドの高い白人が、連日に渡ってブラウンから「奴隷の主人」「敵」と名指して攻撃されるのだから、ブラウンの言葉がクラレットへの好意であろうが、それがまったく正論であろうが、後戻りはできないだろうし事態は悪化する。
<負けた>とするならば、きっとこの後からだ。本人に圧倒的な実力と才能があろうとも、勝手に祭り上げられたものは無慈悲に引きずり降ろされる。周囲が負けるように仕向ければ、少年はいくらだって「誘惑」に負け続けてしまう。
選手としてプレイの機会を失ったクラレットは、NFLが2軍を持たず、その代わりカレッジフットボールが“2軍”の役割を果たす(高校卒業後、3シーズンを経過した選手でなければドラフトの資格を得ない)という<洗練されたシステム>に異議を唱えざるを得なくなる。ここから話はガイガーの(矮小な)プライドを巡る話から高度なビジネスシステムとの戦いへ拡大していく。
そして高卒2年目でのNFL入団を希望し、司法に訴えたクラレットがオハイオのユニフォームを脱ぎ捨てる写真を掲載した雑誌が発売されると、オハイオのローカリズムの愛憎は沸騰する。ローカリズムが熱ければ熱いほどヒーローは愛され、そしてローカリズムの期待に応えられなくなったヒーローに冷淡になるものだ。
昨日のヒーローは今日の裏切者になる。
連邦裁判所でクラレットの訴えは一旦認められたものの、<洗練されたシステム>を守ろうとするNFLによる控訴審で判決は覆されてしまう。
2005年にデンバー・ブロンコスから指名を受け、ようやく念願のNFL入りを果たしたものの彼の身体はすでにボロボロだった。そして間もなくブロンコスを退団し、ヤングスタウンの「ストリートライフ」に戻ったかつての少年は警察との派手なカーチェイスの末に逮捕、収監された。
その後の誤解と憎悪の転落劇は罠に嵌められたとしか思えない。ガイガーの策謀とまでは言わないが、彼のような大人たちの憎悪と嫉妬と冷淡なビジネスに付け狙われ、実力と才能でスーパースターの階段を上り始めたばかりの少年はひたすら肉体と精神を消耗し、アルコホリックにまで堕ちていた。
この作品の主要な登場人物で、オハイオ州立大の恩師とも言えるジム・トレッセルもクラレットが堕ちていく間は実に冷淡な印象しか持てなかったが、彼自身もチーム内の醜聞でその座を追われることになる。本作のディレクターは「父と子の物語」をひとつのテーマとして挙げていて、クラレットとトレッセルの関係もその目線で描いているのだが(クラレットの家には父親がいなかった)、監督と選手の関係こそ疑似家族的に語っているものの、トレッセルはあくまでもチームという「家」を守るために立ち回っていた印象が残る。
製作者は、特に終盤は「父親(もしくはそれに値する尊敬できる存在)はいた方がいい」というテーマで描いているのだが、どうもこの辺は消化不足というか、食い足りない。クラレットの母親自身、トレッセルがチームから切り離されたクラレットに対して冷淡だったことを一刀両断しているのが可笑しい。母親としてみればそんな「ストーリー」は鼻で笑いたかったのではないか。
父がいなくても子は育つ。
「町(ヤングスタウン)」というコミュニティ、決して洗練されないローカリズムが良くも悪くも子を育てるのだ。
洗練されないローカリズムは洗練されたビジネスシステムに食い物にされがちなものなのだが。
収監後のクラレットが立ち直っていく姿は熱い。
左の腕には「信」という漢字が大きく刻み込まれている。あまりにも大きくてクールな感じはしないのだが、ヤングスタウンボーイらしいと思った。
30 for 30 I Season 2 Episode 15 I Youngstown Boys