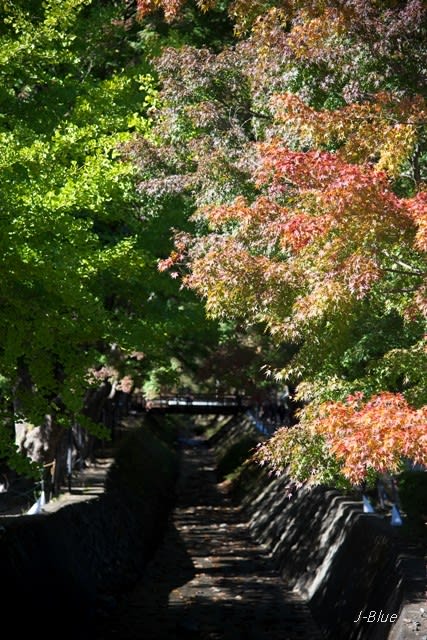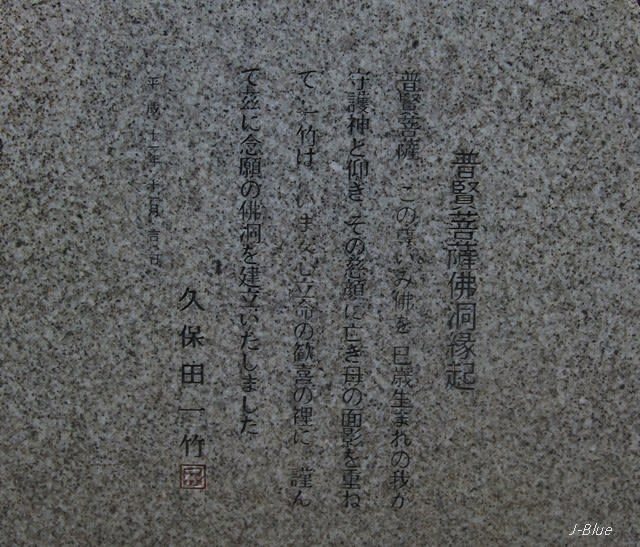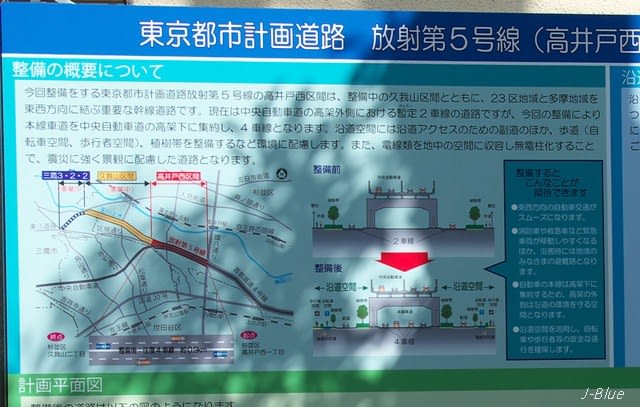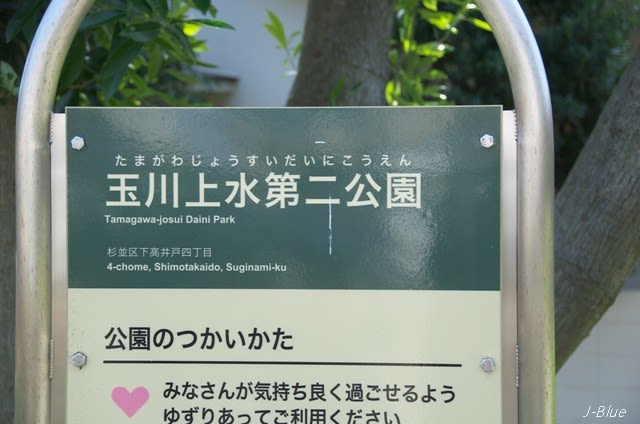「旧御坂峠から黒岳」を周回する(後編)は「黒岳展望台」からの景色から始まります。この地域は先日の台風の影響は殆ど受けなかったようで心配は無用でした。
タイトル写真は富士山を右端に捕らえ「山中湖」方面を撮った物です。方角としては南から少し東よりへ向いた方角です。位置をずらすと「山中湖」が入るのですがこの写真では手前の木が邪魔しています。
御坂山塊「旧御坂峠から黒岳」を周回する(前編)
 前編と同じ地図ですが、展望台で少し休んでから再度「黒岳」山頂へ戻り稜線西方向へ進路を取り「破風山」迄往復するつもりでした。しかしこの急傾斜を「すずらん峠」迄下り「破風山」まで再度登り返し往復となると可也時間と体力が必要そう! 「すずらん峠」の標高が1,620m程「破風山」の標高が1,674m「黒岳」の標高が1,792.7mよく考えると難しそう。
前編と同じ地図ですが、展望台で少し休んでから再度「黒岳」山頂へ戻り稜線西方向へ進路を取り「破風山」迄往復するつもりでした。しかしこの急傾斜を「すずらん峠」迄下り「破風山」まで再度登り返し往復となると可也時間と体力が必要そう! 「すずらん峠」の標高が1,620m程「破風山」の標高が1,674m「黒岳」の標高が1,792.7mよく考えると難しそう。
そんな訳で「すずらん峠」手前1,680m付近の景色の良い所で引き返す決断をしました。
今回後編の行程
黒岳展望台ーー黒岳山頂ーーすずらん峠への途中ーー黒岳山頂ーー黒岳展望台ーー広瀬と御坂トンネル分岐ーー板取沢ーー御坂トンネル駐車場

 写真は「黒岳展望台」から西方向を撮った物、南アルプスと思いますが雪をかぶり「甲斐駒ヶ岳」などの特徴的な容姿が確認できません、手前左の山は「破風山」の稜線と思います。
写真は「黒岳展望台」から西方向を撮った物、南アルプスと思いますが雪をかぶり「甲斐駒ヶ岳」などの特徴的な容姿が確認できません、手前左の山は「破風山」の稜線と思います。
 写真中央の湖は「山中湖」と思えます。その向こうにちょこんと頭を出しているのは箱根「外輪山」では無いかと思えます。
写真中央の湖は「山中湖」と思えます。その向こうにちょこんと頭を出しているのは箱根「外輪山」では無いかと思えます。


 「黒岳山頂」から「破風山」へ向け下り「すずらん峠」手前1,680m付近岩場から撮った「破風山」「黒岳展望台」からの写真と比較するとかなり標高が下がった事が判ります。
「黒岳山頂」から「破風山」へ向け下り「すずらん峠」手前1,680m付近岩場から撮った「破風山」「黒岳展望台」からの写真と比較するとかなり標高が下がった事が判ります。
 同じく右方向に少しカメラを向けます。中央右手前の山は「釈迦ヶ岳」と思います。
同じく右方向に少しカメラを向けます。中央右手前の山は「釈迦ヶ岳」と思います。
 さて下った道を引き返します。急な斜面を標高差100m程ジグザグに登り返します。
さて下った道を引き返します。急な斜面を標高差100m程ジグザグに登り返します。
 そして再度「黒岳展望台」へ戻り、昼食休憩にします。ここで30分程ゆっくりして、この写真のすぐ下を降って行きます。ウイークデーですがハイカーは多くいました。
そして再度「黒岳展望台」へ戻り、昼食休憩にします。ここで30分程ゆっくりして、この写真のすぐ下を降って行きます。ウイークデーですがハイカーは多くいました。
 写真は「三つ峠」と「清八山」の鞍部を撮った物ですが、写真中央南東方向を拡大してみると遙か彼方に微かに都心が写っていました。
写真は「三つ峠」と「清八山」の鞍部を撮った物ですが、写真中央南東方向を拡大してみると遙か彼方に微かに都心が写っていました。
 12時20分下山開始。この下山ルートはマイナーな感じで踏み跡も薄い、この場所で2回の休憩をしましたが滞在時間中此の路を上り下りした人は誰もいませんでした。登山道の指導表示もありません。地図とGPSで確認しないと降り口が有るとは気が付かない状態です。
12時20分下山開始。この下山ルートはマイナーな感じで踏み跡も薄い、この場所で2回の休憩をしましたが滞在時間中此の路を上り下りした人は誰もいませんでした。登山道の指導表示もありません。地図とGPSで確認しないと降り口が有るとは気が付かない状態です。
 写真は数分降った所を振り返って撮った物ですが、急な滑りやすい道で転ばない様に歩くのが精一杯、この後トラロ-プが頻繁に出て来て難儀する事になる。
写真は数分降った所を振り返って撮った物ですが、急な滑りやすい道で転ばない様に歩くのが精一杯、この後トラロ-プが頻繁に出て来て難儀する事になる。
 この写真も降りた後振り向いて撮った物、判りやすい様に赤い線を入れました。岩と土が混じる滑りやすい所で非常に緊張する。雨の日は非常に危険と思う。
この写真も降りた後振り向いて撮った物、判りやすい様に赤い線を入れました。岩と土が混じる滑りやすい所で非常に緊張する。雨の日は非常に危険と思う。
 非常に緊張を強いられる下山道ですが「至広瀬」との私設の指導表示があり間違っていなかったとホッとします。
非常に緊張を強いられる下山道ですが「至広瀬」との私設の指導表示があり間違っていなかったとホッとします。

 こんな所で下手に転ぶと止まらずに何メートルも転げ落ちる。登る時は何とか行くかも知れないが下りは数倍緊張する。
こんな所で下手に転ぶと止まらずに何メートルも転げ落ちる。登る時は何とか行くかも知れないが下りは数倍緊張する。
 こんな痩せ尾根も頻繁に出てくる、一見すると道が無くなっている!・・・・と思う。
こんな痩せ尾根も頻繁に出てくる、一見すると道が無くなっている!・・・・と思う。
 このピークを越えなければならないのか?・・・・と思ったら左にトラバースルートがあった。右手の虎ロープの所は深く切れ落ちている。
このピークを越えなければならないのか?・・・・と思ったら左にトラバースルートがあった。右手の虎ロープの所は深く切れ落ちている。
 次に又かよ!・・・・巻き道は?・・・・・無い! 仕方なしにピークを超しました。
次に又かよ!・・・・巻き道は?・・・・・無い! 仕方なしにピークを超しました。

 左手には「三つ峠」から「清八山」の稜線がクッキリ見えています。あっと言う間に標高を下げた! それだけ急な登山道と云う事です。
左手には「三つ峠」から「清八山」の稜線がクッキリ見えています。あっと言う間に標高を下げた! それだけ急な登山道と云う事です。



 1時間程下り景色が良い岩場で小休止。緊張がほぐれる時! 相変わらず天候は安定している。誰も来ない静かだ! しかし次第に景色は白っぽくなって来ている。
1時間程下り景色が良い岩場で小休止。緊張がほぐれる時! 相変わらず天候は安定している。誰も来ない静かだ! しかし次第に景色は白っぽくなって来ている。
 さて目の前の道を下ります。こうして写真を見ると此所を飛び降りるんじゃ無いかとさえ思える感じです。
さて目の前の道を下ります。こうして写真を見ると此所を飛び降りるんじゃ無いかとさえ思える感じです。



 漸く平坦な所へ出た! 此所は「広瀬」地区へ下る道と「板取沢」から御坂トンネル登山口方面の分岐です。
漸く平坦な所へ出た! 此所は「広瀬」地区へ下る道と「板取沢」から御坂トンネル登山口方面の分岐です。



 そして「板取沢」に出ます。この沢の上部は涸れ沢ですが降りるにつれ次第に水量も増え何回か徒渉する事になります。雨の降る時にこのコースは要注意です。
そして「板取沢」に出ます。この沢の上部は涸れ沢ですが降りるにつれ次第に水量も増え何回か徒渉する事になります。雨の降る時にこのコースは要注意です。
 先日の台風の時はキットかなりの流れになったと思います。徒渉していて時々道が途切れて判らなく成る所が何カ所かありました。
先日の台風の時はキットかなりの流れになったと思います。徒渉していて時々道が途切れて判らなく成る所が何カ所かありました。
 下界の車の音が聞こえる様になると下山口ももうすぐです。この沢沿いの道は岩がゴロゴロする荒れた道で階段も多くとても歩きにくい。
下界の車の音が聞こえる様になると下山口ももうすぐです。この沢沿いの道は岩がゴロゴロする荒れた道で階段も多くとても歩きにくい。

 出発の時にあったもう一台のワンボックスカーは見当たらず。自分の車がポツンと一台有るのみでした。男性二人組はおそらくピストンしたと思われます。14時28分下山完了。
出発の時にあったもう一台のワンボックスカーは見当たらず。自分の車がポツンと一台有るのみでした。男性二人組はおそらくピストンしたと思われます。14時28分下山完了。
データー (YAMAPのデーター)
距離Sスタート~Gゴール迄 7.8km
合計時間 6時間39分
合計休憩時間 50分程?
この後、以前行った事のある日帰り温泉へ行きましたが、今は宿泊専業にして日帰り温泉は止めているとの事・・・・・だったら看板やNetの表示も変更してよ!!(怒)
そんな訳で真っ直ぐ自宅へ帰り風呂掃除をして夕食の支度までしました。かみさんが留守なので・・・・・と云う落ちが付きました!!
タイトル写真は富士山を右端に捕らえ「山中湖」方面を撮った物です。方角としては南から少し東よりへ向いた方角です。位置をずらすと「山中湖」が入るのですがこの写真では手前の木が邪魔しています。
御坂山塊「旧御坂峠から黒岳」を周回する(前編)

そんな訳で「すずらん峠」手前1,680m付近の景色の良い所で引き返す決断をしました。
今回後編の行程
黒岳展望台ーー黒岳山頂ーーすずらん峠への途中ーー黒岳山頂ーー黒岳展望台ーー広瀬と御坂トンネル分岐ーー板取沢ーー御坂トンネル駐車場





写真は河口湖の町並み










しかし相変わらず虎ロープの連続で転ばない様に必死で降ります。












何とか木に掴まりながら降りると、一難去って又一難!

この岩の向こうから降りてきましたが実際は写真よりもっと急な感じです。



ホッとするのもつかの間、すぐ急降下が始まります。ただ岩が混じった道では無いのが救い。

やがて植林帯の急傾斜をつづら折りに道が付いている所に出ました。





やっと行く時に通過した看板の所へ出ました。一瞬気の抜ける様な感じでした。

データー (YAMAPのデーター)
距離Sスタート~Gゴール迄 7.8km
合計時間 6時間39分
合計休憩時間 50分程?
この後、以前行った事のある日帰り温泉へ行きましたが、今は宿泊専業にして日帰り温泉は止めているとの事・・・・・だったら看板やNetの表示も変更してよ!!(怒)
そんな訳で真っ直ぐ自宅へ帰り風呂掃除をして夕食の支度までしました。かみさんが留守なので・・・・・と云う落ちが付きました!!