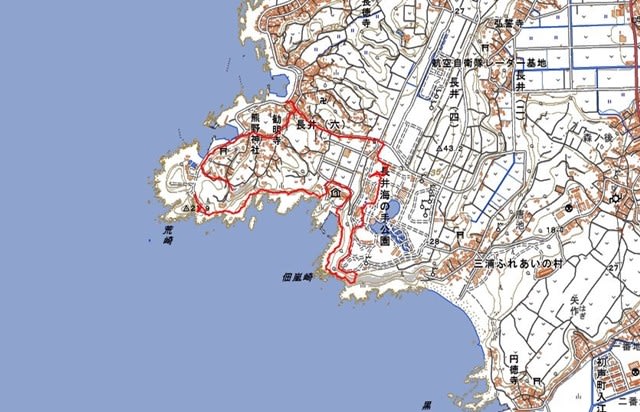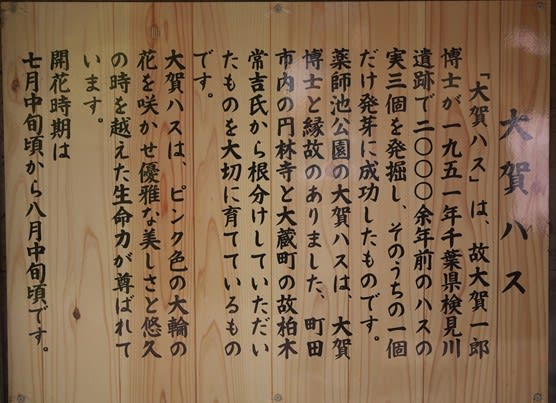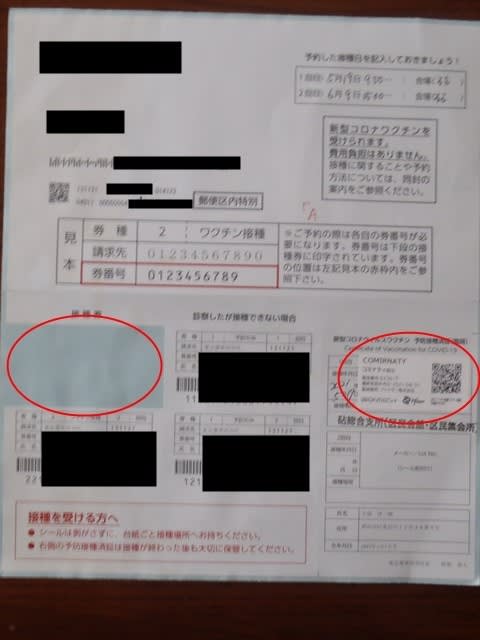前回に引き続き「野川公園・自然観察園」の彼岸花以外の草花を見て行きたいと思います。自然観察園の掲示板には沢山の種類が掲示されて居ましたが、全部を探すのも大変で目に付いた草木だけ撮りました。
 「コムラサキ」ムラサキシキブに似ていますが実の付き方から見るとどうもコムラサキのようです。
「コムラサキ」ムラサキシキブに似ていますが実の付き方から見るとどうもコムラサキのようです。




 ガマズミ、オオカメノキやミヤマガマズミに似ていますが葉の形状と生息する標高が違うようです。いずれの「実」も食用になるようです。
ガマズミ、オオカメノキやミヤマガマズミに似ていますが葉の形状と生息する標高が違うようです。いずれの「実」も食用になるようです。


















 最初「ハッチョウトンボ」と思いましたが一回り大きく調べたら「リスアカネ」かな~、悲しい事に知識が無いと調べるのも難しい!
最初「ハッチョウトンボ」と思いましたが一回り大きく調べたら「リスアカネ」かな~、悲しい事に知識が無いと調べるのも難しい!
これで今回のシリーズは終わります。相変わらず山登りや旅行に出掛ける事を手控えています。若い方達は積極的に出掛けている様ですがどうも籠もり癖が付いて仕舞った様で今一動きにくい!
今の所落ち着き始めていますが次のピークの感染爆発は大きくなりそうな予感!
皆様も十分注意してお過ごし下さい!
追加分 【昨日の月】
一昨日の「中秋の名月」も撮りましたが、酔っ払って撮った為、ピンボケの写真ばかり、リベンジであらかじめ明るい内からカメラの設定など準備。一日遅れの「月」を撮りました。




アレチヌスビトハギの花と種

フジカンゾウと思います。

イヌタデ


ツリフネソウ

ミズヒキ、数ミリの小さな花なので開花した物を綺麗に撮影するのが難しそう。

不明



ゲンノショウコ

キンミズヒキ

ユウガギク

ママコノシリヌグイ



カリガネソウ

アキノタムラソウ?

ヌスビトハギ

ツユクサ

タマゴダケ成長した物

シモバシラ

キツリフネソウ


これで今回のシリーズは終わります。相変わらず山登りや旅行に出掛ける事を手控えています。若い方達は積極的に出掛けている様ですがどうも籠もり癖が付いて仕舞った様で今一動きにくい!
今の所落ち着き始めていますが次のピークの感染爆発は大きくなりそうな予感!
皆様も十分注意してお過ごし下さい!
追加分 【昨日の月】
一昨日の「中秋の名月」も撮りましたが、酔っ払って撮った為、ピンボケの写真ばかり、リベンジであらかじめ明るい内からカメラの設定など準備。一日遅れの「月」を撮りました。