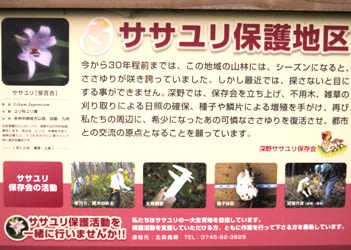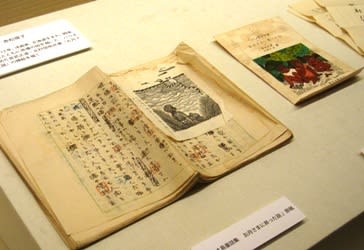【代表種に矢羽根模様の「マコヤナ」、夜には葉を立てて〝睡眠運動〟】
ブラジルを中心とする中南米原産のクズウコン科の多年草。同属の植物は高温多湿を好み、熱帯アメリカに100種以上分布する。花が美しいものもあるが、多くは多彩な葉の模様や形、質感などを楽しむ観葉植物として人気が高い。(写真は園芸品種の「Gekko(月光)」)

カラテアの名はギリシャ語で「籠(かご)」を意味する「カラトス」に由来するという。理由ははっきりしないが、苞葉(ほうば)に包まれて花弁が立ち上がる花穂を籠に見立てたともいわれる。カラテアを代表するのが「マコヤナ」。葉に矢羽根状の模様が入ることから「ゴシキヤバネショウ(五色矢羽根蕉)」の和名を持つ。英名では「ピーコックプラント」と呼ばれるそうだ。
「ランキフォリア」も人気種の1つ。葉は細長い線形で縁が波打つことから「ヤバネシワヒメバショウ(矢羽根皺姫芭蕉)」という和名が付いている。葉の裏側の色は「マコヤナ」同様に赤紫色。他に葉の長さが60cmにもなる大型で「シマウマのような縞」を意味する「セブリナ」、小型で鮮やかなオレンジ色の花を咲かせる「クロカータ」などがある。
カラテアの仲間は日中横に広げていた葉を、夜になると直立させるものが多い。〝睡眠運動〟と呼ばれる性質で、光の加減だけでなく、土の乾き具合や強風などによっても葉を立てるという。葉からの水分の蒸散を防ぐためといわれる。このユニークな性質によって「マコヤナ」や「ランキフォリア」などでは葉の両側で緑と紫のコントラストを楽しめる。