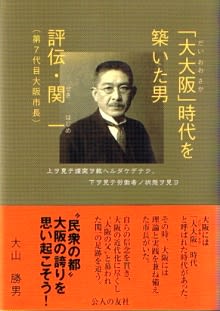【大山勝男著、公人の友社発行】
大阪市がかつて「大大阪(だいおおさか)」と呼ばれた栄光の時代があった。大正後期から昭和初期にかけて。市域の拡張で人口は日本一、商工業でも国内随一の隆盛を誇った。昭和初めの人口約225万人はニューヨーク、ロンドン、ベルリン、シカゴ、パリに次いで世界第6位。工業生産額も全国の14%弱を占め東京を凌いでいた。
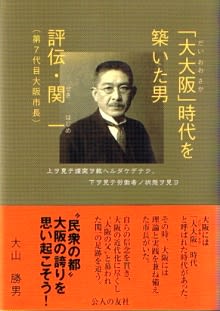
その「大大阪」づくりを牽引したのが第7代市長の関一(せき・はじめ、1873~1935)。東京高等商業学校(現一橋大学)教授から大阪市の助役、市長に転進し、約20年を市勢発展に尽くした。功績としてよく挙がるのが御堂筋の拡幅整備や地下鉄梅田―心斎橋間の開通だが、そのほかにも関が成し遂げたものは多い。中央市場の開設、大阪港の拡張整備、大阪商科大学(現大阪市立大学)の開校、大阪城天守閣の再建、橋梁・上下水道の整備……。まさに今の大阪の礎を築いた第一人者である。
御堂筋の整備は当時6mほどだった道幅を7倍以上に広げ、その下に地下鉄を走らせるという大事業。まだ車が少ない時代。市議会では「飛行場でもつくる気か」というヤジが飛んだ。用地買収の前には船場など沿線の地主や商人たちの頑強な抵抗が立ちはだかった。その壮大な事業が実現したのはなぜか。昭和天皇の大阪行幸が大きな転機になったという。「天子さまのお通りになる道路も造れなくては商都大阪の中心たる船場の恥」。誰からともなくこんな声が沸き上がったそうだ。そして全長4キロの御堂筋は難産の末、昭和12年(1937年)に開通する。着工から約11年、関が没して2年後のことだった。
本書を通じて関の先見の明には改めて驚かされた。「東の後藤新平、西の関一」。後藤は東京市長で、関東大震災直後には「帝都復興院」の総裁として東京復興に尽力した。関はその後藤と並び称された。著者は多くの文献や学者へのインタビューを通して、関の都市政策の底辺に流れる思想・信念を探り求めた。「関一研究会」代表の宮本憲一氏(大阪市大名誉教授)は関を「日本都市史上、理論と実践を統一した最高の市長」と評する。
「上を見て煙突を数えるだけでなく、下を見て労働者の状態を見よ」。本書には関の口癖だったというこの言葉が度々登場する。著者が関の評伝をまとめたいと思ったのもこの言葉を知ったのがきっかけという。関はハード(社会資本)の整備とともに住環境の改善や福祉、緑化、文化振興などソフトにも力を注いだ。「アメニティ」。この言葉を国内で最初に使ったのも関だったという。著者は関の都市政策の目的を「一口で言えば『住み心地よき都市』つまり現代の市民が理想とする『アメニティのある街』をつくることであった」とみる。病に倒れ志半ばで没して80年。関がもし大阪の現状を知ったら、どんなふうに評するのだろうか。



著者大山勝男氏は大阪日日新聞記者の傍ら、ノンフィクションライターとして活躍中。友人や記者仲間からは「勝ちゃん」と慕われている。主に「人権」や「差別問題」をテーマとし、著書に孤高の棋士坂田三吉の素顔を追った『反骨の棋譜 坂田三吉』、戦後8年間アメリカ占領下に置かれた奄美諸島の祖国復帰運動を描いた『愛しのきょら島よ―悲劇の北緯29度線』、庶民史として父の行きざまを綴った『あるシマンチュウの肖像 奄美から神戸へ、そして阪神大震災』などがある。