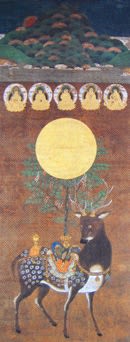【斎藤卓志著、風媒社発行】
童話「ごんぎつね」や「手袋を買いに」で知られる新美南吉は1913年(大正2年)現在の愛知県半田市で生まれ、1943年(昭和18年)結核のため短い生涯を閉じた。今年はちょうど生誕100年、そして没後70年の節目に当たる。本書は南吉自身の日記や多くの聞き書きを基に、作品の生まれた背景やあまり知られていない人となりを丹念に掘り起こした。

代表作「ごんぎつね」が児童雑誌「赤い鳥」に入選し、掲載されたのは南吉18歳のとき。その頃、南吉が生涯兄代わりと慕う巽聖歌(1905~73)に出会う。巽は童謡「たきび」の作詞者として知られる。南吉は巽の紹介で初めて北原白秋に会った。その時の喜びを白秋宛ての手紙にこう記す。「先生のお宅にあがってから、先生が、僕を『新美君』と仰有ったときも、うれしくて、返事も出来ないほどでした」。童話作家として南吉の名が戦後広く知れ渡るようになったのも、1つは巽の尽力によるといわれる。
南吉はその後、東京外国語学校英語部文科に進む。ただ自分の進路については思い悩んでいたようだ。日記に「三つの道に迷ふ。英文学にゆくか、児童文学に行くか、小説にゆくか」と書いた。南吉の日記は9歳の綴り方帳に始まって約20年に及ぶ。その目的について「将来私が小説を書く時私の日記が何かの役に立つやうにと思ふがためである」と記す。著者も「ゴールは小説を書く作家としての生活だった」とみる。
だが南吉には健康への不安が付きまとった。18歳の時には「我が母も我が叔父もみな夭死せし我また三十をこえじと思ふよ。」と詠んでいる。著者は「18歳の南吉が漠然とした形にしても死を意識していたことは重大である」という。そして、21歳の時、初めて喀血する。さらに23歳で2回目の喀血。この間に「墓碑銘」というタイトルの詩も作っている。「結核は死と同義語の時代だった」(著者)。作家や歌人にも結核で若くして逝った人が多い。樋口一葉(享年24)、石川啄木(26)、中原中也(30)、正岡子規(34)……。
南吉は25歳の時、愛知県安城高等女学校の新任教師として1年生の担任になった。専門は英語だが、一番力を入れたのは作文だったといわれる。暇さえあれば生徒の作文を読み、点数をつけ評言を記して生徒に返した。添削で一番多く使った言葉は「実感」だったという。「実感がない」「実感がうすい」……。「大事なのは自分が受けた感じというわけだ」(著者)。
南吉は初めて受け持った生徒たちを4年後に卒業するまで担当し送り出した。「途中で担任交代の話が出たとき全員が泣いて拒んだ」という。先生としていかに慕われていたかが目に浮かぶ。南吉は生徒に原稿の清書も手伝ってもらっていた。生涯独身だったが、女性に関心がなかったわけではない。強く惹かれた女生徒もいたらしい。その経緯は本書の中でわざわざ1章を立てた「先生の恋」に詳しい。
「南吉の童話作家としてのピークはこのあと、昭和17年5月に来る。ふり返ると死まで1年を切ったときにはじまる」(著者)。巽聖歌も「最後の1年のために、短かった全生涯を賭けた」と表現する。とりわけ3~5月には精力的に執筆し、「おぢいさんのランプ」「牛をつないだ椿の木」など9作品を執筆した。その1年後の3月、喉頭結核のため永眠。29歳と7カ月だった。皮肉にも18歳の時詠んだ歌の通りになってしまった。
直後、学校の中央廊下に南吉が「絶筆」と鉛筆書きした一文が張り出されたという。「皆んなと一緒に行った遠足は楽しかった。とても嬉しかったよ。そんな君達に石頭だとかザル頭だとか悪口言ったり叱ったりして悪かった。許してくれたまえ」。南吉の優しさ、温かさが伝わってくる。音楽も好んだ南吉は生前「(チャイコフスキーの)アンダンテ・カンタービレのような(文学)作品を書きたい」とも言っていたそうだ。