(前編 デフレの論理)
2011年秋、物理学者を色めき立たせる出来事があった。名古屋大などの国際研究チームが、素粒子ニュートリノが光より速く飛んだという実験結果を発表をしたからである。残念ながらと言うか、やはりと言うか、翌年には、実験が誤りであったことが判明して終わったが、もし、それが本当だったら、物理学の基本的な理論は、書き換えられていただろう。
この騒動を思い出したのは、himaginaryさんが1/15にリポートした「投資において企業は金利の低下に極めて非感応的」というFRBの論文を見た時だった。それは、こうした事実が判明した場合、経済学は、「金利が投資や貯蓄を調整する」という理論を書き換えたりするのだろうかという連想である。
もちろん、そんなことがないことは、分かっている。金利の効かない事態は、今に始まったわけではない。1930年代のケインズの昔から、繰り返し指摘されており、その道の者には、半ば常識化しているからだ。そもそも、FRBの論文自体が「膨大な実証研究の積み重ねにおいて、金利の投資への実質的な効果に関する実証結果は、良く言って曖昧」と指摘するとおりなのである。
しかし、こうした「実証に合わない理論が罷り通ったまま」という光景は、経済学プロパーには当たり前でも、外の者には相当な違和感があるのではないか。「金利に従って投資するのが合理的であって、そうでないのは偶々であり、長期的には解消される事態」であるとしても、それでは、長らく続いている「今」の現実がどういうものか、いつまで経っても分からない。「不合理な構造を正し、金融緩和が効く社会にすれば良い」では、済ませられない問題だろう。
………
文系の方でも、熱力学のボイル・シャルルの法則は御存知だと思う。気体における、圧力、体積、温度の関係を表したもので、『圧力 = n/体積 × 温度』という式になる。nは定数(粒子数)なので、それを割っている体積を小さくするほど、圧力は高まる関係にある。これが「古典的理想気体」の状態方程式と言われるものだ。何やら、金利を小さくするほど、投資を高められるという関係に似たところがある。
ところが、この法則は、温度の高くない「実在気体」の場合には、当てはまらなくなる。低い温度だと、分子間の引き合う力の影響が無視できなくなり、体積を小さくする過程で、液化が始まり、圧力が高まらなくなるからだ。そこで、分子間力の因子も取り入れ、当てはまるようにしたものが、ファン・デル・ワールスの状態方程式である。『圧力 = n/体積 × 温度 -分子間力』という形になっている。いわば、金利を小さくしていっても、投資が高まらなくなる現象が起こるのである。
経済学の論理は、金利で投資を説明しようとする。だから、金融緩和をして短期や長期の金利を下げ、それでも投資が高まらないと、『金利→投資』というの経路のどこかに構造的な障害があるのではないかと考える。この構図は、『利益→投資』という行動原理をベースにしているので、「短期金利がゼロなら長期金利も」となるだけでなく、金利と同じく利益を左右する『法人減税or投資補助金or規制緩和→投資』の構図で解決しようとする発想にもなる。
しかし、投資を説明する因子が金利や利益以外にもあるとしたら、どうだろう。いわば、分子間力のような、体積減を無効にするような強い力を持つ因子である。これを導入したのが本コラムで紹介する「どうすれば経済学」である。その因子は、「大損する可能性」だ。論理としては、『利益 -大損性 → 投資』である。すなわち、金利をゼロにし、投資促進策を打ったとしても、需要が急減しつつあるといった、損が甚大になりそうな状況では、「大損性」のマイナス因子が大きくなって、投資はなされなくなるわけである。
………
通常、経済学では、「リスク」について、「期待値」で捉える。したがって、1億円投資し、上手く行けば年500万円の利益が得られるプロジェクトの場合、10回に1度1000万円の損が出るものも、100回に1度1億円の損が出るものも、同じ価値があると考える。期待値で考えるから、リスクを織り込んだ利益は400万円で利回り4%となる。裏返せば、1億円の損が出る危険を犯すのは絶対に嫌だから、400万円の利益を得る機会を捨てるなんてことは、選択しないことになっている。
しかし、これは不自然な話である。1億円もの大損の恐れがあると聞けば、普通の人は、手を出さない。なぜなら、期待値を確実に望めるのは、このプロジェクトを100回繰り返せる人に限られるからだ。大概は、人生の限られた時間では、十分に繰り返せず、失意のまま終えることを心配する。そのため、利益を得られる機会を捨てる「不合理」な行動を取る。これは、危険(大損)をカバーするため、保険料(小損)を払う行動と変わらない。
こうして見ると、「リスクを織り込んだ利益」と「大損性」は、別の価値観に基づく、異なる因子であることが分かるだろう。「利益」はできるだけ大きくしたいが、短い人生で受け入れられる「損」の大きさには制約がある。「大損性」は、リスクプレミアムとして、収益率に織り込めるものとは違う。取るか取らないかで、薄く分散ができないからだ。もっとも、政府が「投資失敗保険」でも作って補償すれば、除去できるのかもしれないが、モラルハザードを招くから、とても実用にはならないだろう。
合理的にリスクが取れないのは、人生が限られ、時間軸での分散が無理なことにある。加えて、経済は多数の主体から構成されるから、主体間での分散にも限度がある。したがって、長期的に淘汰される不合理ではない。共同で対処するにしても、現実的なのは、政府が財政で需要を維持し、リーダーシップを発揮するくらいしかない。ゆえに、緊縮財政と金融緩和の組み合わせは、虚しいのである。
………
「現実気体」の状態方程式は、『圧力 = n/体積 × 温度 -分子間力』という形だ。この分子間力は、「a × (n/体積)^2」、すなわち、体積の逆数の2乗で表される。分子間力は、分子の運動エネルギーがもたらす圧力とはまったく異なる力なのに、運動エネルギーを描く要素の「体積」と、定数(a,n)だけで表されるところがポイントだ。このために、分子間力という「概念」のない者にとっては、圧力は、妙に複雑な形の体積の関数に見えるはずだ。
「どうすれば経済学」の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 -大損性』という形になる。古典派的な「理想経済」の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 』である。マイナス因子が「ない」ので、金利が効かないことがある「実在経済」を上手く表現できない。また、あまり意識されないが、「デフレがデフレを呼ぶ」大恐慌や「売りが売りを呼ぶ」株価の崩落のような極端な現象も無理である。
他方、ケインズ経済学の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 -有効需要』であろう。マイナス因子があるから、金利が効かない実態を表現できる。このように、ケインズ経済学は本質を突いているから、投資関数の説明変数に需要を加えると、途端に説明力が高まるということが起こる。むろん、不況への処方箋は、金利の項が不全なら、財政で需要動向を動かせば良いとなる。
ただし、ケインズ経済学の説明では、需要の動向が投資を決めるとなると、投資が生み出すのが所得であり需要だから、堂々巡りになってしまう。同時に、ヒトの行動原理とどう結びついているのかという論争ともなる。むろん、答えは、「利益の機会を捨てても、分散が利かない大損は避けたいという選好」である。需要動向に反応する、不合理であるが正当なる恐怖心が正体だ。これを無理やり「利益追求の選好」に関連づけようとするから、訳が分からなくなる。
………
興味深いのは、こうしたケインズ経済学の「-有効需要」について、「金利」で描くことも、可能なことだ。なぜなら、需要と金利には、間接的で弱いながらも、相関関係があるためだ。これは、「分子間力」を「体積」で表しているのと似た構図となる。だから、古典派的な経済学の立場からすると、金利で説明が全部できるはずなのに、ケインズ経済学は「曖昧な概念」を持ち込んでいるように見えるわけである。
とは言え、「金利」を使い、マイナス因子を作るのは面倒だし、古典派が成功しているわけでもない。「分子間力」の場合、「体積」の逆数の2乗を用いるが、これは、体積が小さくなるにつれ、引力は「相互」に作用するという意味で2乗にする。もし、「金利」についても、逆数の2乗を用いるとしたら、「金利」が低下していく局面では、需要動向への恐怖心が相互作用によって加速度的に強まるとでも解釈するのだろうか。
結局、ケインズ経済学を金利に還元できるかどうかより、金利でマイナス因子を作れるのか、そして、金利で作ったマイナス因子が何を意味するかを理解することが遥かに重要になる。ファン・デル・ワールスの状態方程式が優れていると評価されるのは、単に、体積で記述されているとか、記述が実験データにフィットするとかではなく、マイナス因子の記述が分子間力の本質を端的に示し、直感的に理解できるところにある。
………
ここで、金利が投資を動かす実態を踏まえて置くと、本来の直接に収益性を動かす効果より、住宅と輸出という需要を動かし、その需要が投資を動かす間接的な効果が強い。住宅投資は、自分が住むという確実な需要が見込めるから、金利に感応的である。また、輸出は、金融緩和による自国通貨安という「価格メカニズム」が働くことで増加する。それらが有効需要となり、大損への恐怖心を緩和して、投資を動かすのである。
ハブル崩壊後、「バランスシート不況」になって、金融政策が効かなくなるのは、こうした金利の間接的な効果のルートが潰れているためである。住宅が過大投資の後に効かないのは当たり前だし、世界的なバブルだったりすると、いずこも金融緩和で自国通貨安にならなかったり、外国も景気が悪かったりで、輸出に結びつかないことが起こる。
現在の米国は、QEという金融緩和で、住宅、自動車ローン、株式にプチバブルを作るとともに、ドル安で新興国などへの輸出を伸ばしている。リーマンショックから5年が経ち、金利の間接的な効果のルートが回復を見せている。もっとも、病み上がりの弱く脆いものなので、多少の緊縮財政や緩いテーパリングさえ、これを無にする恐れを孕んでいる。
(つづく)
2011年秋、物理学者を色めき立たせる出来事があった。名古屋大などの国際研究チームが、素粒子ニュートリノが光より速く飛んだという実験結果を発表をしたからである。残念ながらと言うか、やはりと言うか、翌年には、実験が誤りであったことが判明して終わったが、もし、それが本当だったら、物理学の基本的な理論は、書き換えられていただろう。
この騒動を思い出したのは、himaginaryさんが1/15にリポートした「投資において企業は金利の低下に極めて非感応的」というFRBの論文を見た時だった。それは、こうした事実が判明した場合、経済学は、「金利が投資や貯蓄を調整する」という理論を書き換えたりするのだろうかという連想である。
もちろん、そんなことがないことは、分かっている。金利の効かない事態は、今に始まったわけではない。1930年代のケインズの昔から、繰り返し指摘されており、その道の者には、半ば常識化しているからだ。そもそも、FRBの論文自体が「膨大な実証研究の積み重ねにおいて、金利の投資への実質的な効果に関する実証結果は、良く言って曖昧」と指摘するとおりなのである。
しかし、こうした「実証に合わない理論が罷り通ったまま」という光景は、経済学プロパーには当たり前でも、外の者には相当な違和感があるのではないか。「金利に従って投資するのが合理的であって、そうでないのは偶々であり、長期的には解消される事態」であるとしても、それでは、長らく続いている「今」の現実がどういうものか、いつまで経っても分からない。「不合理な構造を正し、金融緩和が効く社会にすれば良い」では、済ませられない問題だろう。
………
文系の方でも、熱力学のボイル・シャルルの法則は御存知だと思う。気体における、圧力、体積、温度の関係を表したもので、『圧力 = n/体積 × 温度』という式になる。nは定数(粒子数)なので、それを割っている体積を小さくするほど、圧力は高まる関係にある。これが「古典的理想気体」の状態方程式と言われるものだ。何やら、金利を小さくするほど、投資を高められるという関係に似たところがある。
ところが、この法則は、温度の高くない「実在気体」の場合には、当てはまらなくなる。低い温度だと、分子間の引き合う力の影響が無視できなくなり、体積を小さくする過程で、液化が始まり、圧力が高まらなくなるからだ。そこで、分子間力の因子も取り入れ、当てはまるようにしたものが、ファン・デル・ワールスの状態方程式である。『圧力 = n/体積 × 温度 -分子間力』という形になっている。いわば、金利を小さくしていっても、投資が高まらなくなる現象が起こるのである。
経済学の論理は、金利で投資を説明しようとする。だから、金融緩和をして短期や長期の金利を下げ、それでも投資が高まらないと、『金利→投資』というの経路のどこかに構造的な障害があるのではないかと考える。この構図は、『利益→投資』という行動原理をベースにしているので、「短期金利がゼロなら長期金利も」となるだけでなく、金利と同じく利益を左右する『法人減税or投資補助金or規制緩和→投資』の構図で解決しようとする発想にもなる。
しかし、投資を説明する因子が金利や利益以外にもあるとしたら、どうだろう。いわば、分子間力のような、体積減を無効にするような強い力を持つ因子である。これを導入したのが本コラムで紹介する「どうすれば経済学」である。その因子は、「大損する可能性」だ。論理としては、『利益 -大損性 → 投資』である。すなわち、金利をゼロにし、投資促進策を打ったとしても、需要が急減しつつあるといった、損が甚大になりそうな状況では、「大損性」のマイナス因子が大きくなって、投資はなされなくなるわけである。
………
通常、経済学では、「リスク」について、「期待値」で捉える。したがって、1億円投資し、上手く行けば年500万円の利益が得られるプロジェクトの場合、10回に1度1000万円の損が出るものも、100回に1度1億円の損が出るものも、同じ価値があると考える。期待値で考えるから、リスクを織り込んだ利益は400万円で利回り4%となる。裏返せば、1億円の損が出る危険を犯すのは絶対に嫌だから、400万円の利益を得る機会を捨てるなんてことは、選択しないことになっている。
しかし、これは不自然な話である。1億円もの大損の恐れがあると聞けば、普通の人は、手を出さない。なぜなら、期待値を確実に望めるのは、このプロジェクトを100回繰り返せる人に限られるからだ。大概は、人生の限られた時間では、十分に繰り返せず、失意のまま終えることを心配する。そのため、利益を得られる機会を捨てる「不合理」な行動を取る。これは、危険(大損)をカバーするため、保険料(小損)を払う行動と変わらない。
こうして見ると、「リスクを織り込んだ利益」と「大損性」は、別の価値観に基づく、異なる因子であることが分かるだろう。「利益」はできるだけ大きくしたいが、短い人生で受け入れられる「損」の大きさには制約がある。「大損性」は、リスクプレミアムとして、収益率に織り込めるものとは違う。取るか取らないかで、薄く分散ができないからだ。もっとも、政府が「投資失敗保険」でも作って補償すれば、除去できるのかもしれないが、モラルハザードを招くから、とても実用にはならないだろう。
合理的にリスクが取れないのは、人生が限られ、時間軸での分散が無理なことにある。加えて、経済は多数の主体から構成されるから、主体間での分散にも限度がある。したがって、長期的に淘汰される不合理ではない。共同で対処するにしても、現実的なのは、政府が財政で需要を維持し、リーダーシップを発揮するくらいしかない。ゆえに、緊縮財政と金融緩和の組み合わせは、虚しいのである。
………
「現実気体」の状態方程式は、『圧力 = n/体積 × 温度 -分子間力』という形だ。この分子間力は、「a × (n/体積)^2」、すなわち、体積の逆数の2乗で表される。分子間力は、分子の運動エネルギーがもたらす圧力とはまったく異なる力なのに、運動エネルギーを描く要素の「体積」と、定数(a,n)だけで表されるところがポイントだ。このために、分子間力という「概念」のない者にとっては、圧力は、妙に複雑な形の体積の関数に見えるはずだ。
「どうすれば経済学」の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 -大損性』という形になる。古典派的な「理想経済」の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 』である。マイナス因子が「ない」ので、金利が効かないことがある「実在経済」を上手く表現できない。また、あまり意識されないが、「デフレがデフレを呼ぶ」大恐慌や「売りが売りを呼ぶ」株価の崩落のような極端な現象も無理である。
他方、ケインズ経済学の論理は、『投資 = n/金利 × 温度 -有効需要』であろう。マイナス因子があるから、金利が効かない実態を表現できる。このように、ケインズ経済学は本質を突いているから、投資関数の説明変数に需要を加えると、途端に説明力が高まるということが起こる。むろん、不況への処方箋は、金利の項が不全なら、財政で需要動向を動かせば良いとなる。
ただし、ケインズ経済学の説明では、需要の動向が投資を決めるとなると、投資が生み出すのが所得であり需要だから、堂々巡りになってしまう。同時に、ヒトの行動原理とどう結びついているのかという論争ともなる。むろん、答えは、「利益の機会を捨てても、分散が利かない大損は避けたいという選好」である。需要動向に反応する、不合理であるが正当なる恐怖心が正体だ。これを無理やり「利益追求の選好」に関連づけようとするから、訳が分からなくなる。
………
興味深いのは、こうしたケインズ経済学の「-有効需要」について、「金利」で描くことも、可能なことだ。なぜなら、需要と金利には、間接的で弱いながらも、相関関係があるためだ。これは、「分子間力」を「体積」で表しているのと似た構図となる。だから、古典派的な経済学の立場からすると、金利で説明が全部できるはずなのに、ケインズ経済学は「曖昧な概念」を持ち込んでいるように見えるわけである。
とは言え、「金利」を使い、マイナス因子を作るのは面倒だし、古典派が成功しているわけでもない。「分子間力」の場合、「体積」の逆数の2乗を用いるが、これは、体積が小さくなるにつれ、引力は「相互」に作用するという意味で2乗にする。もし、「金利」についても、逆数の2乗を用いるとしたら、「金利」が低下していく局面では、需要動向への恐怖心が相互作用によって加速度的に強まるとでも解釈するのだろうか。
結局、ケインズ経済学を金利に還元できるかどうかより、金利でマイナス因子を作れるのか、そして、金利で作ったマイナス因子が何を意味するかを理解することが遥かに重要になる。ファン・デル・ワールスの状態方程式が優れていると評価されるのは、単に、体積で記述されているとか、記述が実験データにフィットするとかではなく、マイナス因子の記述が分子間力の本質を端的に示し、直感的に理解できるところにある。
………
ここで、金利が投資を動かす実態を踏まえて置くと、本来の直接に収益性を動かす効果より、住宅と輸出という需要を動かし、その需要が投資を動かす間接的な効果が強い。住宅投資は、自分が住むという確実な需要が見込めるから、金利に感応的である。また、輸出は、金融緩和による自国通貨安という「価格メカニズム」が働くことで増加する。それらが有効需要となり、大損への恐怖心を緩和して、投資を動かすのである。
ハブル崩壊後、「バランスシート不況」になって、金融政策が効かなくなるのは、こうした金利の間接的な効果のルートが潰れているためである。住宅が過大投資の後に効かないのは当たり前だし、世界的なバブルだったりすると、いずこも金融緩和で自国通貨安にならなかったり、外国も景気が悪かったりで、輸出に結びつかないことが起こる。
現在の米国は、QEという金融緩和で、住宅、自動車ローン、株式にプチバブルを作るとともに、ドル安で新興国などへの輸出を伸ばしている。リーマンショックから5年が経ち、金利の間接的な効果のルートが回復を見せている。もっとも、病み上がりの弱く脆いものなので、多少の緊縮財政や緩いテーパリングさえ、これを無にする恐れを孕んでいる。
(つづく)


















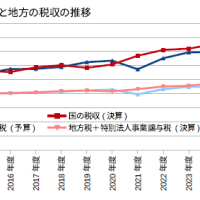





ファン・デル・ワールスの状態方程式 圧力 = n/体積 × 温度 ー分子間力
分子間力が追加された訳で・・・自然科学の発展とは、こうした「新しい要因」の追加でなしとげられてきたわけですね。重力加速度と万有引力の法則の関係も同じです。
mという質量にかかる力 F=mg
mという質量にかかる力 F=m×M×G/rの2乗 万有引力の法則
なおGは定数
つまり、上の式の重力加速度gは、下の万有引力の法則で見ると「M×G/rの2乗」だったわけです。ここでは、新たに(地球の引力について万有引力を見るときは)地球の質量Mに、地球の中心部と地表の距離rという2つの要因が追加されています。地表にある物体と地球の中心部との距離は、ほとんど変わらないですし、地球の質量も変わらないから、定数に見えていたわけで。
自然科学では、科学の発展とは、多くの場合、基礎的な方程式に新しい要因を追加することです。ところが、経済学では、基礎的な方程式に疑問を持つことなく、小手先の先端部をこねくりまわしているだけのように見えます。その方が「高度」なことをやっているように感じられるからでしょうか。あるいは、経済学の科学としての歴史が浅いために、科学の発展がどのようにして行われるかを経済学者が理解していないためでしょうか。