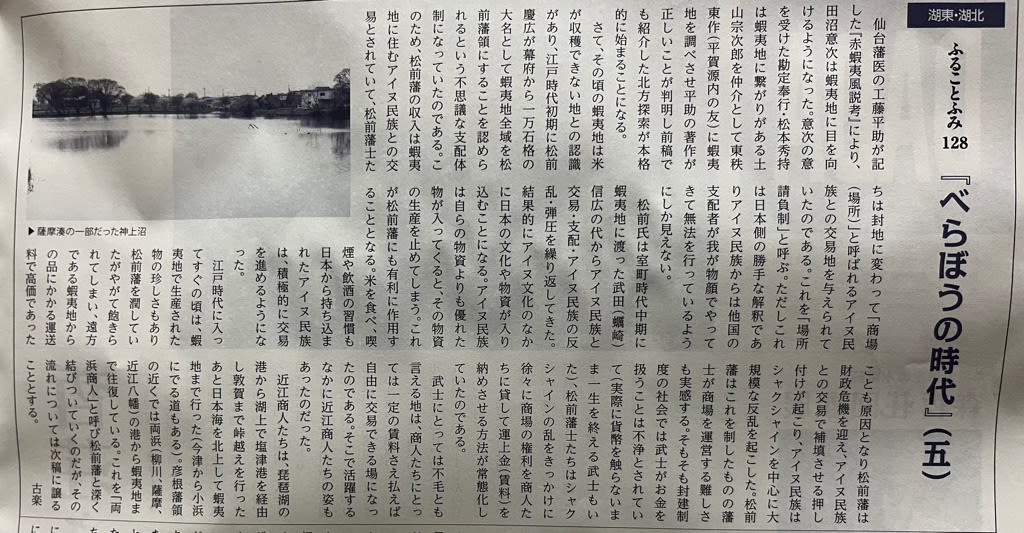
仙藩医の工藤平助が記した『赤蝦夷風説考』により、田沼意次は蝦夷地に目を向けるようになった。意次の意を受けた勘定奉行・松本秀持は蝦夷地に繋がりがある土山宗次郎を仲介として東秩東作(平賀源内の友)に蝦夷地を調べさせ平助の著作が正しいことが判明し前稿でも紹介した北方探索が本格的に始ますことになる。
さて、その頃の蝦夷地は米が収穫できない地との認識があり、江戸時代初期に松前慶広が幕府から一万石格の大名として蝦夷地全域を松前藩領にすることを認められるという不思議な支配体制になっていたのである。このため、松前藩の収入は蝦夷地に住むアイヌ民族との交易とされていて、松前藩士たちは封地に変わって「商場(場所」と呼ばれるアイヌ民族との交易地を与えられていたのである。これを「場所請負制」と呼ぶ。ただしこれは日本側の勝手な解釈でありアイヌ民族からは他国の支配者が我が物顔でやってきて無法を行っているようにしか見えない。松前氏は室町時代中期に蝦夷地に渡った武田(蠣崎)信広の代からアイヌ民族と交易・支配・アイヌ民族の反乱・弾圧を繰り返してきた。結果的にアイヌ文化のなかに日本の文化や物資が入り込むことになる。アイヌ民族は自らの物資よりも優れた物が入ってくるとその物資の生産を止めてしまう。これが松前藩にも有利に作用することとなる。米を食べ、喫煙や飲酒の習慣も日本から持ち込まれたアイヌ民族は、積極的に交易を進めるようになった。江戸時代に入ってすぐの頃は、蝦夷地で生産された物の珍しさもあり松前藩を潤していたがやがて飽きられてしまい、遠方である蝦夷地からの品にかかる運送料で高価であったことも原因となり松前藩は財政危機を迎え、アイヌ民族との交易で補填させる押し付けが起こり、アイヌ民族はシャクシャインを中心に大規模な反乱を起こした。松前藩はこれを制したものの藩士が商場を運営する難しさも実感する。
そもそも封建制度の社会では武士がお金を扱うことは不浄とされていて(実際に貨幣を触らないまま一生を終える武士もいた)、松前藩士たちはシャクシャインの乱をきっかけに徐々に商場の権利を商人たちに貸して運上金(賃料)を納めさせる方法が常態化していたのである。
武士にとっては不毛とも言える地は、商人たちにとっては一定の賃料さえ払えば自由に交易できる場になったのである。そこで活躍するなかに近江商人たちの姿もあったのだった。
近江商人たちは、琵琶湖の港から湖上で塩津港を経由し敦賀まで峠越えを行ったあと日本海を北上して蝦夷地まで行った(今津から小浜にでる道もある)。彦根藩領の近くでは両浜(柳川、薩摩、近江八幡)の港から蝦夷地まで往復している。これを「両浜商人」と呼び松前藩と深く結びついて行くのだが、その流れについては次稿に譲ることとする。
薩摩湊の一部だった神上沼


























